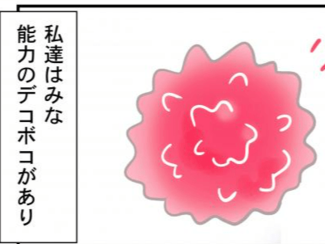2学期から、小学6年生の娘が主人の田舎に転校することになりました。
そこは、東京生まれの私にとって、映画の中でしか見たことのないような緑豊かな片田舎で、日々カルチャーショックの連続です。
私の知る限り、信号は町にひとつしかなく、小さなスーパーと、町役場と小学校が隣接した場所が唯一の繁華街で、メインストリートには、いのししの親子が平然とした態度で歩いています。
夏休みのしおりには当たり前に書かれている、「子どもだけでショッピングモールやゲームセンターに行かない」という文字はなく、代わりに書かれているのは、「子どもだけで山の中へ入らない」という、初めて目にする注意事項でした。もちろん、ショッピングモールも、ゲームセンターもありません。
(そして、先生から「新学期からランドセルにつけて登校してください」と手渡されたものは、防犯ブザーではなく、クマ鈴という衝撃!)
町の子どもたちはみな人懐っこく、年の近い子ども同士で、よく遊びます。それを自然に周りの大人たちが見守っており、近頃あまり目にしなくなった、昭和の時代の子ども達の姿が、そこにはありました。
こういう田舎に暮らしていると、「HSP」という概念も、それ以外の個性の名前も、あまり必要がなくなってきます。
やはりいろんな人がいることはいますが、「この人はこういう人。だからこうなんだ」と思うだけで、特別視しなくても、みな普通に生活しています。
「HSP」という概念が必要になるのは、敏感なるがゆえに生きづらさを感じている人が、生きやすくなるためのもので、別段困ることがなければ、このレッテル自体、いらなくなるのです。
町の人を見ているとつくづく思います。おとなしい人、情熱あふれる人、優しい人、おせっかいな人、同じ人はひとりとしていませんが、みんな、自分とは違うところを面白がって、楽しい話題にし、全てを受け入れて暮らしています。
失敗しないように気をつけながら生活をするのが普通ですが、ここでは、失敗したら「大好物!」とばかりにみんなが食いついてきて、ユーモアを交えながら人から人へと語られ、何度も笑って、いつまでも愉快な気持ちにさせられます。
「下着泥棒が出た」「高速道路で車が横転した」などの大ネタは、何年にも渡って話題に上がり、その度にみんなで大笑いします。
個性は一人一人違うから面白い。
みんなと同じ感性でないといけないなんて、そんなのおかしいですよね。
毎年、田舎に帰ると、とても居心地がいいと感じていましたが、それは「あなたはあなたでいいんだよ」という優しさによるものなのだろうと思います。その中で過ごすと、ゆりかごで揺られているような安心感に包まれるのです。
「あなたはあなたでいい。私は私でいい」みんなが当たり前のようにそう思う世の中になれば、どんなに暮らしやすくなるでしょう。
杓子定規にあてはめるのではなく、「あなたはこうなんだね、素晴らしいね」「あなたはこう思うんだね、面白いね」と、互いの違いを尊重し、それぞれの良さを発揮できるようになることを願わずにおれません。ここの田舎の人たちのように。
我が家の「HSC」の娘は、いろいろあって疲れ気味でしたが、田舎の人々の優しさに包まれてだいぶリラックスしたようで、2学期が楽しみになりました。
傷つきやすいこと、刺激を受けやすいことには変わりありませんが、「HSC」が自分らしく過ごせる場所にいると、敏感な部分は目立たなくなって、普通の子と変わりなくなってくるのです。

◆太田知子(おおた・ともこ)◆
1975年、東京都生まれ。主に子どものイラストを中心に描くイラストレーター。小学生と高校生の2児の母。
著書『子育てハッピーたいむ ななとひよこの楽しい毎日』1~3。『りんごちゃんと、おひさまの森のなかまたち』1~5。『HSC子育てあるある うちの子は ひといちばい敏感な子!』。