連載は最終回となりました。終わりに、私が支援で大切にしている「自己肯定感」について記しておきたいと思います。
みなさんは「自己肯定感」という言葉をご存じでしょうか。一般的には「良いも悪いも含め、『自分は自分で大丈夫』というポジティブな感覚」との意味があるようですが、実は、私はこの「自己肯定感を育むこと」が支援をする上でとても大切なキーワードだと思っています。
「どうせ自分なんて」と一歩を踏み出せない若者
私はこれまで、自分の良さ(強み)に気づくことなく、「どうせ自分なんて」と自己肯定感を下げ、チャレンジする前に立ち止まってしまっている多くの若者に出会ってきました。「一緒に頑張ってみようか」と誘ってみても、なかなか最初の一歩が踏み出せない人たちでした。知識や働く体力がありながらも、その自己肯定感の低さが、就職できない、できても長続きしない大きな原因になっていました。
自己努力だけで肯定感育むのは難しい
そんな若者に出会う度に、「人生を共に伴走してくれる支援者がいてくれたら、彼らはもっと輝ける人生を歩んでいたのではないだろうか」と思うと同時に、「彼らが社会に踏み出せない原因を、果たして彼らだけの責任として終わらせていいのだろうか」との強い憤りをも感じるのです。
自己肯定感は、他者から自分がどのように見られているかを感じることから育まれるものと言われています。そのため、自分を客観的に見ることの苦手な人たちが自己努力だけで自己肯定感を育むことは容易なことではないでしょう。
どうすればできるか具体的に伝え続ける
しかし、私たちが彼らに対し、できていることとできていないことを正しく伝え、さらには、できていないことはどのようにすればできるようになるのかを具体的に伝え続けることができれば、自信を持ってできる行動が増え、それが自己肯定感を育むことにつながるのではないでしょうか。きっと彼らは、私たちからの「あきらめない支援」を待ち望んでくれていることでしょう。

「支援とは何か」と聞かれると、私たちは、つい、「できないことをできるようにすること」と答えがちですが、実は、「既にできていることや得意なこと(好きなこと)を継続できる環境を整えること」も、とても大切な支援なのではないでしょうか。
チャレンジしようとする気持ち 認めて
一見できて当たり前に見えることでも、特性のある人にとってはとてつもなくハードルの高い場合があります。そんな時に、チャレンジしようとする気持ちを認めてあげることで、彼らの良い所がたくさん見えてくるようになります。私たちが彼らの良い所を見つけようとすることが、実は自己肯定感を育むための一番の近道なのかもしれませんね。ぜひ、「自己肯定感という宝物探しの旅」に出かけてみませんか。
(おわり)
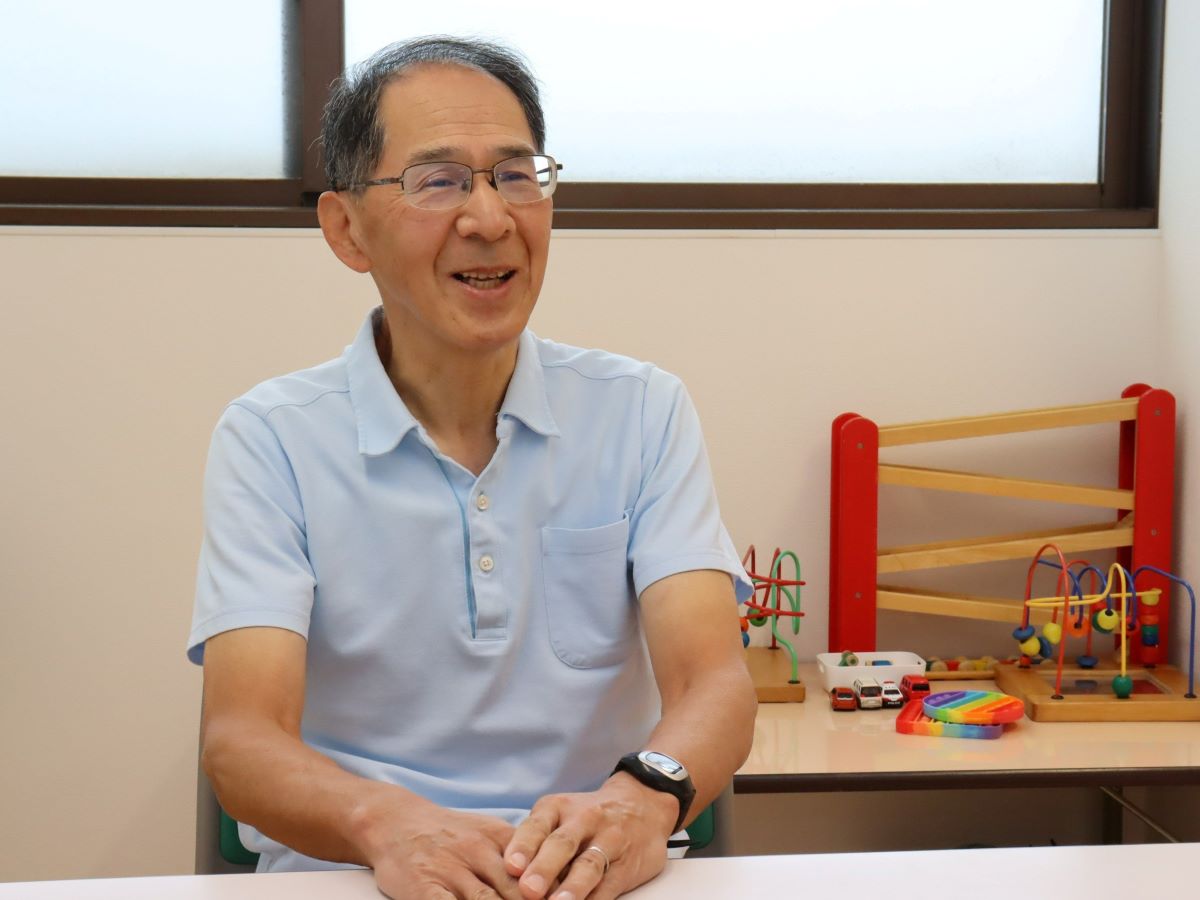
北川忠(きたがわ・ただし) 富山大教育学部卒。社会福祉法人めひの野園で長年、自閉症や成人の発達障害者の支援にたずさわり、2016年から県発達障害者支援センター「ほっぷ」に赴任。24年から社会福祉法人新川会、地域生活相談室に勤務。現在も発達障害に関する研修会講師や相談業務を行う。富山短大幼児教育学科非常勤講師。67歳。








