今回は「家族支援」について触れたいと思います。私は機会あるごとに、「発達障害の人達が住みやすい社会は、実は誰もが住みやすい社会なのですよ」とお話しをしてきました。そのためには、ご家族を地域の中でしっかりと支えて行く仕組みづくりが必要であり、ご家族への支援は当事者さんへの支援と同じくらい、むしろそれ以上に大切であると感じているからです。
「診断名聞き どうやって帰ったか記憶ない」
以前、ある研修会で家族支援についての講師依頼を受けたことがあります。主催者からの要望は「お子さんの障害を受容できていない保護者への指導法を助言いただきたい」というものでした。しかし私はその講演の冒頭で、「本日の内容にはそぐわないものとなることをお許し願います」と前置きした上で、「そもそも、我が子の障害を受容できる親が本当にいるのでしょうか。私が親なら一生涯受容できません」と言い切ってしまいました。
その理由は、複数の保護者からお聞きした診断名の告知を受けた時の話にあります。あるお母さまは、「覚悟はしていたが、告知の後は帰りの車中で涙が止まらなかった」と話されました。また、あるお母さまは、「病院の駐車場に車を置いたまま、どうやって帰ってきたか記憶がない」とも話されました。さらには、「家に帰って夫や義父母から責められると思ったら家に帰れなかった。このまま、この子と川にでも」と涙ながらに話されるお母さまも。とても子育てを楽しめる状況ではなかったでしょう。

「しつけのできない親」とレッテル
さらに、地域の中では「しつけのできない親」とのレッテルを貼られ、地域外で専門教育(療育)を受けるうち、知らず知らず孤立し、あたかも犯罪者であるかような肩身の狭い暮らしを強いられてきたというご家族のお話しは、衝撃として私の心に深く刻まれています。
私たちから彼らの世界に飛び込む
2005年の発達障害者支援法の施行に伴い、発達障害という言葉は明らかに広がりを見せました。しかし、「誰もが住みやすい共生社会は、まだまだ道のり遠し」と言わざるを得ません。その実現に向けて、まずは当事者さんやご家族さんを中心に据え置いた社会づくりを進めてはどうでしょうか。かのローナ・ウィング氏(自閉症の研究で知られる児童精神科医)は「私たちは彼らの世界に飛び込まなければならない。なぜなら、彼らが私たちの世界に入ってくることはできないからだ」と共生社会づくりの糸口を諭してくれています。今、まさに、実践の時ではないでしょうか。
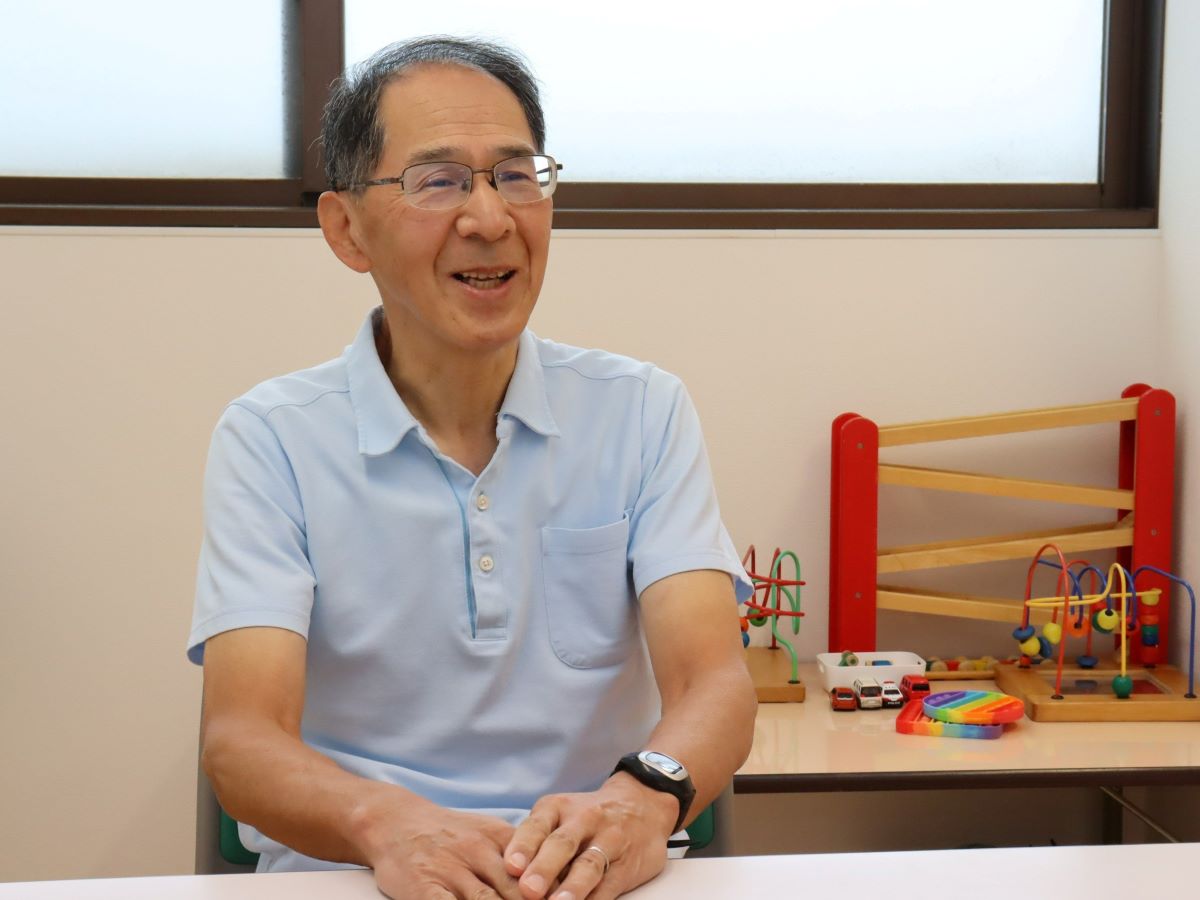
北川忠(きたがわ・ただし) 富山大教育学部卒。社会福祉法人めひの野園で長年、自閉症や成人の発達障害者の支援にたずさわり、2016年から県発達障害者支援センター「ほっぷ」に赴任。24年から社会福祉法人新川会、地域生活相談室に勤務。現在も発達障害に関する研修会講師や相談業務を行う。富山短大幼児教育学科非常勤講師。67歳。









