今回は、こだわりの強さという特性と支援について、私が出会った当事者さんとのエピソード(失敗談)を交えてご紹介します。
「要らない物 おいてこられよ」にパニック
富山市の障害者支援施設「めひの野園」に在職中、毎日大きなリュックを担ぎ片道10㎞以上の道のりを自転車で通うDさんに出会いました。リュックの中身が雑誌、フィギュア、新聞広告など、作業に無用なものばかりだったため、気を利かせたつもりで「毎日大変やろ、こんな要らない物、全部家においてこられよ」と伝えました。すると、本人は突然独り言を発して大パニックとなり、それ以降通所しなくなってしまいました。Dさんはリュックを担いたまま通所することにこだわっておられたのです。

(画像提供:PIXTA)
めひの野園には、作業の手順、園内を歩くコース、食事の食べる順番、衣類の脱着の順番などに強いこだわりを持った利用者さんがたくさんおられたのですが、私がその行動を無理やり制止したり対象物を隠したりしたことで、より状況を困難にしてしまった苦い経験があります。
こだわりの特性というのは、決められた手順や一度決められたルールに強く執着するという特性です。また、偏食や成績が一番であることへの執着、ゲームやギャンブルへの過度の没頭など、一見こだわりに見えないこれらの行動も、実はこだわりが原因と考えられています。
こだわりは安心を得るための作業
こだわりについてはいろんな捉え方がありますが、私は「安心を得るための作業」と考えています。見通しのきかない不安感を軽減する為の行動(儀式)とも言えます。強く禁止すると諦める場合もありますが、不安が改善されなければ別のこだわり作ったり一層しがみつこうとしたりして、より症状が重篤になる場合が多かったように思います。
数年前、発達障害の当事者を長年診察してきた信州大学医学部の本田秀夫先生にお話を聞く機会がありました。先生はこのような状況を「こだわり保存の法則」と名付け、こだわりに対するエネルギーの総量は変わらないことを説明してくださいました。私も浅学ながら、本田先生のネーミングには大変共感を覚えました。生死にかかわるこだわりは強制的に止めることも必要ですが、こだわりを生かし、それを逆手にとって支援につなげる工夫も大切ではないでしょうか。
認めてあげることも支援
富山県発達障害者支援センター「ほっぷ」に在職中も、Dさんと同じように、大きな荷物を持って面談に来られる成人の方がいらっしゃいました。Dさんとの失敗を踏まえて「今日も荷物の中をたくさん見せてくれるんだね」と話すと、「僕の大切な宝物だよ」と笑顔で答えてくれました。認めてあげることはとても大切な支援につながるんですね。
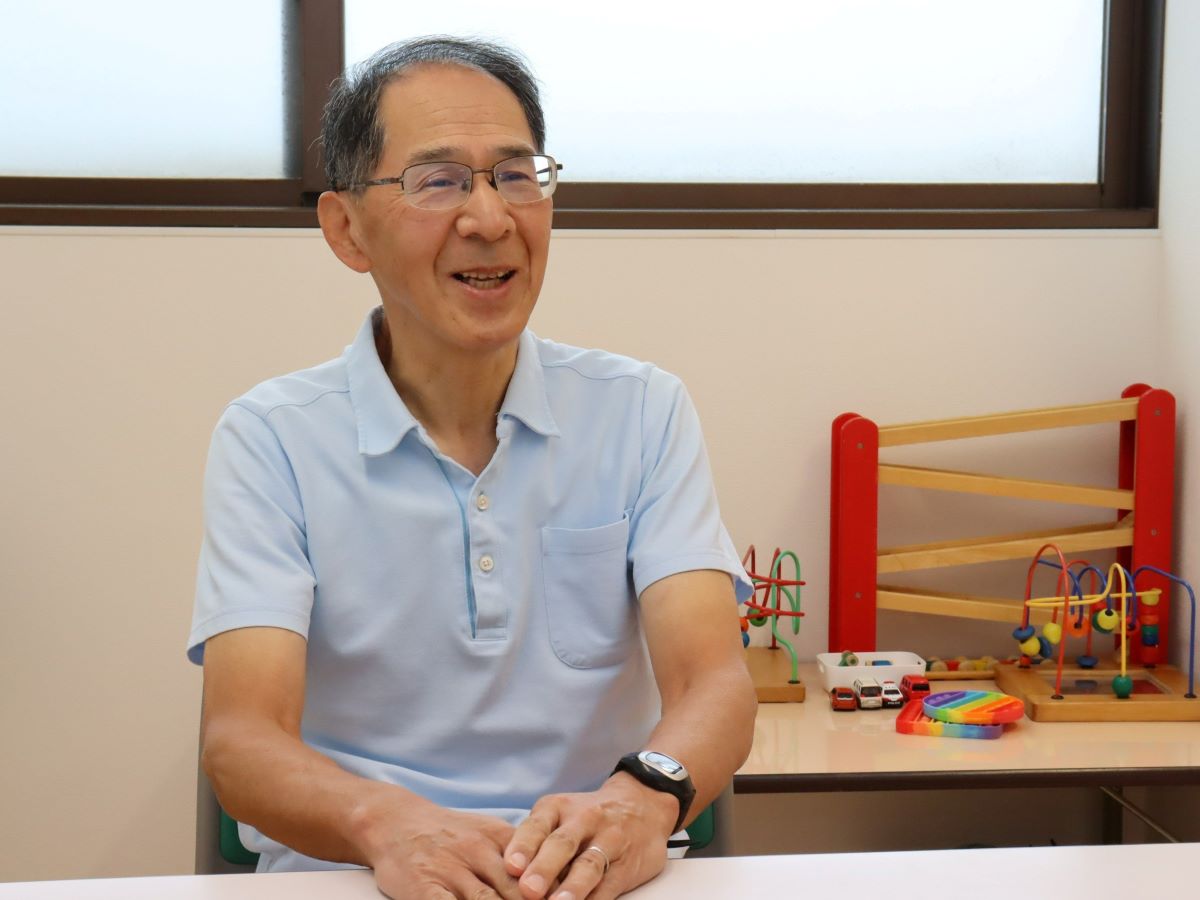
北川忠(きたがわ・ただし) 富山大教育学部卒。社会福祉法人めひの野園で長年、自閉症や成人の発達障害者の支援にたずさわり、2016年から県発達障害者支援センター「ほっぷ」に赴任。24年から社会福祉法人新川会、地域生活相談室に勤務。現在も発達障害に関する研修会講師や相談業務を行う。富山短大幼児教育学科非常勤講師。67歳。









