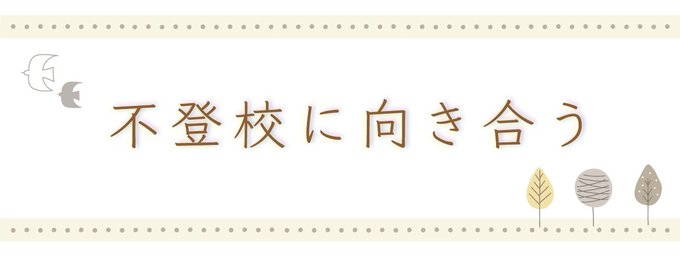県発達障害者支援センター「ほっぷ」センター長
県リハビリテーション病院・こども支援センター小児科部長(児童精神)
森 昭憲氏

不登校は「怠け」ではない
ー診療で、不登校の子どもたちと接しておられます。彼らの学びへの意欲についてどう感じていますか?
コロナ禍で、オンライン授業が注目を集めました。そこで小児科に来院した小中学生と高校生に「オンライン授業が始まったら受けたいですか?」と聞いたところ、「画面に顔を出さないなら」という条件付きを含めて、不登校になっている76人のうち62人(81.6%)が「授業を受けたい」と答えました。
これは不登校の理由が、「怠けている」「勉強したくない」ではないこと、むしろ勉強したいと思っている子が圧倒的に多いことを表しています。また「画面に顔を出さない」という条件を付けた子どもさんは、学校で感じた嫌な気持ちやつらい体験があるため、同級生や教員に顔を見せたくないことが理由になっていました。
不登校の子どもたちと話していると、「学校に行くと苦しい」という子どもたちの真実が見えてきます。学校には行かなくてはいけないことは分かっているから、「学校に行っていない」、そのことだけで大きなストレスとダメージとなって本人たちが苦しんでいるのです。理由が分からないけれど、学校に行けない、行くとつらいという場合が多く、理由が分からないからこそ、子どもたちの苦しさはとても強いと感じています。
親からの「学校行け」でさらに苦しく
ー学校でのつらい経験だけでなく、「学校にいかなければいけない」という思いから、自分で自分を追い詰めてしまっているということでしょうか
自分はダメな奴、自分は少数派(学校に行っている人が多数派)になってしまったと自分を追い詰め、苦しむこともあります。そんな心のうちなのに、一番頼りにしたいと思っている親から「学校に行け」と言われ、つらい思いさらに強くなっている子ども達も多くいます。
私は、不登校は子どもではなく大人たち自身が向き合うべき問題と考えます。そもそも「義務教育」(9年の普通教育を受けさせる国民の義務で、行政は無償で提供することが教育基本法第4条に記載されています)は、日本国憲法第26条にある、教育を受ける権利が元になっているのですが、子どもを学校に行かせる義務と思いこんでいる大人が多いのです。
「学校」の見直し必要
ー不登校の子どもを減らすために、何が必要と考えますか。
子どもの人口が減少し続けているのに、不登校の子どもは増え続けていることは全国調査で明らかになっています。
・誰のための学校なのか?
・全ての子どもが元気で楽しく教育を受けられるために何をしたら良いのか?
この単純な2つのことについて大人は考え、子どもたちの学びを見直さなくてはいけない時期なんだと子ども達は教えてくれています。
多くの子ども達の話を聴くと、現在の「学校」という場は、残念ながら全ての子ども達が健やかに学べる環境になっていないのが事実です。もしも全ての子どもが学べる場を学校に求めるなら、「学校」を見直す時期でしょう。現在の「学校」のあり方が変わらないなら、学校以外の学びの場を設けて子どもが色々な形で学べるようにするのが、大人たちの役割になります。
特集「広がる進路の選択肢」関連記事