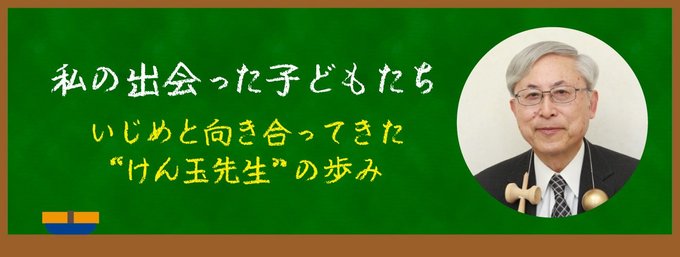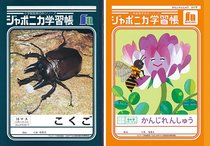本校は市の郊外にあり、かつてはのどかな田園地帯であった。しかし、近年、アパートが建ち並び、急速に集合住宅地帯となってきた。子どもたちの転入・転出が急増し、保護者同士の人間関係も希薄で、経済的な格差や二極化が目立つ。多くの保護者は日々の暮らしに追われ、子どもと触れ合うことができず、我が子の生活も心も把握できていない。そのような環境の急激な変化は、子どもたちの成長発達に少なからぬ影響を及ぼしていると言っても過言ではない。
学校には「生徒指導主事」という役職があり、校内の生徒指導全般をリードする役割を担う。小学校では学級担任が兼務するのが通例となっている。私は本校に赴任して3年目から学級担任と生徒指導主事を兼務するようになり、今年で7年目を迎える。
昨年度は自分の学級でのいじめ問題と格闘する日々であり、生徒指導主事として他学級・他学年への目配りが十分ではなかった。幸いにも、4月以来、自分の学級は落ち着いており、今年度こそ…。私は決意を新たに始動した。
本校に赴任以来、ずっと気になっていることがあった。子どもたちの「心の荒れ」だ。日々の言動を通して、多くの子どもが不満やストレスを貯め込んでいることが分かった。
私はこれまで、子どもたちに自己表現の場や機会を保障し、一人一人の心を開きたいとの願いのもと、「書くこと」を大切にしてきた。
クラスの仲間の作品を読み合う中で、子ども同士の心の交流が図られる。つながりが生まれる。一人一人の心に潤いとぬくもりがもたらされ、クラス全体に「やさしさの輪」が広がっていく。
私はこの取り組みを全校に広めたいと思った。
年度当初の職員会議で「いじめを生まない学校づくり」の一環として『全校、詩を書く運動』を提案した。
全校の子どもたちに詩を書かせたい。書くことによって、心のつぶやきや叫びを吐露させたい。一人一人が自由に自己表現できる場を設けることによって心を開放させたい。その営みが「いじめ防止」にもつながるのではないだろうか。
提案が受け入れられ、さっそく、校舎各階の廊下に「詩のコーナー」が設置され、掲示板と投稿用ボックスが据え付けられた。いよいよ、『全校、詩を書く運動』がスタートしようとしていた。
そのような時期、学校全体を揺るがす問題が発覚した。外国籍のパクくんが「学校へ行きたくない」と言い出し、母親が担任教師に「上級生にいじめられたと言っている」と訴えて来たのである。
パクくんは半年前、父親の海外留学に伴って家族そろって来日し、4月に本校の新1年生として入学したばかりだった。

私は本人と保護者から事情を聞いた。
日本語をほとんど話せないパクくんは、入学して間もなく、他学級の子どもたちから冷やかされたり、からかわれたりした。休憩時や下校時には他学年の子どもたちから殴ったり、蹴ったりされたという事実が分かった。
これは明らかに集団によるいじめである。しかも、学級や学年だけで解決できる問題ではない。学校ぐるみで問題解決に取り組むことを本人と保護者に約束した。
〔付記〕事例はプライバシーへの配慮から登場人物を匿名とし、事実関係についても若干の修正が施してあることをお断りしておきます。
◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。
現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。