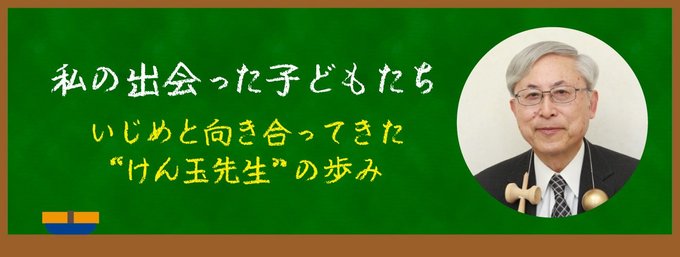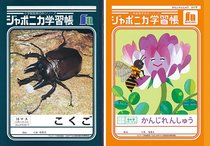親子との面談を通して、ツヨシの淋しさを知った。親子関係の希薄さと、ツヨシを取り巻く周囲の優しさの不足を痛感した。
私は、ツヨシを支え、彼の理解者になろうと思った。彼の淋しさと愛し愛されたいという気持ちを受け容れよう。彼の話に耳を傾けよう。我と我が心に誓った。
さらに、学級の子どもたちに相手を思いやる優しい心、温かくて豊かな人間性を培いたいと思った。
ツヨシ宅への訪問を終えた翌日、私は、子どもたちに「優しさいっぱいのクラス」にしたいと話した。
友達や家族に対して、「優しい言葉」をかけよう。「優しい行い」をしよう。その「優しさ」を日記に書いて知らせてほしいと呼びかけた。
子どもたちは私の話を真剣に聴いていた。
その直後から子どもたちは「優しさ」を発揮した。
授業中、誰かが消しゴムをうっかり落としたとき、周りの子どもがさっと拾ってくれる。拾ってもらった子どもが「ありがとう」と笑顔でお礼を言う。
授業後、私が黒板を消し始めると、何人もの子どもが手伝ってくれる。
私は「ありがとう。おかげであっという間にきれいになった」と子どもたちに感謝の気持ちを伝える。
帰りの会が始まろうとしているときのことだった。
ツヨシが教室の後ろのロッカーから次々とランドセルを取り出した。
そして、「はい、どうぞ!」と配って回った。
手渡されたクラスメイトは驚きながらも笑顔で「ありがとう」とツヨシにお礼を言った。
帰りの会が終ると、ツヨシは戸口に立った。
教室を出て行く一人一人に「さようなら」と声をかけた。

その翌日からツヨシは誰よりも早く登校し、教室の前で『朝のあいさつ』を始めた。
登下校時には、男女の区別なく、気持ちの良いあいさつが飛び交った。
係や当番の活動の中でも、さりげなく助け合い、支え合う姿が目立つようになった。
「優しさ」を言葉だけでなく態度や行動を通して実践していくその姿は、従来から児童会を中心に続けられてきた『あいさつ運動』の域を超えていた。
そこで、あえて4年2組では『優しさ運動』と呼ぶことにした。
ツヨシは、まさに『優しさ運動』の“鏡”だった。
私は、毎日、全員の日記に目を通した。
一人一人の「優しさ」を認め励ます言葉を赤ペンで書き添えた。
子どもたちはクラスの仲間の「優しさ」についても目を向け、日記に書き綴った。
やがて、多くの子どもたちがツヨシの変化に気づき始めた。
「前のツヨシくんとは、ぜんぜんちがうなあ」
「今までのツヨシくんとだいぶんちがってきたと思いました」
「ツヨシくんが生き返ったなあと思った」
そのような記述を毎日のように目にするようになった。
友達の「優しさ」に気づくことも素敵な「優しさ」であり、目一杯のほめ言葉を書き添えた。
6月22日、ツヨシは日記に次のような一文を書いてきた。
いしゃのかえり、バスをまっていると雨がふってきました。
しらないおばちゃんがきて、「ぼく、かさにはいられ」といわれました。
「ありがとう」といって、いれてもらいました。
バスがきました。
かさからでるとき、もういちど、「ありがとう」といいました。
ツヨシの日記を読みながら胸が熱くなった。
「おばちゃん」の「優しさ」に心を打たれた。
ツヨシの「優しさ」にも心を打たれた。
さっそく、ツヨシの日記を子どもたちの前で読んだ。真剣に聴いていた。
ツヨシは少し恥ずかしそうだった。
その日の夜、母親に電話をかけた。
学校でのツヨシの近況を報告するとともに、日記を電話口で読み上げた。
母親は、「ツヨシがそんなことを書いていましたか…」と控えめながらも嬉しそうだった。
次の日の朝、ツヨシが連絡帳を持って私のところにやって来た。
「ぼくのおばあちゃんが書きました」と言って見せてくれた。
そこには、丁寧な文字で次のように書かれていた。
いつの間にか大きくなって、先生様の教えに育てられて、うれしゅうございます。
今後共よろしくお願いいたします。
◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。
現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。