発達障害を理解する上で、三つ知っておいてほしいことがあります。社会性(対人関係)の特性、コミュニケーションの特性、こだわりの強さです。具体的にどのような行動が見られ、どう支援していけばよいのか、私が出会ってきた当時者さんとのエピソードからご紹介します。
数分早い電話に叱責「かけ直して」
ある日、初めて面談することになったAさんから相談日時を一方的に指定する電話がありました。私は他に予定もありましたが、なんとか日程を調整しました。ところが当日、Aさんは「おれ、約束は午後やったけど、家にいても暇やから午前中に来たわ」と言って、悪びれる事もなく相談に来られました。

同じく初めてお話を聞くことになったBさんからも、時間指定で電話相談の依頼があったため、気を遣って2~3分早めに電話をしました。すると電話に出たBさんから「心の準備ができていません。約束の時間に掛け直してください」と厳しくお叱りを受けました。
初対面でありながらこのように振る舞われるお二人から、社会で常識とされていることや暗黙のルールに無頓着という社会性(対人関係)の特性が見えてきます。
場の空気読めず 自己中に見られる
発達障がいの当事者は、その場の空気や相手の気持ちを読み取ることが苦手なため、周囲に配慮した行動ができず、まったく悪気が無いにも関わらず「非常識」「自己中心的」と見られことがあります。挙げ句の果てに、他人から怒りを買って職場で孤立してしまうこともあります。前述したお二人も例外ではなく、自分のルールで仕事を進めることで周囲を困らせていたことが後日判明しました。
「ルール守れば、あなたにいいことがある」
他者の気持ちをくみ取ることが苦手な人たちには、その都度その場にふさわしい言動を丁寧に伝えてあげる必要があります。ぜひ「叱って教える」のではなく「望ましい行動(言動)を伝える機会」にしていただきたいと思います。
また、私の経験では、「ルールを守らないと他者が困る」と伝えるよりも、「ルールを守ればあなたにいいことがあるんですよ」といった「本人主体」で伝えたほうが有効であったように思います。
とは言いながらも、そもそも社会性というものは発達の特性の有無にかかわらず、「あたりまえの子育ての中で少しずつ育まれていくもの」ではないでしょうか。時には親子の会話の中で、時にはゲームなどの活動を通してなど、学びの機会はたくさんあります。やはり「継続は力なり」なのではないでしょうか。
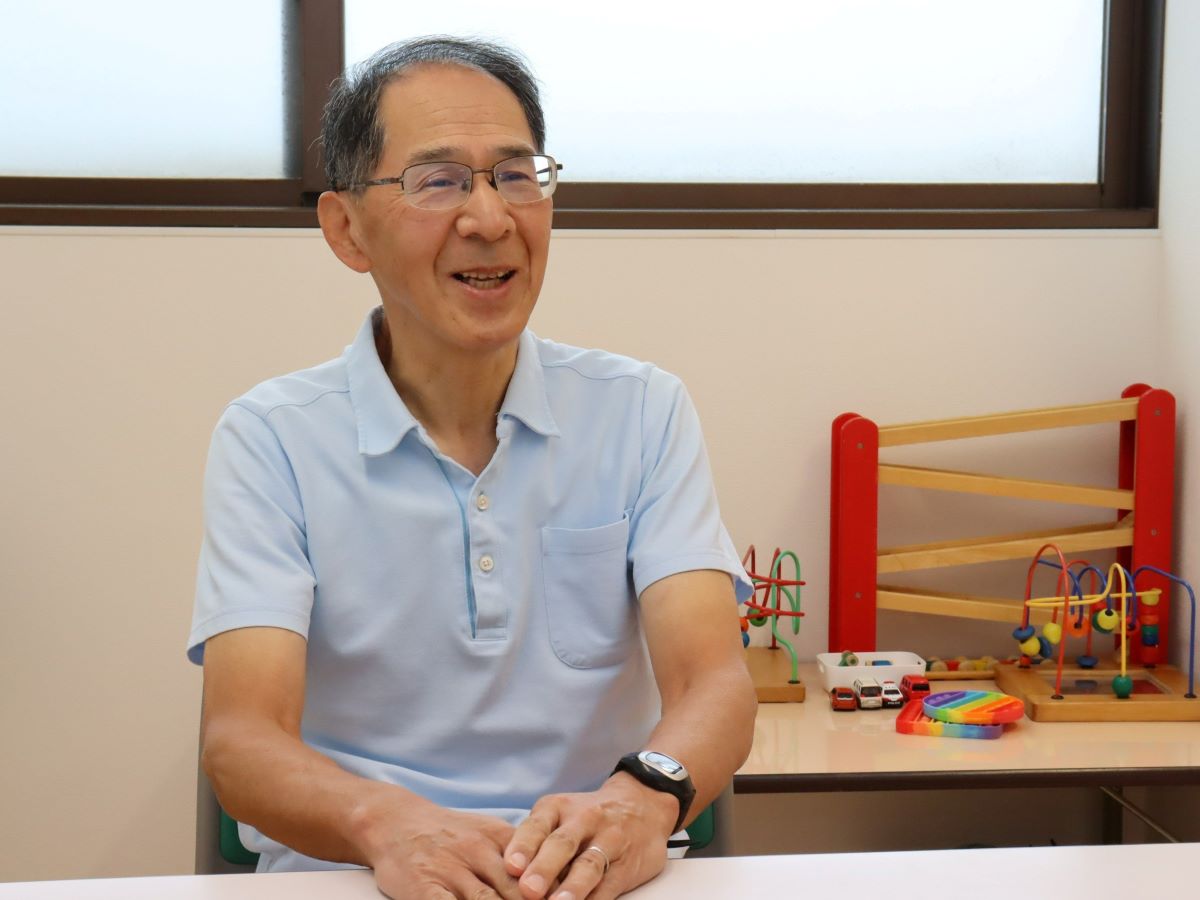
北川忠(きたがわ・ただし) 富山大教育学部卒。社会福祉法人めひの野園で長年、自閉症や成人の発達障害者の支援にたずさわり、2016年から県発達障害者支援センター「ほっぷ」に赴任。24年から社会福祉法人新川会、地域生活相談室に勤務。現在も発達障害に関する研修会講師や相談業務を行う。富山短大幼児教育学科非常勤講師。67歳。










