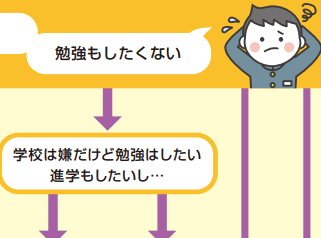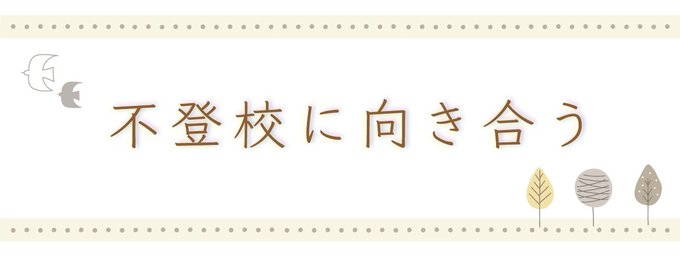「いつも機嫌がいいじゃないか。それでこちらも気分がいいのさ」
講演で私がいつも紹介するのは深谷かほるさんの夜廻り猫(第4巻)に出ている、猫の宙さんと飼い主である先生のやりとりです。
先生が宙さんの餌を準備しているとき…
宙さん「ごめんね。猫は役に立てないね」
先生「いや、一番役に立ってるさ」
宙さん「なんで?なにもしてないよ?」
先生「キミはいつも機嫌がいいじゃないか。それでこちらも気分がいいのさ。一日に何十回も自分はこのままでいいって、いってもらっているようなものなんだ」と笑顔で答えます。

一緒に暮らしながら、機嫌良くしていること、それは相手の存在を肯定している、そういうメッセージを送っていることになります。その大切さは、その逆を考えればよくわかるでしょう。いつも父親が(母親が)不機嫌にしている。そういう空間で過ごさざるを得ない子どもにとって、それはとても居心地の悪い、つらい暮らしとなるでしょう。
「あなたはそのままでいい」とか「あなたが生きていてくれて私はうれしい」という言葉よりも、ずっと確かなものは、子どものいる空間で機嫌良くしていること、その時間の幸せを感じて生きること、だと思います。
機嫌のいいふりではダメ
これに対しても、よくもらうコメントがあります。それは「忙しくて大変なのに、なんで機嫌のいいふりまでしないといけないのか」とか「現実にはしんどいことが山ほどある。機嫌のいいふりなんてする余裕がない」というようなものです。
機嫌のいいふり、ではダメなのです。親子なので、親が「ふり」をしていることはすぐに子どもに伝わります。自分が子どもだったときのことを思い出してください。幼いときでも(幼いときほど、かもしれません)親が本当に機嫌がいいか、ふりをしている(無理をしている)のかは、わかるものです。
親が自分の生活を楽しむ その姿を子どもに
子どもには親の生き方、生活、気分の面倒はみれません。親は大人として、自分の生活をできるかぎり楽しめるように(そして、それは子どものためにもなる)、できることをやる、がんばるべきです。

子どもと暮らせる時間、子どもが子どもでいるわずかの時間を大切に過ごせるように、自分の心の状態をいいものに保つ努力をすること。その努力をしている親の姿を子どもは間近で見ながら育っていきます。それはなかなかたいへんではあるけれど、やりがいのある贅沢な挑戦だと思います。
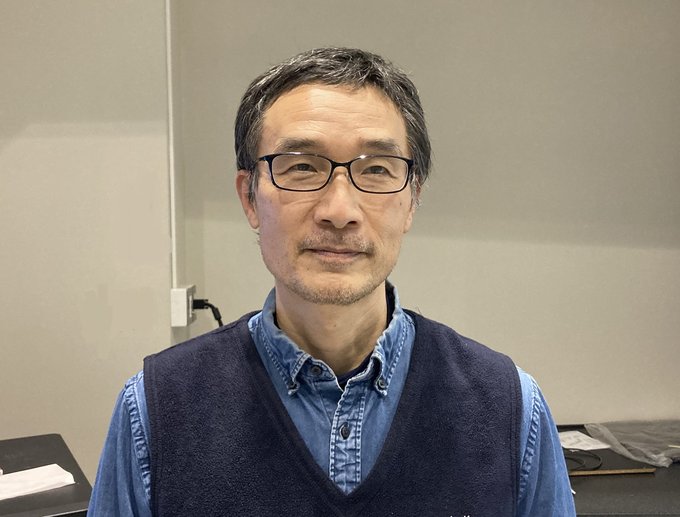
田中茂樹(たなか・しげき) 医師、臨床心理士
1965年東京都生まれ。京都大医学部卒。仁愛大人間学部心理学科教授などを経て、現在は佐保川診療所長。著書に「子どもを信じること」(さいはて社)。