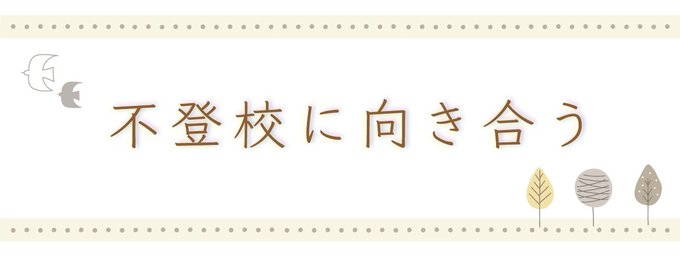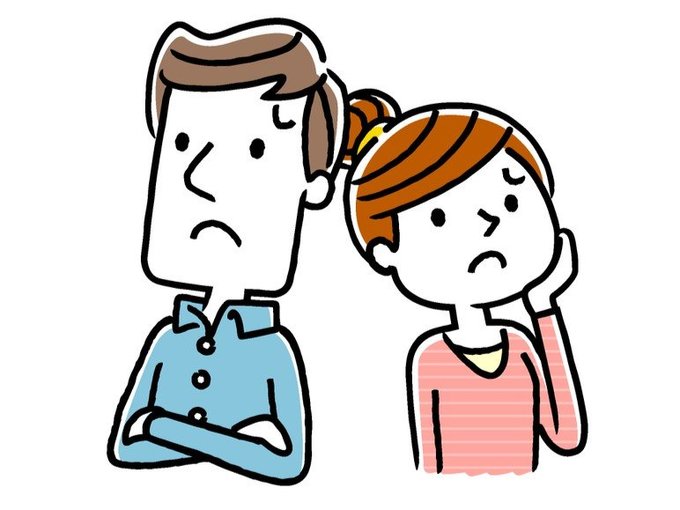
回答 「子どもに小言をいうのをやめましょう」「いろいろと子どもに与えてきた指示をしばらくやめてみましょう」と提案すると、実に多くの人がこのような質問をされます。
どちらかの親が小言を控えるだけでも、子どもはかなりリラックスできます。それよりも、この質問には別の意味があると長年の面接を通して私は感じています。
「相手を変えようとすること」への依存
今まで、子どもにいろいろと指示をしてきたのをやめると、今度は、パートナーの行動に不満が出てくる。こういう気持ちになる背景には、小言を言うこと、つまり「相手の行動を自分の思う通りに変えようとすること」への依存症のようなものがあると思います。あら探しの視点はずっとやり続けてきたので発達しているけれど、相手のことをとりあえず受け入れる力や、適当に受け流す力は育っていない、とも言えます。
そこで、パートナーに「小言を言わないで」と言いたくなったら、「自分はまた相手を変えようとしているんだ」と意識するようにしてみましょう。
これには他の理由もあります。相手を変えることは簡単にはできませんが、自分を変えるのは自分がそう思いさえすれば、たった今からでも可能です。
相手ではなく自分を変える
しかし、これは一部の人にはとても難しいことのようです。「子どもが間違っているから、親として正しいことを教えようとしているのに、なんでそれを辛抱しなければならないのか?」、「自分が辛抱しても、夫が(妻が)それを台無しにしている。自分だけが努力しても無駄じゃないか」。このような不満が必ずのようにでてきます。相手を変える方法を相談しに来ているのであって、自分を変えたいのではない、というわけです。

私は、今までそういうやりかたでやってきて、うまくいかないから専門家に相談にこきたのだから、勇気を出してやってみませんか、と提案します。
子どもやパートナーのしていることの、どこが間違っているか、それをどうやったら正しく直せるのか。そういうことに囚われてしまっている自分の心を意識するのです。1年もやる必要はありません。一ヶ月ぐらい、いや一週間でも本気でやってみる。それで十分効果は得られます。小言を言わずにいられる力はそれで十分育ちます。それだけではありません。子どもの、もしくはパートナーの意外なところ、やさしさやかしこさ、たくましさ(生きる力)などを、あらためて発見するはずです。それは、これまでのあら探しの視点では見えなかったものです。
多くの人は、自分が親から言われた小言を、そして親のあら探しの視点を、知らぬ間に受けついでしまっています。そして、今度は子どもにそれをそのまま渡そうとしています。その悪循環から離脱することは、自分自身の力で親の悪影響を乗り越えるという達成、解放感もたらします。
次ページ…どうしても一方の親が小言をやめられないときはー