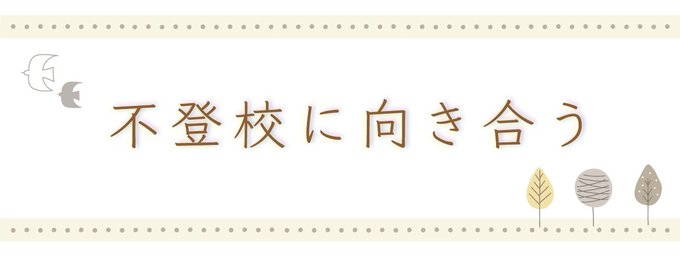かつては「登校拒否」

私は県内の小・中学校を訪れていますが、規模の大小を問わず、どこの学校にも不登校の子どもがいて、また増えていることを実感しています。
かつて不登校は「登校拒否」と呼ばれていました。これは、いかにも子どもが悪いというイメージです。その中で先生たちは「どうやったら学校に行くか」を考え、学校に登校させることを目的に支援をしてきました。しかし子どもたちを無理に学校に連れていっても、苦痛となるだけで逆効果となることが多かったのです。
不登校は、休養し自分を見つめ直すプラスの時期
国はこのような支援方針を是正するため、2019年10月に「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知を各教育委員会に出しました。
そこでは、子どもたちへの支援は「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、「社会的に自立すること」を目指すとしています。また学校に行かない時期は、休養や自分を見つめ直すプラスの時期ともいえると捉えています。行政もようやく子どもが中心の考え方になってきたといえます。
「学校になじめない」も要因の一つ
私たちスクールカウンセラーは定期的に学校を訪ね、子どもたちの話を聞いています。不登校の背景はさまざまです。心の問題、精神疾患を抱えている子、家庭が落ち着かず、学校に行く気分になれないという子、また学校内でいじめがあり、安心できないという子もいます。
それ以外に「学校になじめない」「勉強は嫌いではないけれど、みんなで一緒のことをすることができない」という子どもたちも一定数います。
そのようなケースでは、中学3年生の秋ぐらいから、学校の相談室や保健室などに登校するようになり、高校に入学していく生徒もたくさん見てきました。私はそういう子どもたちは、心の発達のリズムというか体内時計がゆっくりなんだと感じています。
好きなことがきっかけに
また、一つのことをきっかけに、再び学校とのつながりを持ち始める子もいます。それは、本人が好きなことです。例えば校外学習や修学旅行などのイベント、部活だけ行くようになるというケースです。高校進学も変化のきっかけとなりますが、自分の好きなこと、興味のあることが、ターニングポイント(転機)になることがあります。
ですから学校に行っていない間でも、親は常に学校とパイプを持ち、いろんな情報を得ながら、本人が興味を持った時には行くことを勧めてみることも大切です。
専門家を加えたチームで対応
子どもが不登校になったとき、親は「自分に責任があるのではないか」「育て方がよくなかった」と自分一人の問題として考えがちだと思います。
でも先ほども言いましたが、不登校の背景も子どもたちの心の発達のスピードも、一人ずつ違います。不登校の対応に単一の答えはなく、その子にあった方法を探さなければいけません。そんな大変なことを、親が一人でやろうと思わないでください。
今、不登校の問題は、教員だけでなく私たちのようなスクールカンセラー、スクールソーシャルワーカーら専門家を加えたチームで対応するよう、教育現場は変わりつつあります。また学校以外の教育機関の相談窓口として県総合教育センターや、不登校の家族の会もあります。さまざまな人とつながり、情報を得て、より多くの支援を得てほしいと思います。
法務省心理技官として25年間、少年鑑別所・刑務所・拘置所などで、非行少年や受刑者のカウンセリングに従事。その後米国に留学し、二つの大学院で15年間にわたり、心理検査・カウンセリングの研修を積み、デンバー大学でカウンセリング心理学の博士号取得。2010年、富山市で 「うつ心理相談センター」開設。富山の専門家紹介サイト「マイベストプロ」登録プロ。