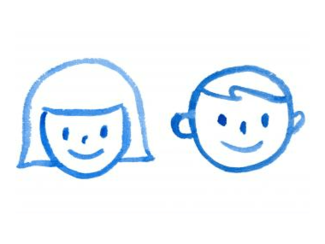苦労した理由を考える
質問にある「宿題」が、ゲームや本人の好きな事だとしたら、どうでしょう?
苦労したのは、その宿題が「面白くない」「面倒」「分からない」などの理由が考えられます。もしかしたら、大人自身が、勉強は面白くないと思っているのではないでしょうか。質問の子どもさんの場合、タブレットは進めているので、理由がつかめそうな気がします。
また、直接教えてもらわないと、学習が進められない子どもさんもいらっしゃると思います。その場合には、一緒に取り組むのがよいと思います。
「子どもが宿題をしない」と悩んでいる方へ
「宿題をしない」と悩んでいる親御さんは、たくさんおられると思います。次のように考えて、お子さんを見守ってください。
①分からなくて当たり前と思って接する
特に休校中に出された課題は教わっていない新しい分野の勉強が多いと思うので、分からなくて当たり前。先生も分からなくて当たり前と思っているでしょう。
親がまず「分からなくて当たり前」「新しい事が出来たらスゴイ」と思って接しましょう。なので、分かる所までは行い、分からない所は学校で先生に聞くことにします。
そもそも今回の休校中の課題は、まだ学校で学んでいないところの予習もあり、夏休みの宿題とは全く違います。
先生たちも、本当なら教室で教えながら楽しく進めたかった学習が急にできなくなり、困っていろいろと悩みながら考えて作った課題です。先生が直接教えながらでないとできない事が、課題になっているものもあるかもしれません。
②細切れにする
休校中、学校からどっさり課題が送られてきた家庭も少なくなかったと思います。
イヤと思っている物がたくさんあったら、誰でもイヤになります。
プリントなどは、子どもが1回でできる現実的な量に分け、1回分ずつ取り出してできるよう準備します。「やりたくない」という気持ちにならないよう工夫が必要です。
③子どもの特徴に合わせる
集中する時間が短い子には、1回の集中時間にあった量を行うようにします。
読み書きが苦手な子にとっては、文字をたくさん書くのは苦痛だったりします。もしそうなら、例えば、書く量を少なくすることも必要になるでしょう。
④子どもが怒ったり親がイライラするくらいなら、答えを写して提出もあり
「課題をさせなくては」と親がイライラしたり、それで子どもが怒ったりするくらいなら、学校の先生からは怒られるかもしれませんが、答えを写して提出でも良いと思います。
その時の注意点は、回答を嫌々写すのではなく、解き方や答えを覚えるつもりで写すようにしましょう。
YouTubeで「学年と教科」で検索すると、子どもさんにとって分かりやすい動画が出てくるかもしれません。小島よしおさんの動画は分かりやすいと子どもさんに好評ですよ。
「できた」「分かった」「楽しく」が大切
達成感を得ることは、うれしいことです。例えば、ゲームがうまくいった時の達成感やうれしさは、ゲームをする子どもさんを見ている親御さんも御存知の通りでしょう。「分かった」という達成感もあります。知りたい欲求は人間誰にでもあり、知ることは嬉しいことです。テレビ番組、YouTube、ネットで見聞きした事を、子どもさんが楽しそうに話すこともあるでしょう。
しかし「させられている」と本人が感じると、途端に面白く感じられなくなってしまうのは、子どもも大人も同じではないでしょうか。だからこそ学習においても「楽しく」が大切になります。
また学習でいろいろと知ると、こういう良い事がある、役に立つ、人生が楽しくなる、心配や不安が減るなど、知ることの良い点を、具体的に伝えることも大人の役目です。
こんな時は、親も心が苦しくならないことを第一に
子どもも親も先生も、コロナのために生活が急激に変化し、不安になり、今後の見通しもつかず、たくさんのストレスを抱えています。こんな時は、楽しく生活することを心がけることが大事です。
親の皆さんも心が苦しくならないことを第一にして、過ごされるよう願っています。
森 昭憲(もり・あきのり)

県発達障害者支援センター「ほっぷ」センター長
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 小児科部長(児童精神)・精神科部長 心理療法科長
1970年生まれ。富山医科薬科大学(現富山大学)医学部医学科卒業。
内科、和漢診療を経て、精神科病院に勤務。あいち小児保健医療総合センター心療科、豊田市こども発達センター、愛知県立城山病院(児童精神・精神科)にて児童精神医学・発達障がい診療の研修。
2017年より富山県リハビリテーション病院・こども支援センターに勤務し、子どもの心の外来・精神科の診療を担当する。資格は精神科専門医・指導医、精神保健指定医