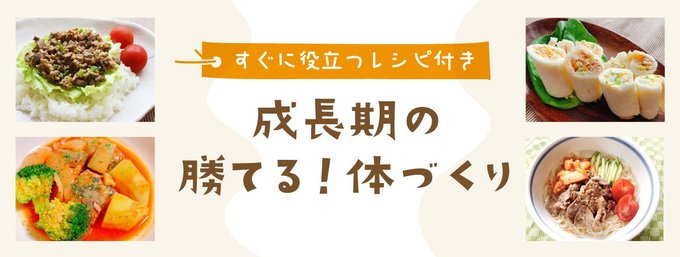「食べ物はよくかんで食べなさい」。幼い時からよくお母さん、おばあちゃん、学校の先生に言われてきた言葉です。
「分かってはいても実行できない」「今はいいとやめてしまった」など習慣化がなかなか難しいですね。また、近年はやパンやゼリーなど、やわらかい食べ物が好まれるため、食べ物によっても、だんだんかむことが少なくなってきています。今回は「かむことの意義」を考えてみたいと思います。
「よくかむ」ことによって
-
食べ物の消化・吸収を促進
消化酵素のアミラーゼを含む唾液の分泌を促し、胃腸での食べ物の消化吸収を促進する。 -
むし歯・歯周病予防
唾液の分泌がよくなり、唾液に含まれる免疫物質が細菌を減少させるため、口腔内の清潔が保たれ、むし歯や歯周病の予防につながる。 -
脳を刺激、活性化する
おいしい・固い・熱い・冷たいと感じたり、かむという作業により、頭部の骨や筋肉が動き、血液の循環がよくなることで脳神経が刺激され、脳の働きが活発になる。 -
肥満の防止
食事に時間をかけることにより、満腹感が得られ、食べ過ぎ防止の効果もある。 -
強いあごをつくる
固い物をよくかんで食べると、上下のあごの骨や顔の筋肉が発達し、丈夫なあごをつくる。あごが充分に発達していないと歯並びが悪くなり、運動能力が低下するなど、健康を害する問題が生じる。
また、よくかむことによって、会話のある食卓を囲むこともできるでしょう。ちょっとしたことですが、小さなことをコツコツと行うことで、このようなことが期待できます。
食事の工夫でかむ習慣を
疲れているとき、急いでいるときほど良くかまずに、流し込んだり、丸のみしたりしがちになりますが、かむことには意味があります。
こどもは特に心身の発達には良くかむことは欠かせません。
よくかまなくては食べられない食材としては、小魚、いか、たこ、ごぼうやきゅうりなどの生野菜、お肉、かたいせんべい等がありますね。 よくかむ工夫としては、野菜を大き目に切ったり、やわらかい食材にきのこや切干大根などよくかむ食材を混ぜたりすることもできます。

私たちの身体は食べ物から出来ています。いつでも、いつまでもおいしく、楽しく食べることが出来ますように。ちょっとしたことを忘れないでくださいね。

次回はカムカムレシピです。
◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士
富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。
日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。