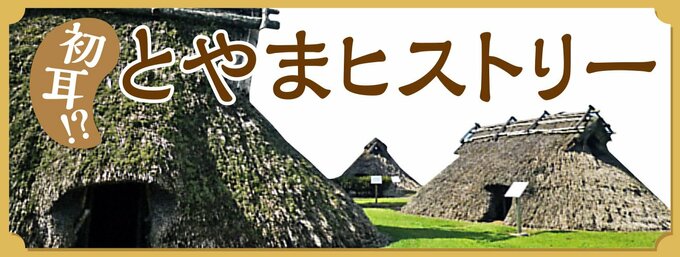平安時代に紫式部が書いた「源氏物語」の第一帖「桐壺」の中で、高麗人(こまうど)が幼少の光源氏の顔を見て不思議な予言をする場面がある。
帝位につくべき人相だが、即位すれば国が乱れる。しかし、臣下に終わる人相ではない―。
この高麗人の占者が渤海(ぼっかい)人だ。さらに光源氏の呼び名を、最大の賛辞である「光る君」としたのも渤海人だと記される。
作品の中でなぜ渤海人が重い役割を担ったのだろう。平安文学が専門の河添房江東京学芸大名誉教授は、紫式部の着想に越前(福井)の国司を務めた父に同行した思い出があったとみる。「かつて渤海国使を受け入れた土地柄ゆえに、その交流の歴史にも思いをはせたのではないでしょうか」
加えて渤海国の謎めいたイメージも、占者の役どころに合っていたのかもしれない。

渤海使船のイメージ模型=石川県志賀町、シーサイドヴィラ渤海
遣唐使超え47回行き来
渤海は、中国の東北部、北朝鮮、ロシア極東部のエリアにあった国。唐から「海東の盛国」と称されるほど繁栄したが926年、遊牧民の王朝「契丹(きったん)」に滅ぼされ消え去ってしまった。
残り1243文字(全文:1714文字)