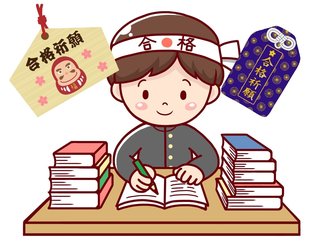2025年は日本の女性にとっては一つの節目だろう。女性参政権が認められてから80年。男女雇用機会均等法が制定されてから40年。そして、女性首相が誕生した。服飾史家の中野香織さんはかつて内定先で「女性は男性より10%給与が低い」と告知され、辞退した。以来、常に新しい道を切り開いてきた。中野さんが語る、装いと働き方の変遷、そして現在も続く社会の課題とは——。(聞き手・田尻秀幸)
高市首相のチーフ

——今日はパンツスーツ姿ですね。
最近はそうですね。来年はスーツ生誕360周年なんですよ。1666年は、英国王チャールズ2世が衣服改革宣言を発した年で、「倹約」のためのベストが導入され、これが上着、ベスト、シャツ、タイ、下衣から成るスーツのシステムの基礎になりました。
——スーツというと、日本で初めて女性首相となった高市早苗氏は青色のスーツが印象的ですね。
高市さんだから首相に選ばれたのだと思います。女性初を強調しすぎることはないでしょう。高市さんはブルー系のスーツやジャケットで登場されることが多いですね。日本的な文脈においても、日本の伝統色である藍は「ジャパンブルー」と呼ばれていますし、文化的な側面から、風の谷のナウシカの「その者青き衣をまといて金色の野に降り立つべし」という言葉も連想できます。公人としてのブルーの使い方が一貫しているのは戦略的です。外交の場面で脚光を浴びるべきシーンでは白系を駆使し、式典ではダークカラーでも光る素材を取り入れるなど、ファッションの演出は巧みで的確だと思います。
——サッチャー元首相を意識しているともいわれますね。
サッチャー元首相との唯一の違いは、ブローチの使用です。サッチャーさんは必ずブローチをお付けになっていました。西洋においてブローチは女性性と女性の権威の象徴的な意味合いがあるのですが、高市さんはそれを真似せず、紳士社会の秩序と知的洗練の象徴であるポケットチーフを取り入れていらっしゃいます。これは、サッチャー的な強さを単純に継承するのではなく、お互いへの敬意と信頼に基づいた権威、つまり同じ権力でもその質が違うということを示しているように見えます。
時代の変化——パワースーツからジェンダーレスへ
——女性の装いと働き方の変遷についてはどう思われますか。
女性の社会進出に合わせて、ビジネスファッションは楽な方に流れていきましたね。1980年代、90年代はみんなちょっと無理してハイヒールを履いて、肩パッドの入ったスーツを着て、前髪なんかを立てていました。そうやって頑張った上で、男性と互角に社会の中で仕事をしているのがかっこいいと思われていました。

——2000年代から変わった気がしますね。
そのあたりからリクルートスーツが画一化しましたね。男性も女性も同じような黒いスーツを着始めた。そのうち、ワークライフバランスが謳われ始めた。「MeToo運動」になぞらえた「KuToo運動」もありました。
2000年以前は、会社で配偶者を見つけるみたいな空気もあったけれど、今ではアウト。だから、そんなところにエネルギーを女性は使わずに、女性性を消すみたいなところがありますね。自分の世界を守りたいという空気が強い。
——女性初の総理誕生ということですが、2025年は女性にとって大切な節目ですね。中野さんご自身は1985年の就職活動を経験されていますね。ちょうど男女雇用機会均等法が成立した年でした。
大学4年になり就職活動を行いましたが、当時は今の学生のように長期間にわたる本格的な企業研究を行う学生は少なかったように思います。とりあえず、ある洋酒会社の宣伝部を志望しました。私が目指していたあり方というのは、開高健さんのような存在でした。企業の宣伝部で文化的な雑誌を作ったり評論を書いたりして、世の中を楽しませながら、それが直接PRにならなくても、結果的に企業の利益にも貢献するという働き方に憧れていました。「開高健になれるのはどこだろう」と考えて、その会社の宣伝部かなと思った程度でした。
幸い内定をいただいたのですが、その後に「女性は一律男性より10%給与が低い」「女性だけ制服着用」ということを告知されました。均等法が制定されたばかりで、現実レベルではまだ適用されていなかったのですね。どんなに努力しても、最初からスタートラインが違う。目の前にシャッターが下りたような感覚を覚え、内定を辞退しました。女性は制服を着て、お茶汲みから始まると言われて、努力する方向が根本的に違うんだと思ったんです。
その後、もうどこも就活は終わっていて、どうしようかなと思っていました。決断をちょっと2年延ばすというか、もう1回大学にいる理由を作るために、教養学部のイギリス科に学士入学しました。
「踏まれ尽くした所を踏むのは嫌」
——高校時代は理数科で医学部志望だったそうですね。女性に不利な時代であっても、当時でも医師は女性に開かれていた職業でしたが、それも意識していたんですか。
高校2年の時、新聞の作文コンクールで入賞しました。取材で将来の希望を聞かれた際、「人の役に立つ仕事がしたい、たとえばお医者さんのような存在になりたい」と答えました。当時の環境では、周りに会社員の方はいらっしゃらず、人の役に立つ仕事といえば、高校教師、県庁職員、医師という選択肢しか思い浮かびませんでした。漠然とものを書くのは好きだったから、どっちにしても書いて生きていくんだろうなとは思っていました。
ただ、私、動物の血を見るのが苦手だったんです。医学部に進めば人体の解剖実習も必要になりますが、それでは患者さんにご迷惑をおかけすることになるのではないかと色々疑問が湧いて、世の中を見てから将来を考えても遅くないかなと思いました。東大を選んだのも、学部の選択を後ろ倒しにできるという利点があったからです。
——現在につながるような執筆活動は大学時代の旅行雑誌から始まったそうですね。
結局、東大では英文学を選択しました。ただ、最も強かったのは世界を見たいという欲求でした。すぐに旅行レポーターのアルバイトに応募し、最初にメキシコに連れて行ってもらいました。そもそも募集要項には「スペイン語圏に行くので、スペイン語ができること」という条件があったのですが、もちろんできません(笑)。とりあえず応募してみたら、面接で「その度胸があるなら大丈夫。メキシコはすごい無法地帯だから」って。いろいろな場所に行きましたよ。

大学は楽しかった。当時の先生たちって今考えても大スターなんですよ。蓮實重彦さんの映画論とか、柴田元幸さんのアメリカ文学の話とか、伊藤亜人さんの文化人類学とか。一流の先生たちが目の前で最先端の話をしてくれるわけで、少人数でこういう教育が受けられる環境が素晴らしかった。レジャーランドみたいでした。
——中野さんといえば、ファッションの専門家ですが、大学時代から研究されていたのですか。
ミニスカートを世界的に流行させたイギリスのファッションデザイナーマリー・クワントを卒論で取り上げたのが最初です。これは一種の反抗でもありました。先生方をとてもリスペクトしてたんですが、一流の先生方がいらっしゃる分野で同じことをしても、その上に行くには何十年もかかる。
そこで先生方が絶対に手をつけなさそうな分野はなんだろうと考えたら、ファッションだった。当時ファッションは応用芸術として軽んじられていましたが、私はアール・デコの時代にその区別はもう覆っているのではないかと楽観していました。ただ前例がないし、資料も少ないから猛反対を受けました。

「英文学の中に描かれたファッションの話にしたらどうか」とも言われたんですけれど、それじゃあマリー・クワントがやった革命に迫ることができない。あの人の革命って、周りを挑発しながら、世の中全体、階級社会すら揺さぶったことにあるんです。社会学的な側面からアプローチすれば非常に面白いものになると直感していました。
——反対されてもやったんですね。
むしろ「よし」という感じでしたね。踏まれ尽くした道を歩くってつまらない気がしたのです。マリー・クワント本人にお手紙を書いたところ、資料を航空便でお送りいただき、論文を書くことができました。30年後、日本に巡回してきた「マリー・クワント展」展覧会の翻訳監修を務め担当させていただく機会があり、ご恩返しができたと思った直後に、マリー・クワントが亡くなりました。我ながらドラマチックですね。
「自分より下で活躍してね」
——結局、研究者の道を歩まれた。洋酒会社は入り口の時点で男性社会の壁を感じたということですが、アカデミアではどうでしたか。
多くの男性は一応、女性の活躍を応援してくれるんですよ。だけれど、「自分より下で活躍してね。あなたは頑張ってもいいけれど、僕の上には行っちゃいけないよ」ってなることが少なくない。たとえば私が大学で働くことを応援していてくれても、本を出したり、メディアに出たりとなると嫌な顔をする人がいる。そういうことがずっとあったんですね。だから男の人のプライドは決して傷つけてはいけない、と気を遣っていました。

講義をすると大学の400人ホールがほぼ満席になった
キャリアを続けるうえで、知らされるべきことを知らされなかったという場面もあり、最終的にはすべて自分の責任ではあるのですが、競争の原理が働いてしまう場としての大学からは離れました。自分のペースとルールで研究とその成果の発表ができるよう、自分で会社をつくって独立しました。
——固定観念に縛られた男性が女性に嫉妬するということはありますね。男性同士の争いに負けるのは許容できても、女性に負けることには耐えられない。
解放されなきゃいけないのは、もしかしたら男性の方かもしれない。女性の方が選択肢があるという見方もできる。出産を選んでもいいし、選ばなくてもいい。働き続けることだって社会に応援されているし、環境が許せば家庭に入ってもいい。これを選ぶっていう覚悟さえあれば、邁進できるんですよ。でも、男性は選択肢が少ない。世の中は変わってきたとはいえ、主夫という存在も世間的にはまだ肩身が狭いこともあるでしょう。住宅ローンだって男性名義が大前提になっている。男性にとっては、なかなか重荷ですよね。