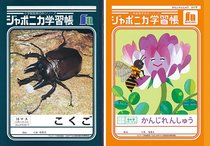能登半島地震の発生時を振り返り、「本当はどうしたらよかった?」と考えるコノコトレポーターの声に応えるシリーズ企画「パパママのための地震対策」。前回の津波編に続き、今回は避難時のポイントについて考えます。アドバイスをいただくのは、ケーブルテレビ富山で防災番組を担当し、4歳児のママでもある防災士の鈴木佑実さんです。
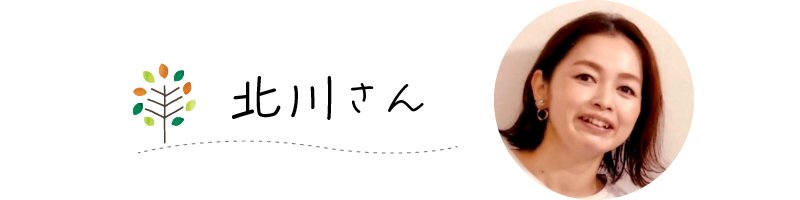
帰省先の珠洲市で初詣に行き、お宮さんの建物に入った瞬間に地震が起きました。いったん揺れが収まった隙に道路へ出て避難。余震が続いたため家の中は危険と判断し、その日は車中泊をしました。落ち着いてから近所の一人暮らしの高齢の方にも声を掛け、みんなで集まって過ごしました。
水も電気も使えず、備蓄していた餅を食べたり、発電機で携帯を充電しながらしのぎました。トイレが使えないのが一番大変でした。
激しい揺れに襲われた時、すぐに外に出た方がいいのか、テーブルなどの下に潜り、揺れが収まるのを待った方がいいのか正しい行動を知りたいです。
住まいのリスク把握を
鈴木さん(以下同じ):一概には言えない非常に難しい質問です。専門家は、一般的に揺れたら頑丈な机の下に潜るなどして「まずは身を守る」のを優先してほしいと呼び掛けています。慌てて外に飛び出すと、移動中に落下物の下敷きになったり、車にひかれたりするリスクもあります。まずは、倒れてくる家具などでケガをしないように安全の確保をしてください。
今回の地震では古い家屋の倒壊が目立ちました。確実に言えるのは、住まいのリスクを事前に知っておくことの大切さ。ご自宅の耐震性を把握し、それに基づいた対策、行動を日頃から考えておきましょう。

断水が続いた地域は、トイレなど本当にお困りだったと思います。短期的には非常用トイレやおむつを備蓄しておくといいでしょう。ケーブルテレビ富山では、バケツとポリ袋、新聞紙を使った超簡易トイレの作り方も紹介していますので、参考にしてください。

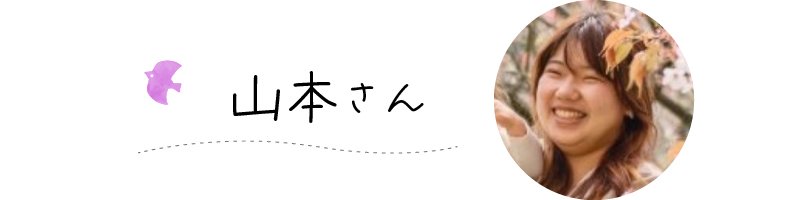
お通夜に参列するため、富山市八尾町の葬儀場に家族でいました。柱の近くで身を寄せ合いましたが、建物が壊れるかもと考えて外に出て、車を安全な場所に移動させました。今回は家族3人がそろっていましたが、もしバラバラで連絡が取れなかったら、どこに避難するかを話し合うとともに、ハザードマップを調べ、非常用持ち出し袋を作ったり、懐中電灯を枕元に置いて寝たりしました。
待ち合わせ場所を決めておく
避難場所の認識を家族ですり合わせておくことはとても大切です。我が家では通信インフラが寸断された場合に備えて「地震が起きたら小学校前」などと、災害の種類別に待ち合わせ場所を決めてあります。また毎朝、夫婦でその日の互いのスケジュールを共有し、何かあったときにどちらが保育園に迎えに行くかを決めています。
小学生以上のお子さんであれば、災害時に比較的繋がりやすいとされる公衆電話の使い方や設置場所を確認しておくのもおすすめです。家族の連絡先も持たせておきましょう。

乳幼児などがいる場合、避難所に行くのがためらわれるケースがあるかもしれません。自宅の安全性が確保されているなら「在宅避難」、移動が可能なら親戚や知人宅、宿泊施設などに身を置く「分散避難」も考えられます。繰り返しになりますが、いざというときに大切なのが助け合い。普段から「何かあったら頼むね」と言い合える関係を築いておきましょう。
次回は、備蓄について考えます。
コミチャン9ch 毎日7:30/17:30ほか
■HP:https://ctt.ne.jp/comichan/bousai/
■YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL6_ShUmOdTom-VeIVxnPPI64A1U6SXoZc
※番組では「赤ちゃんの防災」なども取り上げている。YouTubeでアーカイブ公開中。