

三者協業の精神で暮らしに貢献
三協立山は「環境技術でひらく、持続可能で豊かな暮らし」を実現する企業グループを目指し、建材を主軸に、マテリアル、商業施設、国際事業など多彩な事業を展開しています。サステナビリティ(持続可能性)や脱炭素に対する社会の関心や要請の高まりに、いかに向き合い、責任を果たしていくか。同社の平能正三社長と蒲地誠北日本新聞社長が語り合いました。
蒲地 長期目標「VISION(ビジョン)2030」で「多角化した経営」を掲げ、バランスの取れた事業ポートフォリオを目指されています。各事業の状況をどう見ていますか。
平能 当社は社内カンパニー制を取っており、ビジョン2030では2030年時点の売り上げ比率を、建材事業を担う三協アルミ社50%、マテリアル事業の三協マテリアル社と国際事業が合わせて30%、商業施設事業のタテヤマアドバンス社15%、その他の領域拡大5%と計画しています。前期は建材51%、マテリアルと国際合わせて38%、商業施設11%となりました。国際事業は三協マテリアル社と同じ、アルミの鋳造、押出、加工を行っており合算しています。
アルミ地金価格の高騰で売り上げが上振れした側面はありますが、比率はビジョン2030で描いた数字に既に近づいています。

国際事業黒字化に注力
蒲地 各事業の今後の見通しを教えてください。
平能 建材事業は強みである自然換気、カーボンニュートラルに向けた高断熱、リニューアルに注力し、付加価値を訴求していきます。取り組み始めて9年目の国際事業は黒字化が急務ですが、徐々に手応えは感じています。マテリアル事業は国内外合わせて成長を図りたい分野であり、軽量化が求められる電気自動車関連をはじめとして伸ばしていきたいと考えています。商業施設事業は、コンビニをはじめ小売業界で省力化や省人化に向けた改装投資が期待でき、それに対応していきます。
領域拡大では、10年以上前から植物工場事業を手掛け、技術的なストックを積み上げてきました。当初は自社で設備投資をして、野菜を販売しようと始めました。今は大和ハウス工業と提携し、植物を栽培するシステムを販売しています。この事業を育てるとともに、新規事業にも取り組んでいきます。
蒲地 三協立山グループが2050年までに目指す目標として「サステナビリティビジョン2050」を設定されていますね。
平能 「サステナビリティビジョン2050」は、日本が2050年までに目指すカーボンニュートラルに対し、当社がどう寄与できるか考え、21年に策定しました。「カーボンニュートラルへの挑戦」「資源の循環」「人財を未来へつなぐ」の三つの方向性と、それぞれのマテリアリティ(重要課題)を設定し、2030年度時点での目標値を定めています。
蒲地 カーボンニュートラルの進ちょくはいかがですか。
平能 当社は生産活動全体で多くのCO2を排出しています。50年のカーボンニュートラルに向け、まず30年度に基準年の50%に削減することを目標にしています。本社や支店、工場の照明をLED化したほか、工場などでバッテリー式のフォークリフトの導入を進めています。また22年は国内の4工場、23年は2工場で、CO2フリー電力を導入し、合わせて年間約1万4千㌧を削減できたとみています。今後のさらなる技術革新も見据え、実現していきます。
蒲地 「資源の循環」は何が鍵になりますか。

平能 サーキュラーエコノミー(循環経済)に向けてはアルミのリサイクルが重要課題です。生産工程で発生した端材は、100%リサイクルを達成しています。市中から求めたスクラップ材も含めたリサイクル率は約50%で、さらに高めていきます。リサイクル材を溶解してアルミ製品を作る場合、化石燃料由来の電力を使って精錬したアルミと比較すると、エネルギー消費量が約3%で済み、CO2排出量の大きな削減につながります。一方でアルミ関連業界全てが取り組み、リサイクル比率が上がると、原材料と位置づけられるスクラップが不足することが考えられます。
富山大と共同研究
蒲地 アルミリサイクルについて富山大学と共同研究を進めていますね。
平能 富山大学と共同研究講座を2022年に開設し、アルミのリサイクルと、超高強度アルミ合金の押出加工・熱処理プロセスに関する研究に取り組んでいます。アルミリサイクルでは、スクラップの不純物の除去が課題です。アルミ合金は他の金属材料も含んでいます。スクラップを押出材として使用可能なレベルまでアップグレードする技術はまだ確立できていません。これができると、いろんなスクラップのリサイクルが可能になります。
研究は富山大学高岡キャンパスにできた軽金属材料共同研究棟で進めています。とても魅力ある施設で、オープンイノベーションの進化や、地域振興モデル創造に寄与する産学官民の融合拠点として、いろんな研究に携わりたいと思っています。
一方、リサイクルは地球環境のために当然やらなければならないことですが、コストがかかります。我々はコストダウンして商業ベースに乗せるところまで技術革新をしていかねばなりません。

女性活躍へ意識改革
蒲地 「人財を未来へつなぐ」では、2030年までに女性管理職の比率10%を目指していますね。
平能 女性活躍に関して当社は遅れていると言わざるを得ない段階です。女性管理職の比率は現在約2%です。比率アップに向け、その予備軍が増えてくれることが課題です。男性社員の意識や企業文化も変えていかなければならない。ただ、数字にばかりとらわれず、社内風土を抜本的に変えていこうと考えています。いろんな研修メニューを作ったり、外部講師の力を借りて社員のマインドを刺激したりして、女性社員が中核人材や経営視点を持った人材になるよう育成に取り組んでいます。次の中期経営計画で、さらに積極的にやっていきます。
蒲地 東京証券取引所は最上位「プライム市場」に上場する企業に対し、女性役員の比率を2030年までに30%以上にするよう求めています。
平能 当社はまだ女性の社外取締役1人です。プロパーの社員の中から女性役員を出すために、女性がどんどん活躍できるようにお膳立てをしていくつもりです。
蒲地 最後に経営理念への思いを伺います。昨今、「株主資本主義」に代わって「ステークホルダー(利害関係者)資本主義」が注目を集める中、三協立山の経営理念は時代を先取りしたものと言えます。
平能 当社の経営理念「お得意先、地域社会、社員の協業のもと、新しい価値を創造し、お客様への喜びと満足の提供を通じて豊かな暮らしの実現に貢献をする」は、三協アルミニウム工業創業者の竹平政太郎の「三者協業の精神」を受け継いだものです。当社はこの理念を不変のものとして大切にしています。一方で、成長のために変えるべきところは積極的に変える。また変われる会社でなければいけないとも思っています。

(12月26日紙面掲載)
あの頃の私
入社以来、長い年月、ビル用建材の営業に携わってきました。
最初の赴任地は名古屋支店。そして入社11年目に東京支店へ異動になりました。それが1993(平成55)年、バブル崩壊後まもなくのことでした。名古屋での営業時代にバブルを経験したと言っても、東京のそれと比較すれば至って控えめなものだったことが異動して分かりました。それぐらい東京のバブルはスケールが大きかった。その後始末、後遺症に悪戦苦闘する日々が続きました。
大きな混乱から立ち直ろうと懸命に取り組む中で、営業の基本に立ち返る、基本に忠実に向き合うことこそ解になると強く意識しました。当たり前のことを当たり前にすることが重要だということです。まだ若かったこともあり、営業の姿勢を学べた時期だったと、今も思っています。
「あの頃の私」では、若手時代の印象深い出来事や仕事への思いを振り返ってもらいます





北日本新聞は今春に新たな総合情報サイトwebunプラスをスタートし、2024年には創刊140周年を迎えます。本対談は、その記念として展開するシリーズです。
企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局


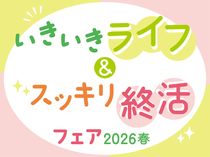



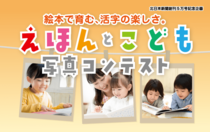
![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)