

変化は、変革への絶好のチャンス
大型ビジョンや電光掲示板、さらに医療機器や半導体製造装置などの産業機械…。コーセルは、人々の生活と深く関わるこれらの機器に安定した電気を送る直流安定化電源を企画開発、生産、販売し、国内トップシェアを誇ります。このほど第10次中期経営計画を公表、さらなる飛躍への一歩を踏み出しました。同社の斉藤盛雄社長と蒲地誠北日本新聞社長がモノづくりへの思いや、その礎となる人財育成、組織のあり方などについて語り合いました。
蒲地 新型コロナウイルス対応のほか、原材料費の高騰、人手不足など製造業の周辺環境が激変する中での舵取りです。トップとしての10カ月間を振り返っていかがでしょうか。
斉藤 昨年8月の社長就任後、多くの人から「大変な時期に社長になられましたね」と声を掛けられました。そんな時には「逆に大変な時の方がいろいろとやりやすいんです」とお答えしました。確かに新型コロナやロシアによるウクライナ侵攻を機に、世界、日本の製造業が抱える課題が顕在化しています。ただ、そうした課題を克服する上で、変化や改革は待ったなしです。変化には抵抗がつきまといますが、今なら小さな抵抗で改革に挑める。むしろチャンスだと受け止めているんです。

社長に就いたその日、全社員に向けて「所信表明」を行いました。過去初めてのことです。その中で「まずは『取り除く』『止める』ことから始めたい」と呼び掛けました。長く継続している案件の中で、単なる前例踏襲で続けていることはないか、目的が不明確になっているものはないか、そんな事案を見直し、止めようということです。もちろん狙いは仕事の生産性を上げ、新たな価値を創造する力に結び付けることです。「古いものを手放さないと、新しいものは入ってこない」って言うでしょう。
蒲地 成長発展に向けたスクラップ&ビルドですね。ただ、さまざまな反発やリスクもあって、一筋縄ではいかないケースを見聞きします。
斉藤 「止める」には一歩踏み出す勇気が必要です。実際、長く市場に出していたある製品を止める(生産中止にする)ことに決めたのですが、当然、社内には反対意見もありました。一定の売り上げが消滅しますし、それを補う新製品開発が必要になる訳ですから。でも将来に向けたコーセルグループ全体の成長を考えて決断しました。簡単なことではありませんが、変革は着実に進んでいます。
モノづくりへの思い
蒲地 所信表明では、品質至上を掲げた「経営理念」と「品質方針」を読み上げられたそうですね。データ偽装など日本の製造業の信頼が揺らぐ中、モノづくりに対する強い意志を感じます。
斉藤 「品質至上を核に社会の信頼に応える」が当社の経営理念です。中国に子会社を作った時、経営理念の重要性をあらためて感じました。最近はこの理念を言えない社員もいるようなので、今一度胸に刻んでほしいと語りかけたわけです。その後も半期の業績報告会など、折々で説明するようにしています。
私たちは「ものづくり」を「モノづくり」とカタカナで表現しています。製品はもちろん、生産設備、治工具、サービスなどを含めて「モノ」ととらえ、品質、納期、コストの面でお客様に満足していただくとの思いを込めています。中でも品質は最も重要です。製品は同じようでも、「モノづくり」は各社各様で、一つ一つの過程にどんな魂が込められているか、価値の違いが出てきます。そういう意味では、コーセルの「モノづくり」は価値の作り込みであり、そこには社員のチャレンジの積み重ねが息づいています。
必ず思いは通じる
蒲地 斉藤社長は2011年、中国での子会社「無錫(むしゃく)コーセル」の立ち上げを自ら牽引、その中心的な役割を果たされました。初の海外生産へのターニングポイントでもあり、自らチャレンジを体現されてきました。

斉藤 東日本大震災から間もなくのことです。無錫市の電源メーカーを訪れた際、現地の方と話が盛り上がり、「会社でも作ろうか」という話が飛び出したのが始まりです。当社としてプロジェクト化し、「じゃあ誰がやるのか?」となった時に、「自分がやります」と手を挙げた。中国という巨大市場を目の前にして、前に進むしかないと感じたからです。ただし、中国語ができるわけでもなく、十分な知識もなく、怖いもの知らずでした。資金の手当て、従業員や仕入れ先の確保、税関とのやり取りなど難しい局面は多々ありましたが、運と縁にも恵まれ、なんとか軌道に乗せることができました。
18年に買収し、現在売り上げが急増しているスウェーデンの「パワーボックス社」もそうなんですが、海外ではさまざまな障壁や困難、トラブルがあります。でも現地の方と心を開いて向き合えば、必ず思いは通じると信じています。まさに仕事に向き合う姿勢そのものです。
蒲地 コーセルは、小集団で品質向上や職場環境の改善に取り組むQCサークル活動を40年以上継続されています。人づくり、組織づくりの観点でその思いをお聞かせください。
斉藤 QCサークルで印象深いのは、立山工場の係長時代です。当時、立山工場に協力会社のパートさん約40人を受け入れ、総勢70人くらいとなった「モノづくり」専門部隊がありました。私はその組織の係長となり、当時の常務から「いったん(生産設備を)全て壊すぐらいの意気込みで、工場のモノづくりを変えてほしい」という特命を受けていました。そんな中、QCサークル活動はパートさんたちとの関係性を深めるために良い機会となりました。みんなで知恵を出し合い、業務改善を繰り返す中で、社員の品質意識が高まり、組織の力も向上しました。

私自身は、QCサークルの担い手を育成する「洋上大学」(約2週間の船での海外研修)の講師を務める機会もいただき、大きな刺激を受けたことを思い出します。
製造業が進化していくためには、先入観に固執せず、現状を変革する現場力を持った人財育成が大切です。そういう観点でQCサークルの意義は大きいし、今後はSDGs(持続可能な開発目標)などもテーマにしていきたいですね。
より「元気な会社」へ
蒲地 これまで斉藤社長のお話をうかがい、果敢に変化に挑み、モノ、人、組織づくりを通して新しい価値を創造しようとする姿勢がよく分かりました。こうした考えは新中期経営計画にも反映されているのですね。
斉藤 第10次中期経営計画策定にあたっての基本的な考え方として盛り込んでいます。計画で掲げた3本の重点戦略を進めるためには、従来の思考や手法の改革が必要です。加えて、どのように達成するのかを具体的に考え、確実に実行することにこだわりました。
従業員にとっては厳しい局面があるかもしれませんが、その分、達成感も大きいはずです。現場の力を活かし、その取り組みの結果がやりがい、働きがいにつながり、最終的にはお客様からの信頼へ、そして持続可能な社会の実現への貢献に結びつけていく。そうした循環で、さらに「元気な会社」にしていきたいと考えています。

(6月21日紙面掲載)
あの頃の私
若い頃に多くの人と出会い、さまざまな考えに触れ、経験できました。30歳の時に立山工場の係長として大所帯を担当したことなど、それぞれが自分の中で大きな意味を持っています。
組合活動との関わりもその一つです。執行委員、副委員長を経て、委員長になったのが20代。ちょうど産別労組の電機連合に直加盟するタイミングで、松山市で行われた集会で3500人を前に加盟あいさつすることになったんです。心臓が飛び出るくらい緊張したのですが、当日の朝、同行した仲間と出掛けた松山城の展望台で練習したことで気持ちがぐっと楽になった思い出があります。
その後、日本を代表するような企業の方々と触れ合う機会ができました。客観的に自分の会社を見ることなど、多くの学びがありました。
委員長は異例の7年間務めることになり、休日増など労働環境の改善に取り組みました。会社の理解を得ながら環境改善できたことは、自分の成長だけではなく、組合そして会社の成長にもつながったと考えています。
社員が元気な会社にしたい、という思いは今も持ち続けています。社長就任後、無駄な会議を減らしましたし、残業は極力せずに率先して帰宅するようにしています。恐らく帰宅時間は会社で一番早いと思いますよ。





北日本新聞は3月に新たな総合情報サイトwebunプラスをスタートし、2024年には創刊140周年を迎えます。本対談は、その記念として展開するシリーズです。
企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局


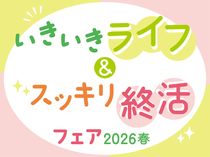



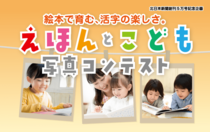
![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)