

地域貢献「ドラえもん」のように
高岡市に本店を置く富山銀行は、地域に密着し、顧客に寄り添い、頼りにされる銀行として、日々進化しています。金融機関を取り巻く環境が変化し、求められる商品・サービスも多様化する中、同行の中沖雄頭取と蒲地誠北日本新聞社長が地域活性化に向けた銀行の将来像やSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みなどについて意見を交わしました。
蒲地 富山産業銀行としてスタートした富山銀行は、来年2月に創立70周年を迎えられます。中沖頭取は目指す銀行像として「地域商社」「情報銀行」を掲げておられますね。
中沖 富山銀行の姿として、いろいろな言葉を使っていますが、一言でいえば、お客さまに満足していただくため、今までと異なる銀行スタイルを目指すということです。当行の行員には「ドラえもんみたいな銀行になろう」と呼び掛けています。作者の藤子・F・不二雄さんは高岡市出身ですからね。体は小さくても、さまざまな便利なものやアイデアが出てきて、困っている人を助けたり、多くの人を喜ばせたりできるような銀行です。

もちろん、融資、預金、決済といった従来業務をしっかり行いながら、同時に事業承継やM&A(合併・買収)、資産運用など多様なサービスを提供していきます。そうした課題解決型のビジネスフィールドを耕すことで、従来業務の取引の幅も広げていく。そんなビジネスモデルを描いています。
事業承継のルールを
蒲地 サービスメニューの一つとして例示された事業承継は、地域経済の大きな課題です。県内では昨年、休廃業・解散した事業所の半数以上が黒字だったというデータがあります。要因に後継者問題があるようです。
中沖 原材料価格やエネルギー価格が上昇する中、黒字の確保は大変なことです。厳しい環境下で頑張っている黒字企業がなくなってしまうのは、地域にとって大きな損失でしょう。私自身、以前から日本でスムーズな事業承継の仕組みがないことを懸念していました。何が問題かというと、中小・中堅のオーナー企業の多くで事業承継に向けたガバナンス・ルールづくりができていないことです。創業家・株主・経営のバランスをとりながら問題解決していけるプロのアドバイザーもほとんどいない。
そこで、コンサルティング会社のフィーモ(東京)と提携し、全国初となる「とやま永続企業支援サービス」を2020年から進めています。提供する支援は、創業家の診断から始まります。事業の永続性に向けたポイントを洗い出すために経営課題や目標を粘り強く聴き、関係者の話し合いを徹底的に行います。その上で創業家の理念や意志決定方式、後継者の育成・選定・退任の手続きなどのルールを「家族憲章」として策定します。時に激しい議論にもなりますが、このルールを定めておけばビジネスに専念でき、従業員も安心する。策定するメリットは大きいと思います。県内第1号案件としてアルミ加工のアルミファクトリーさん(射水市)にご利用いただきました。
フィーモの大澤眞代表取締役は、日銀OBで当行の社外取締役でもあります。このような特別な技能やノウハウを持つ方が身近にいてくれて本当にありがたいと感じています。
蒲地 企業に寄り添った事業承継支援は銀行にとっても、さまざまなメリットがありそうですね。

中沖 当行としては、一連のサービス提供の過程で、お客さまの経営を非常に深く理解することができます。そうすると、お客さまにさらに喜んでいただくためには、どんな提案が必要なのかが見えてくるので、次のビジネスにつながるわけです。お客さまにとっても、銀行側がいろいろと学ばせてもらうことで、資本性ローンを含めたさまざまな融資を利用しやすくなる。事業承継など多彩なコンサル業務を通して、お取引先との関係性を強化していきたいと考えています。
蒲地 地域金融機関が先駆的なベンチャーと組んで地域の課題解決に取り組む意義は大きですね。新しい領域で経験値を積んでこそ、人材が育ち、ビジネスの可能性が見えてきます。
中沖 外部との連携という点では、企業版ふるさと納税を活用した取り組みを進めています。これは、地域企業を支援するRCG(東京)が考案した全国初のスキームを利用します。RCGは地銀などが推薦する地域の特産品を載せたカタログを扱っており、寄付企業にはカタログ価格から最大9割引で提供し、従業員の福利厚生に役立ててもらう仕組みです。既に高岡市など県内5自治体に参画してもらっています。
創業・育成支援の分野でも、スタートアップ企業を支援するArinos(東京)と昨年末に提携し、北陸における起業家の創業・育成を支援する体制を整えました。無料で診断・アドバイスを行い、資金支援もできるのが特徴で、既に問い合わせや具体的な相談も寄せられています。
SDGsを後押し
蒲地 中沖頭取は自らSDGs推進の旗を振っておられます。昨年は優れたビジネスプランを表彰する「TOYAMA SDGs AWARD 2022」も開催されました。
中沖 SDGsの活動は徐々に浸透してきましたが、大事なのは継続していくことです。その意味で、AWARDを企画しました。地域課題の解決に取り組む企業にスポットライトを当てることで、その取り組みを後押しするだけでなく、SDGsの重要性をさらに広め、新たなイノベーションの創出など、地域経済の持続的な発展に結び付ける狙いです。銀行主催のSDGsAWARD事業は全国初の試みです。
AWARDの開催で、実際に新しいお取引先の発掘やビジネスマッチングにつながるケースもありました。特に企業の若手社員や新しいビジネスを目指す起業家を刺激する機会を提供できたのではないかと感じています。AWARDは今後も続けていくつもりです。

CSもESも追求
蒲地 「アスリート採用」の新設を含め、多様性を意識した働きがいのある職場環境づくりを進めておられます。
中沖 行員の働きがいは、地域・お客さま・株主から評価される仕事をするため、必要不可欠なファクターです。職場のDX(デジタルトランスフォーメーション)対応や女性の積極的な登用など、従来から重視してきた顧客満足度(CS)に加え、従業員満足度(ES)も追求していきます。
アスリート採用は地域金融機関としての一つのサポートスタイルです。ハンドボールの新プロリーグに参加する「富山ドリームス」の青沼健太選手を採用しました。また、学生時代から陸上短距離界で活躍し、男子100㍍の県記録保持者の福島聖選手も採用しています。富山でしっかりとした仕事があって、競技活動を続けながら社会人としての経験を積んでいけるような環境を整えることは、地域の活力にもつながります。
ビジネス領域はもちろんですが、こうしたスポーツ分野のほか、北日本新聞社さんにご支援いただいている「高岡・山町ポエム大賞」など教育、芸術文化活動を含めた支援を通じて、これまで以上に地域、人のつながりをつくっていくお手伝いを進めていきます。

(4月3日紙面掲載)
あの頃の私
大学卒業後、日本興業銀行(現みずほ銀行)に入行したのですが、3年目に海外トレーニーでニューヨークに赴任しました。「米国タックス・リース」を勉強してこい、ということでした。
前任の坂井辰史さん(前みずほFG社長)にアドバイスを求めると、「1年は短いが、米国で学べる意義は大きい。旅行気分で行くと痛い目に遭うぞ」と厳しくたしなめられました。まさにその通りで、現地に到着早々、聞いたことのない金融用語が(当たり前ですが)全て英語で飛び交う世界に放り込まれました。米国現法のタックスポジションを活用した大型設備リースを現地の日系企業向けにアレンジするのですが、いきなり分厚い専門書を何冊か渡され、「読んでおけ」。ちんぷんかんぷんの中、先輩に連れられて専門の弁護士や鑑定士とのミーティングに参加し、「次回からはお前が一人で行け」と言われました。少しずつ教えてもらいながらの毎日でしたが、ほとんどの関係者が米国人の中で、自分で決断しなければならない局面も多々あって、最初の3カ月ぐらいは本当に大変でした。難解な税法と微妙に異なる耐用年数や残価分析など、複雑に絡み合う数多くのファクターを織り込んで経済性を極大化する条件を算出するのですが、そのための専用計算ソフトも開発されていました。あたかも未来の金融界にタイムスリップした感覚でした。
たくさん恥もかきましたし、笑われることもありましたが、今、振り返って思うのは、何をやるにしても、準備万端整えるのも良いですが、時には「習うより慣れよ」で飛び込んでいくことも大切かなと思います。
私は富山市舟橋北町で生まれ、安野屋小学校時代には町内対抗の野球大会があり、舟橋北町・南町のチームに所属していました。当時強かった鹿島町チームの監督が元インテック会長の中尾哲雄さん、安野屋町チームの監督が廣貫堂会長の塩井保彦さんで、大きな声を出されていた当時のお二人の印象は強く心に残っています。現在、富山経済同友会の活動などで親しくお付き合いさせていただいていますが、人との縁とは不思議なものだと感じています。






北日本新聞は3月に新たな総合情報サイトwebunプラスをスタートし、2024年には創刊140周年を迎えます。本対談は、その記念として展開するシリーズです。
企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局

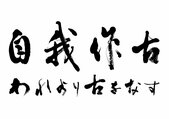






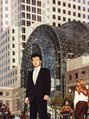






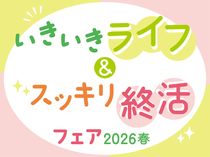



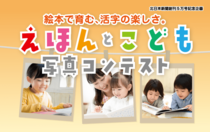
![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)