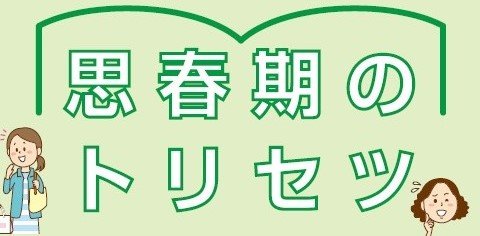
「中学2年の2学期から、子どもの態度がガラッと変わった!」という声をよく聞きますが、一般的に思春期は小学5、6年生から高校3年生くらいと言われます。第二次性徴によってホルモンバランスが変わってくる時期です。急激な体の変化に伴い、心も不安定になります。
思春期は精神的自立の階段を上る時
子どもは、三つの自立を果たして大人になると言われています。
精神的自立‥自分の意思で、親とは違う価値観で行動し始める。思春期。
経済的自立‥自分で生活の糧を稼げるようになる。
思春期は、精神的には自立しているのに、経済的自立はしていない。「親の言うことはちっとも聞かないのに、お金の要求だけしてくる」という親の不満も、まっとうな姿と言えます。
この時期になると、親の言うことさえ聞いていれば安心だったこれまでとは異なり、親の言いなりになるのが嫌で、自分の考えで行動するようになるので、不安になります。そのため友達に依存しがちになり、思春期の友達関係はとても重要になります。
しかし今の中学生たちの人間関係は、SNSの普及で、コミュニケーションが複雑になっています。表面的には友達のように話していても、裏で悪口を言われることもあり、安心して友達に頼れない状況です。そのため人と関わることに不安や怖さを感じている子どももいます。だからこそ大人の支えが必要になります。
手を引っ張ったり 背を押したりしない
友達関係で傷ついたり、部活で失敗したりして、親に頼ってきたときには、支えてあげてください。うまく切り替えられず「自分でやると言ったんだから、こんな時ばかり頼るな」と言いたくなるかもしれませんが、そこは我慢してください。子どもが自分でやるといったときにはやらせる。頼ってきた時には手助けする。思春期の子どもの親は「子どもの後をついていく」イメージです。
子どもが歩いたら、親はその後ろを同じスピードで歩きます。右に行くと言えば親も右に行き、立ち止まったら、歩き出すまで待つ。先回りして手を引っ張ったり、背中を押したりはせず、子どもを前に立たせ、子どもの足で歩かせる。そして子どもが振り返って助けを求めてきた時には、助ける。
もちろん崖から落ちそうなときには「危ないよ」と注意しなければいけませんが、それ以外は後ろからついていきます。
親が寂しい思いをするのは 自立が進んでいる証拠
このような態度で接していれば、子どもは困ったら助けを求めてきます。助けを求めない子どもがいるとすれば「求めても突き放されるだけ」「否定されるだけ」と思っているからです。「今忙しいから」「そんなこと自分でやれ」などとは言わず、必ず助けてあげてください。子どもが思春期になって親が寂しい思いをするのは、子どもの自立がうまく進んでいる証拠です。
反抗期が遅い、ない場合も
子どもによって思春期、反抗期が始まる時期には、個人差があります。女の子は早く、男の子は遅くて高校くらいからということもあります。発達障害の子どもはさらに遅れて20歳過ぎてからということもあります。
反抗期がない場合もあります。ヤングケアラーと言われているような子は立場が逆転しているのでありません。親子のコミュニケーションが本当によく取れていて、反抗する必要がないこともあります。親の反抗期がすごすぎて「反抗している」と感じる感覚が違っている場合もあります。反抗期がないからといって、すべてが心配なケースということでもありません。
不機嫌な時 放っておくことも大事
子どもが学校から帰ってきたら、すごく不機嫌な時があります。声を掛けても「うるさい」という言葉が返ってきます。ただ不機嫌なのは、親に対して怒っているわけではなく、学校で周りからはぶかれないよう空気を読み、人間関係で疲れ切っているからです。そういう時には、放っておくことが大事です。
子どもの側も「学校で嫌なことがあってイライラしている。今は言いたくない」など、できれば言葉で説明してくれると、親も余計な心配をしなくてすみ、無用な親子げんかは減るかもしれません。LINEで伝えるという手もありますね。

明橋 大二(あけはし・だいじ)真生会富山病院心療内科部長、「子育てハッピーアドバイス」シリーズ著者。
1959年、大阪府生まれ。 京都大学医学部卒業。 国立京都病院内科、名古屋大学医学部付属病院精神科、愛知県立城山病院をへて現職。精神保健指定医、小学校スクールカウンセラー、高岡児童相談所嘱託医、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。専門は精神病理学、児童思春期精神医療。







