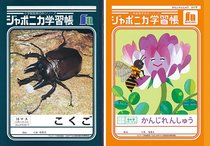夕日の光を浴びてあかね色に輝く田園風景。
コレクションピースに描かれた景色を実際に目の当たりにするとこんな光景が広がります。

水田に家々が点在する砺波平野ならではの景色は、地域の人々の歩みと大きく関係しています。
一帯は最初から農地だったわけではありません。
周りの水田は自ら開墾
一人一人が土地を耕し、田畑を造り、コメ作りを営んできました。
水や肥料の管理、稲の刈り取りなど、日々の作業を踏まえて水田は家の周りに造られ、広がっていったのです。

平野のあちこちに家が散らばった景色は、水田を一枚でも多く広げようと農家それぞれが歯を食いしばって開墾しきてた証しでもあるんです。
暮らし守る「かいにょ」
そんな開拓精神の表れが、家の周りにめぐらされた屋敷林です。
「かいにょ」と呼ばれ、夏の暑さや冬の寒さから暮らしを守ってきました。

それだけではありません。
スギの落ち葉や枝木は、炊事の燃料になりました。
太く大きく育った木は、家を改築したり新築したりする際の材料に使われました。
生活に必要なものを自分たちで賄う「自給自足」の生活を送っていたのでした。

ちなみに散居村の屋敷林保全に取り組む「砺波カイニョ倶楽部」の試算によると、1戸分の屋敷林で16戸が排出する二酸化炭素(CO2)を吸収できるのだとか。
SDG’sなど、持続可能な生活が叫ばれる昨今、こうした昔の暮らしに解決のヒントがあるのかもしれませんね。
コノコトレポーターが散居村横断マラソンに挑んだレポートはこちら
>ファミリーで挑戦!
散居村が舞台になった映画「もみの家」のwebun記事はこちら
>少女の成長 優しく描く
散居村の冬景色を紹介したwebunの記事はこちら
>雪原に浮かぶ屋敷林