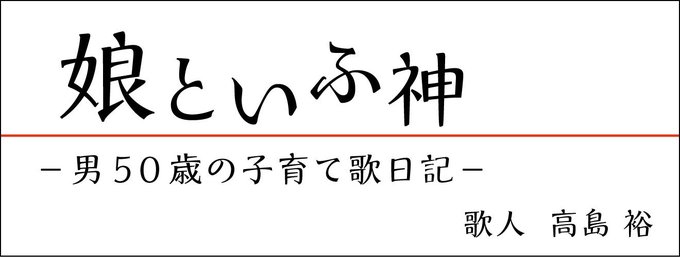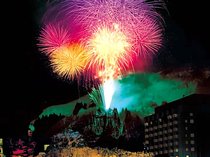春から夏へ。
私たち親が葛藤の中でもがいている間も、娘はすくすくと成長してゆく。
娘は、2歳の誕生日を過ぎてもおっぱいをねだり、夜は授乳なしでは寝付けない状態が続いていて、私たちを心配させた。もちろん栄養的には普段の食事で十分で、おっぱいをねだるのは、心理的な要因に違いなかった。
五月、妻が胸部に軽い炎症を起こし、授乳ができなくなった。娘は最初はぐずり、夜中に起きておっぱいを求めて泣いたりしたが、案外あっさりと乳離れができてゆき、おっぱいがなくても寝付けるようになった。
お絵描きにも変化があった。クレヨンや色鉛筆には早くから親しんできたが、これまでは殴り書きのような線を描くだけだった。それがこの頃には丸が描けるようになり、やがて人の顔のようなものを描き始めた。それはもちろん親として嬉しいことだったが、反面、これまで娘の小さな手から生み出されてきた、囚われのない、のびやかな線が、もう二度と見られないことが、少し淋しくもあった。
顔らしきものを描き初む。永遠に失はれたる無碍の線描

言葉、会話についての成長ぶりは、さらに目覚ましいものがあった。
「ねこ」「みかん」といった物の名前だけでなく、副詞や接続詞、助詞、助動詞のような抽象的な語を自然に習得し、使いこなし、まとまった意味内容を表現できるようになるのは、実に不思議である。保育所で集団生活をしていることが、言語、会話の習得を早め、勢いづかせているのに違いない。
ある日、保育所から帰って夕食を食べさせている時、「今日は保育所で何をして遊んだの?」と訊いた。返事がない。もう一度訊く。やっぱり返事がない。ひたすらもぐもぐ食べている。もう一度訊く。すると「琳ちゃん今ごはん食べてるから」と、断られた。思わず笑ったが、この返答ができるためには、言葉と、言葉が発せられる状況についての高度な理解が必要なはずで、そのことが驚きでもあった。
8月頃には、家にある地球儀を示していろいろ教えてみると、「日本」「アメリカ」など、国の名前や位置も少し覚えた。もちろん、実際の地理認識、空間認識ができるわけではないが、「日本大好き」と何度も言う。「日本」が、自分たちが所属する何か大きいものだということは、おぼろげながらわかっているのだろう。
また、公文から出ている「百人一首カード」を使って、和歌を朗詠して聞かせると、娘は読み終わったカードを神妙に手に持って床の上に揃えていった。そして、私が読み聞かせた和歌の断片を「〜けるかも」などと発声した。和歌のリズムや声調を通して、日本語の美しさに親しんでもらいたいと願う。
そして、大好きなアンパンマンの話をする。「アンパンマンを作ったのは?」「ジャムおじさん」「ジャムおじさんのお手伝いをしているのは?」「バタコさん」「一緒に住んでいる犬は?」「めいけんチーズ」。物語の設定、状況がちゃんと理解できているのがわかった。
◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。