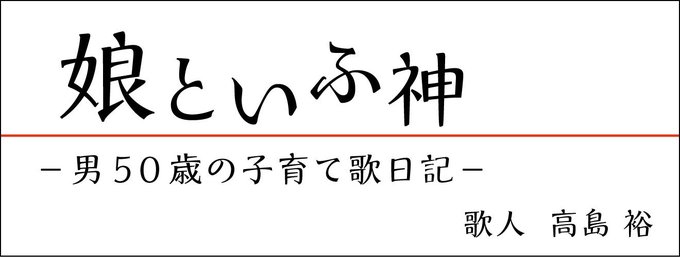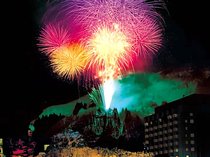夕方四時。得意先の集金に出ていた私に、妻からテレビ電話が入った。妻も仕事中で、会社のユニフォームを着ている。保育所から電話があり、娘が熱を出しているとのことだった。私の方からも掛け直すと、娘は、機嫌は悪くないが、三十八度台の熱を出しているので、迎えに来てほしいとのことだった。保育所へは、妻の会社よりも私の方が近い。妻は私にすぐ行ってくれるように言ったが、子どもが熱を出したからという理由で仕事を抜けることはできかねた。保育所へは妻が迎えに行き、私の方はそのまま仕事を続けた。けれども、娘のことが気になって動揺し、出先の駐車場で社用車のフロントをコンクリの塀にぶつけてしまった。
定時の五時を過ぎてからお医者さんの待合室で娘を抱いた妻に合流し、様子を見た。そしてまた会社に戻って仕事を片付けてから帰宅した。娘は早くに迎えに来てもらって、いつも以上に元気に見えるが、食欲はないようだ。翌日、私はいつも通り出勤し、妻は娘の看病のため会社を休んだ。妻は娘のために捨て身だが、当然ながら、社会人として、仕事のことを心配している。

子どもの親は父と母二人である。けれども現実は、私たちのように二人ともフルタイムで働いていたとしても、働き盛りの父親が、病気のわが子のために仕事を休むことは難しい。結局、病児のケアは母親に負担が集中し、母親だけが、社会的責任のある仕事を中断しなければならない。
今回のようなことは、これからもたびたび起こるだろう。その度に、こんな辛い思いをしなければならないのだろうか。そして何より、病気で弱ったわが子に、親として揺るぎない安心を与えることができず、不安な思いをさせてしまうのではないかと心配だ。
私は、市役所に電話して、病児のケアについて相談したが、市役所では病児保育に関わっておらず、ご相談は担当の保育所へどうぞ、というものだった。病児保育という深刻な社会的問題について、市役所がまったくタッチしておらず、市内の一保育所に丸投げしているという事実に驚愕した。
私は、その保育所に電話を入れ、昼休みの時間をやりくりして、見学に行った。保育所付きの看護師さんが親切に対応してくださった。病後児の保育室は、手狭だが、明るくきれいで、おもちゃなどが具えてある。今日は利用者がなく、こんな日なら預かってもらえるだろう。けれども、あくまでも病後児であり、三十八度以上の熱があると、預かってもらえない。また、感染防止のため、複数児童の預かりは避けたいとのことだった。事前登録だけはしておく。「本当に切実に必要なのは、病後児でなく、病児保育なんですよね」と、その看護師さんは言った。そして、市外の病院などで、病児保育をしているところがあることも教えてくださった。一方、やはり家で看た方が、子どもの治りが早いことも言われた。
以前、私たちは、認知症になった母のケアのため、市役所や病院、施設をさまざま回って相談したが、高齢者に対する社会的なバックアップは、想像以上に手厚く整備されていると感じた。それにひきかえ、育児に対する社会的なサポートは、ひどく立ち遅れているように思える。地域のサポートセンターも、なり手がおらず、機能していない。
後日、娘の保育所でそのことを相談した妻は、市として、病児・病後児保育はすすめない、という方針をはっきり聞かされた。私は、憤りに近い感情を覚えた。そして、その日の連絡帳に、日々懸命に子どもたちを見てくださっている保育所のみなさんへの感謝とともに、切実に病児保育を必要としている私たちのような親がいることを、何かの機会にお伝えください、と書いた。
性差別性分業の暗がりに昭和のままの塩ビ床臭ふ
◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。