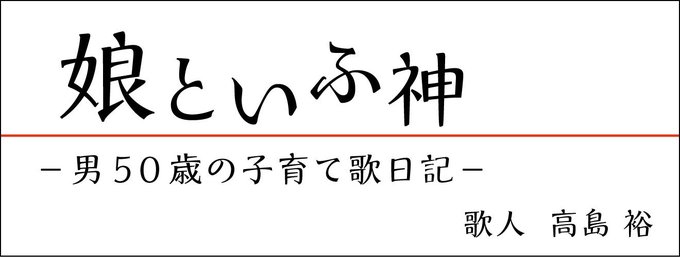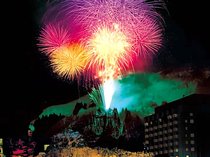娘は、もうすぐ二歳になろうとしていた。少しずつ意味のある会話ができるようになってきた。食事の時に「おかわりください」と言ったり、自分が食べているみかんなど、分けて私たちにくれたりするようになった。やはり、保育所での集団生活が、コミュニケーション能力を高めてくれているのだろう。
さて、妻は、将来を見据えて求職活動をしていたが、二月の末頃から、フルタイムの正社員として会社勤務することになった。妻は、入社の条件を何度も先方と話し合い、確認した。保育所の送り迎えがあるので朝は少し遅れて出勤すること、残業はあまりできないこと、娘が病気の際には休まねばならないこと、自営のデザインの仕事は続けること、などを了承していただいた。また、妻の、デザイナーとしてのスキルや経験を活かせる職場でもあり、この会社との出会いは、大切にした方が良いと思えた。
一方私は私で、管理職に転じて四ヶ月、頑張って仕事を覚えつつ、気を張って日々勤めていた。こうして、娘を保育所に預けながら、私たち両親ともにフルタイムで働く、という生活が始まった。それには大きな労苦と困難が予想されたが、挑戦することにした。私たちが高齢で授かった娘なので、育て上げるまでには、二人とも仕事を頑張る必要がある。それに、妻には妻自身の、働き、表現する喜びを感じつつ暮らしてもらいたいとも思った。
試練はさっそく訪れた。二月の終わりの火曜日の夜、元気だった娘が、何度も咳をして目を覚ました。翌朝、体温を測ると、38度以上あった。妻は、前日は歯の手術のため入社早々休んでいたので、いくら理解のある会社とはいえ、続けては休めない。私が休んで娘を医者に連れていき、看病するしかない。そこで、早朝出社して上司同僚に事情を話し、後を託して、7時半に家に戻った。手術後の歯の痛みと、そのために食事もとれない状態のまま出社していく妻を見送り、9時40分の予約に間に合うように、娘をかかりつけの小児科医に連れて行く。娘は見た目は元気。不慣れな私を気遣うように、おとなしくしてくれていた。
診察の結果、風邪だが、喉の奥の厄介なところにウイルスが着いているので、長引くかも知れない、とのことだった。保育所へは、熱が下がって丸一日経過し、眠れて食べられる状態になってからでないと、行かせられない。鼻、口の吸入をしてもらって、薬も出してもらって帰る。
平日の日中のわが家。娘と二人、久しぶりに静かな時間が流れる。昨夜あまり眠れなかったせいだろう、娘はぐっすりと昼寝する。起きてから、スクランブルエッグを作り、パン、ヨーグルト、みかんゼリーと合わせて、遅めの昼食を食べさせる。その間、職場とは随時電話連絡を取り合って対応した。
翌日は、妻に休んでもらって娘をみてもらい、私は出社した。昨日休んだことについて、上司も同僚もこころよく了承してくれたのだが、ちょうど入札時期に当たり、同僚は早朝から深夜まで働き詰めだった。その中で、管理職にある私が一日休んだことについて、社内では、疑問と批判の声が上がっているようで、それがひしひしと伝わってきた。私自身それはよくわかっていて、会社のみんなには申し訳ない気持ちでいっぱいだった。だが一方で、夫婦ともに働く中で、病気の娘を世話し、安心させることは、人として当然のことだ。…答えのない問題に私たちが悩み、途方に暮れる中、娘は徐々に回復し、二歳の誕生日を迎える。
この日々を届かぬ夢の美(くは)しさで想ひ出す日のあらむ 薄雪

◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。