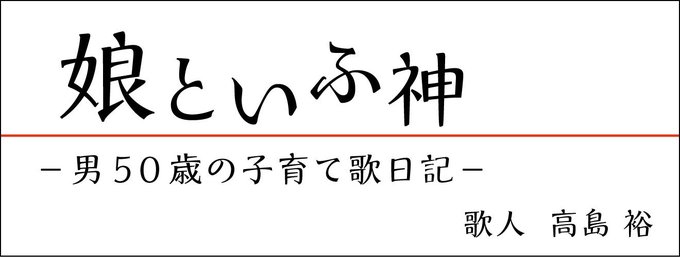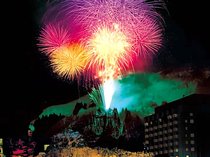一歳半の節目を過ぎ、娘はますます成長してゆく。言葉は、物の名前だけでなく、簡単なセンテンスを言おうとするようになってきた。また、気付き、発見の鋭さに驚かされることもしばしばだった。夕方迎えに行き、抱っこして保育所の玄関を出ようとすると、私の腕の中で「お靴、お靴」と言って、小さい手で下足箱を指さした。私がズックを履かせるのを忘れているのを教えてくれたのだ。
秋が深まる頃、私の職場環境が大きく変わった。入社以来十四年間続けてきた現場常駐の勤務から、本社の管理職へと異動になったのだ。これは栄転といえる異動であり、幼い娘を抱えたわが家の将来を考えれば、ありがたいことである。
だがその一方で、職責が重くなり、忙しくなって、定時に退社したり、規定通りに休日を取ったりするのが難しくなり、家族とともに過ごし、家事育児に携わる時間が減ってしまうのではないかと懸念された。その懸念は現実のものとなった。

一昔前であれば、外でバリバリ働いてたくさん稼ぐことが男の本分とされ、家事育児はもっぱら妻の役割とされてきたが、今の時代は、そう単純にはいかない。
頑張って働き続ければ、勤続年数につれて昇級してゆくという保証は、もうない。一般的に賃金の水準は抑えられ、夫婦ともに働かなければ家計は成り立たない。そうすると、今までのままの考え方では、仕事に家事育児にと、妻ばかりに負担がかかってしまう。男は仕事だけ頑張ればいい、という時代ではないのだ。
とくに私たちの場合、歳をとってから授かった子を育て上げないといけないので、二人とも、働ける間は精一杯働かなければならない。私は、朝まだ暗いうちに家を出て出社し、今までは隔週で休んでいた土曜日も出勤しなければならなくなった。
そして、仕事自体もまた、厳しい時代の波に洗われていた。深刻な人手不足のため、全体的に長時間労働と休日出勤が常態化していた。それはこのご時世、どの企業、どの業種においても見られることで、私の会社が特別なわけではない。私の立場が変わって、それをまともに被ることになっただけだ。
そんな中、心苦しさに胸を痛めながら、保育所の迎えのために夕方六時頃に帰らせてもらい、また保育所に預けられない日曜日だけは必ず休めるようにしてもらった。職場の状況と私の立場を考えれば、それは破格の厚遇なのだが、それでも、家事育児を全うするには十分ではない。この問題は、後々さらに深刻なものとなる。
そんな中、娘にとって母方の従姉妹となる子の七五三参りに同行して、親族みんなで長野の善光寺を訪れた。娘はみなさんに可愛がられ、秋の穏やかな日差しの中、笑い、歩き、喋った。階段の昇り降りにも何度も挑戦し、上手にできるようになった。
黄葉(もみぢば)は光のごとく降り灑(そそ)ぐ、おまへが生きてゆくこの世界
◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。