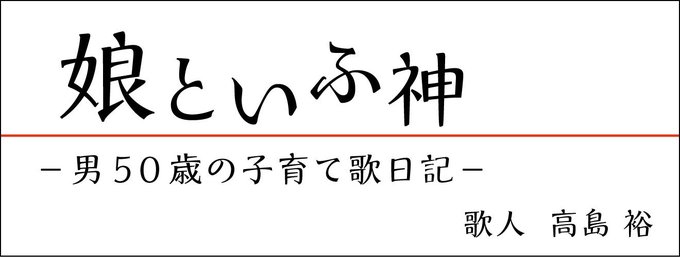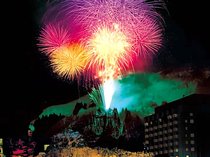夏が過ぎ、娘は一歳半の節目を迎えた。ときどき熱を出したり咳が出たりして休む日もあったが、毎日元気に保育所に通い、他の子たちや先生方と触れ合う中で、すくすくと成長し、いろんなことを覚えていった。詩歌に携っている私のような父親にとっては、言葉の習得が、ひときわ大きな関心事であった。この頃には、「バナナ」「ライオン」といった具体的な物を指す言葉だけでなく、「たくさん」「動物」そして数字の「イチ、ニ、サン」など、目に見えない抽象的な概念を指す言葉も理解し、発語するようになってきた。どういうプロセスでそれを理解し、言えるようになるのか、実に不思議である。
この九月には、保育所の運動会もあった。私は妻と二人で行って、娘と一緒に競技にも参加した。妻の実家のみなさんも来てくださった。段ボールの橇(そり)のようなものに入った娘を親が引っ張って、物を取ってくる、というようなものだったと思う。娘にとって、人生で初めての運動会だったが、物怖じせず、元気に楽しんでいた。この地域の皆さんの、熱心なことにも驚いた。妻に急かされて朝早くからレジャーシートなどを持って場所取りに行ったのだが、すでにお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんがたくさん来ておられた。子どもの運動会とはこういうものなんだと、初めてわかった気がした。

この九月には、一歳六ヶ月児健診もあった。私が仕事で常駐している総合病院に併設された、市の健康センターで実施されたので、昼は病院の食堂で落ち合って、親子三人でランチを共にした。それから私は仕事に、妻は娘を連れて健診に行った。
ところが、健診が済んだ後、私は妻に、院内のカフェに呼び出された。妻は暗い顔をしていた。何事かと話を聞くと、健診の担当の医師から、娘の身長体重が平均を下回っていること、母子手帳の記入に不備が多いことを厳しく叱責され、母親失格だというようなことを言われたという。妻はショックで打ちひしがれていたが、話を聞いた私は、怒りの感情を覚えた。妻が娘のためにどれだけ身を粉にして頑張っているかは、私が一番よく知っている。娘が今どうして欲しいのか、娘に今何が必要なのかを瞬時に理解し、娘に辛い思いをさせないようにいつも気を張っている姿を私は毎日見ている。私にはその医師の言動は、目の前の一人の母親にきちんと向き合おうとせず、自らの経験に甘え凭(もた)れた、傲慢(ごうまん)な態度だと思えた。私は妻を励まし、自信を持つように言った。そして保育所の連絡帳にこのことを書き、健康センターの方へも抗議の声を伝えた。すると、毎日妻の姿を見ている保母さんたちも妻に同情し、どういうことなのかと市役所に問い合わせてくださった。子どもの発育には個人差があり、数字だけを見て母親を責めるのはおかしい、とみなさん言っておられた。
この健診ではもう一つ、育児相談の保健師さんから、母親の負担軽減のため、保育所の迎えの方は、父親がすべきだとのアドバイスを頂いた。さっそく次の日から毎夕、頑張って仕事を早く切り上げ、6時過ぎに保育所へ迎えに行くようにした。急いで保育室に入ると、私を見つけた娘が、さっと顔をほころばせて駆け寄って来る、自然な衝動のままに抱き上げる。この瞬間の嬉しさ、愛おしさはたとえようがない。
夕闇はもどかしき幕、ほころびて寄り来る者を抱き上げにけり
この時間に残っている子は少なく、娘一人の日もあるが、この年齢の子どもは、まだその状況に淋しさを感じることはないそうだ。
◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。