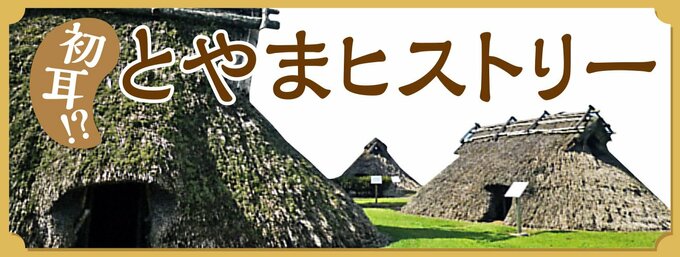「富山売薬」と言えば、2代富山藩主の前田正甫(まえだ・まさとし)が、藩外への売り込みを奨励したことが始まりとされる。
富山藩は売薬を産業として保護した。一方で売薬業者には運上金などを課して藩の財源とした。
売薬業者は明治に入ると、有力な資本家に育っていった。その中の一つに、屋号「能登屋」の密田(みつだ)家があった。

富山売薬のきっかけをつくった富山藩2代藩主の前田正甫公の像=富山城址公園

商家建築の名残がある旧密田家土蔵=富山市売薬資料館
昆布が明治維新の原動力に
江戸末期。加賀藩と、その支配を受けた支藩の富山藩からは、幕府を倒して新しい日本をつくろうとする動きは生まれなかった。加賀藩は大藩でありながら古いしきたりにとらわれ、佐幕(幕府を支える)か倒幕かを巡って八方美人的な対応に終始した。
密田家は蔵宿や質屋も営んでいたが、本業の売薬では薩摩藩に多くの懸場(かけば、商売範囲)を持ち、売薬商人の責任者になることもあった。北前船を所有し、北海道の昆布などを仕入れていた。国産昆布は9割以上が北海道産である。

廻船問屋の室内に展示された北前船の模型=高岡市伏木北前船資料館
富山藩の売薬業者は全国で商いをしたが、行商に対して厳しかった薩摩藩では、藩内で売薬を続けさせてもらうために昆布を献上した。
残り1373文字(全文:1921文字)