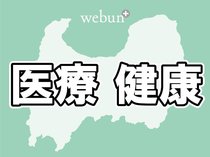富山県を拠点とする地方紙「北日本新聞」。前身である「中越新聞」が創刊された1884(明治17)年から数えて今年で創刊140年を迎えた。でも待てよ、なぜ「北日本」なのか。意外と知られていない弊社の名前の由来をあらためて調べた。

北日本新聞の名前の由来や名付け親については、これまでに何度か本紙に登場したことがある。「聞いた(読んだ)ときには『へ~!』と感心させられるけど、しばらくするとうろ覚えになってしまい、聞くたびに『へ~!』となる雑学」くらいの印象のエピソードなので、読んだことがあっても正確に覚えている人は少ないのではないだろうか。
インターネット上ではどうだろう。オンライン上の百科事典「Wikipedia」にある「北日本新聞」の項目では、「1940(昭和15)年7月31日に北日本新聞社設立」とある。さらに「8月1日 言論統制下の新聞事業令に基づき富山日報、高岡新聞(1931年、高岡新報より改題)、北陸日日新聞、北陸タイムスの4紙が統合して北日本新聞を創刊」と書かれている。富山でも高岡でも北陸でもなく「北日本」を冠した理由は触れられていない(2024年9月8日時点)。
富山県は「北日本」?
そもそも「北日本」とはどのエリアを指すのか。気象庁の定義によると、北日本は北海道、東北を指し、富山を含む北陸は「東日本日本海側」「中部地方」に分類されている。多くの人が日々接している天気予報で「北日本」に富山県が入っていない影響は大きいようで、ネット上でも富山県の新聞社が「北日本」を名乗ることへの疑問がいくつか見つかった。
ただ地理関係の辞典などを調べてみると別の視点もあった。北日本の説明として、次のように書かれている。
「元来東北日本もしくは東日本の一部を意味するが、地体構造や地質・地形のうえでは東北日本・東日本と同義に使うことがある。日本列島は、関東地方以西で東西方向を示すのに対し、関東地方で方向を変えて南北方向となるので、この部分を北日本と表現するが、その範囲は北海道・東北地方で関東地方は通常含まれない」
「しばしば北陸地方を中心とする日本列島の日本海側、裏日本の北部を北日本と呼ぶことがあるが、これは中世以降北陸を北国(ほっこく)とも称したことからくる関連性もあろう」
「東北地方・北海道の総称。地体構造・地質・地形上ではしばしば東北日本・東日本と同義。狭義には北海道を指す。北国(ほっこく)は北陸と同義で、北日本と部分的に重なる」
「東北や北海道の総称」である点は気象庁の定義と同じだが、北陸を中心とする日本海側を意味することもあるとしている。背景として「中世以降北陸を北国とも称したことから」と指摘しているように、京都を中心に日本を見ると北陸を「北日本」と呼んでもおかしくはない。実際、北陸に「北日本」を冠する企業はいくつもある。
一度は却下
では具体的にどのような理由や経緯で「北日本新聞」になったのだろう。「北日本新聞百二十年史」を読むと、主な理由は以下の通りだ。
・明治期に東京で発行されていた新聞「日本」にあやかった
・加藤金次郎(統合前の北陸日日の社主で、統合新会社の取締役)が主張した
・統合する4社(富山日報、高岡新聞、北陸日日新聞、北陸タイムス)のどれにも類似していない
・最も無難である
もう少し詳しく説明すると、経緯はこうだ。まず1933(昭和8)年に「富山新報」の経営権を買い受けた加藤金次郎が、紙名を改めるよう主張し「北日本新聞」を候補として提案した。以下、社史から引用する。
「北日本新聞」という名称案は却下され、「富山新報」は「北陸日日新聞」に変更された。誰の発言かは示されていないが、「東北・北海道の新聞と間違われやすい」という反対の声は説得力を感じる。実際、県外から富山県に引っ越してきた人から「富山県の新聞とは思わなかった」と言われたことがある。
ただ「富山県(または北陸)の新聞と伝わらない」ではなく、「東北・北海道と間違われやすい」という指摘になるあたり、「北日本」が北陸を含むエリアを指す用語としても認識されていることがうかがえる。
社史の年表によると、この議論から約30年さかのぼる1901(明治34)年に高岡市で「北日本新聞」が創刊され、2年後の1903(明治36)年12月に廃刊になったとある。詳細は記されていないものの、おそらく当時は富山県または北陸の新聞社が「北日本」を名乗ることに違和感はなかったのだろう。
「北日本新聞」を主張した加藤金次郎(1884~1966年)は土木実業家で、多彩な活躍をしている。「富山大百科事典」によると、滑川町で土木請負業加藤重右衛門の子として生まれ、県内の電源開発や鉄道敷設に関わったほか、朝鮮や台湾でも農場やダム、鉄道などを手がけ、滑川町長も務めた。独自の工法を編み出して特許を取るなど発明家としての一面もあった。経歴を見ると、「日本新聞」という名称を提案しても不思議ではないスケールの大きさを感じさせる。
「小学校卒業後、父の作業現場で働いて重用される。『太閤記』や『三国志』を愛読して才知に秀で、15歳のころに海岸突堤工事の囲石枠工法を案出して注目を浴びたという」とも書かれており、現代に生まれても起業家として大活躍しそうだ。
再び候補として浮上
いったんは却下された「北日本新聞」だったが、1940(昭和15)年に富山日報、高岡新聞、北陸日日新聞、北陸タイムスが統合する際、新紙名候補として浮上した。北陸日日新聞を経営し、統合会社の経営陣に加わった加藤が再び「北日本新聞」を主張したためだ。社史には「名付け親は加藤金次郎」という見出しに続き、次のような経緯が記されている。
現在に続く北日本新聞の誕生である。あらためて社史を読むと、北日本新聞の前身である中越新聞が創刊号で政府批判をしていきなり発行禁止処分になるなど、決して無難ではなく、むしろ先人が多難な歴史を乗り越えて今があることが分かった。
「東北・北海道の新聞と間違われやすい」という懸念は解消されていないが、紙面もwebunプラスも富山県内の情報満載で、富山県の地元紙であることは間違いようのない内容だ。富山で暮らす人や富山にかかわる人にはぜひ読んでほしい。(本田健司)