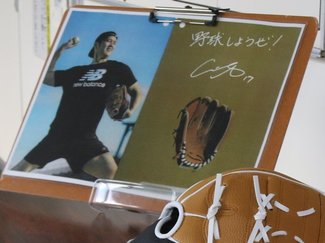正月気分が一気に吹き飛んだという人が大半だったのではないか。1日午後4時10分ごろ発生した石川県能登地方を震源とする「令和6年能登半島地震」は現在も被害の全容がはっきりしていない。被災地では行方不明者の懸命の捜索が続いているほか、避難所暮らしを強いられている人も少なくない。今回の地震は過去の巨大地震と比較して、どの程度のものだったのか。17日は阪神・淡路大震災が発生してちょうど29年。指標の一つとなるマグニチュード(M)について調べてみた。
地震の規模とは
マグニチュードはニュースなどで「地震の規模を示す」との説明書きが付く。気象庁は今回の地震をM7・6と発表した。では、具体的に「地震の規模」とはどういうことなのだろうか。
気象庁地震津波防災推進室は「その地震が起きて生じたエネルギーと考えてほしい」と話す。地震は地下の断層が何らかの理由でずれることによって生じる。ずれた距離や面積などを複雑な計算式に当てはめて算出するのがマグニチュードだ。
同推進室は「今回は石川県珠洲市付近から断層が割れ始め、陸と海にかけて100キロ以上にわたってずれたのではないか」と話す。100キロ以上とはかなりのスケールだが、今回の地震を思えば十分うなずける話だ。それだけのエネルギーがあれだけの災害をもたらしたということだ。
0・1違うと…
ちなみに29年前の1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災はM7・3。能登半島地震のM7・6はそれよりやや高い数値だと思ったが、とんでもない誤解だった。同推進室によると、マグニチュードは特殊な計算式を用いるため、0・1高ければエネルギーは約1・4倍も違うのだという。0・3違えば約1・4の3乗なので約2・8倍。つまり能登半島地震は関西を中心に甚大な被害を出した阪神・淡路大震災の3倍近いエネルギーが働いたということだ。
2011年3月11日の東日本大震災はM9・0。能登半島地震より数値は1・4高い。そのエネルギー量は計算すると約128倍となる。13年前の東北地方の惨状は今も記憶に新しい。自然災害のすさまじさに改めて寒気がした。
マグニチュードと並ぶ地震の指標として「震度」