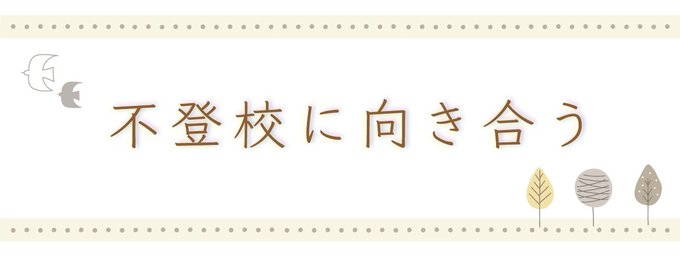夫婦の方針が違うのは当たり前
夫婦の方針が違うのはある意味、当たり前です。価値観も違う。「両親の方針がそろってなければ子どもが混乱するだろう」と心配する人がいますが、それは子どもの判断する力を過小評価しています。子どもはただ「お父ちゃんとお母ちゃんの意見は違うんやな」と理解するだけでしょう。いろいろな考えの人がいること、それが当たり前であることを、学べる一つのいい機会だと思います。
そして、もし一方の親のが小言をやめられない(やめるつもりがない)としても、もう一方の親だけでも小言を控えてやさしく子どもに接することができれば、子どもにとっては十分に大きな支えになります。
それだけでも子どもはおおいに救われるでしょう。子どもが成長するにつれて、やがて小言をいう親に反発する日が来るでしょう。親と対決するときが来るかもしれません。それとて、困ったことではなく子どもが成長していく大事な過程といえるでしょう。
平和的に話し合う姿を子どもに見せて
もう一つ。夫婦で、育児の方針などが違っている場合、そのことについて話し合うことは、とても大切なことだと思います。価値観が合わないとき、意見がぶつかったときに大人たちは、どうやってその状況を克服していくのか。
大きな声でおどしたり、不機嫌になってふてくされたり。そうやって、相手に言うことを聞かせようとする、そんな好ましくないやり方を子どもに見せることは、まずいことだということはわかると思います。感情的にならずに、もてる知恵やユーモアを上手に使って、相手と自分の妥協点をさぐっていく。平和的に話し合う素敵な大人の姿を子どもにしっかり見せましょう。

感謝の言葉が人の行動を変える
一方の親だけが、小言をやめられない場合、それを減らしたければ、注意するよりも感謝する方が効果があるようです。コンビニのトイレに「いつもキレイに使っていただきありがとうございます」という張り紙がしてありますね。感謝の言葉です。「汚さないように使ってください」という「注意」よりも「感謝」のことばのほうが、人の行動を変える力があるからです。
「子どもに小言を言うのをやめてください」と注意するよりも「子どもに小言を控えて見守ってくれてありがとう」と、上手に感謝の言葉を伝える。「あなたがやさしくしてくれるようになってから、子どもがすごく幸せそう。ありがとう」などと声をかけてみる。「あの子は、あなたのことが大好きなのよ」とか、「このごろ、子どもがリラックスしていて、いつも楽しそう」など、根気よく、メッセージを伝え続けたら、相手も変わるのではないでしょうか。自分もかわるでしょう。
母親の負担軽減が心のゆとりに
最後に、このような質問はたいてい母親からのものです。育児の問題に悩んで相談に来る親の多くは母親だからです。日本ではいまだに子育ての負担が母親に大きく偏っています。

現在の若い世代の父親は、その親世代よりも家事や育児により積極的に関わるようになってきてはいるようです。それでも母親の負担の方がまだずっと大きい。料理、ゴミ出し、買い物、洗濯、風呂掃除、そのほか無数にある名もない家事。父親がこれらにより多く取り組めば、母親の負担は減り、その恩恵は親の心のゆとりとなって、子どもに届くことになります。そのような子どもへの愛情の与え方もあります。
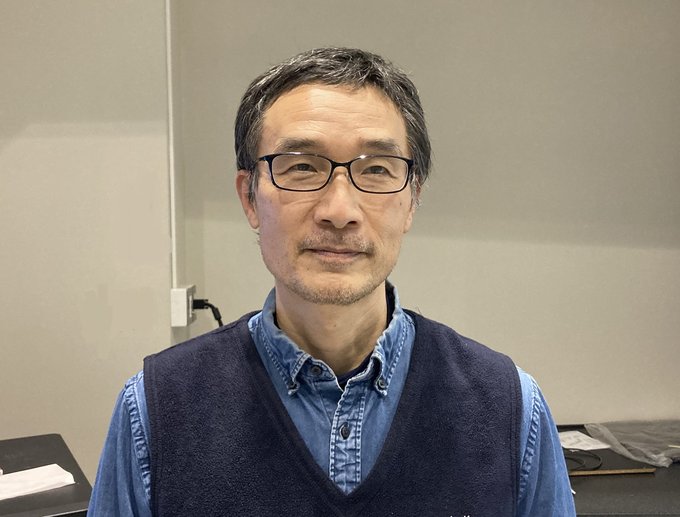
田中茂樹(たなか・しげき) 医師、臨床心理士
1965年東京都生まれ。京都大医学部卒。仁愛大人間学部心理学科教授などを経て、現在は佐保川診療所長。著書に「子どもを信じること」(さいはて社)。