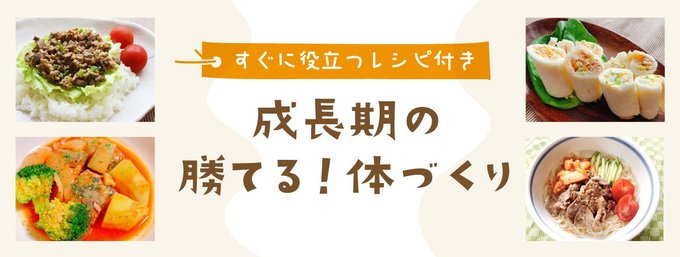食事を食べる時のあいさつ「いただきます」。普段なんとなく言っていませんか?本来どんな意味を持っているのか、改めて考えてみましょう。
「いただきます」の語源は、動詞の「いただく」です。神様にお供えした物を食べるときや、位の高い人から物を受け取るときになどに頂(いただき。頭の上)に掲げたことから、「もらう」の謙譲語として使われるようになったとされます。それがやがて、食事を始める時のあいさつになりました。
「いただきます」は、感謝とお礼の気持ちを表しています。日本では地域によって、食事の際の習慣などに違いがありますが、手を合わせて「いただきます」というあいさつには地域差が見られません。
 「いただきます」には2つの意味があります。
「いただきます」には2つの意味があります。
1つ目は食事に携わってくれた方々への感謝
食事が食卓に並ぶまでには、さまざまな人の手を介しています。食材を作る生産者の方をはじめ、運んだり、売ったりする流通の方、料理を作り、配膳する方。給食では献立を考え、安全に提供するために衛生管理を行う方もいます。生産、流通、調理…その食事に関わった全ての方々への感謝の意味が込められています。
2つ目は食材への感謝
私たちは生きるために、肉や魚、大豆、野菜、海藻、果物などさまざまな物を食べて体を作っています。そして、肉や魚はもちろんのこと、野菜や果物などあらゆる食材に命があります。
「いただきます」には「命を頂き、自らの命にさせていただきます」 という意味が込められています。好き嫌いや食べ残し、味付けなどの問題はありますが、食事は「大切な命をいただいている」ということを忘れてはいけません。
何気なく言っている「いただきます」には、このような感謝の思いが込められています。「いただきます」という言葉の意味をもう一度思い出し、食事をしてみるのも良いのではないでしょうか。
次回は、寒い日に温まる汁物をご紹介します。
◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士
富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。
日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。