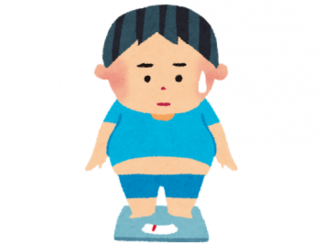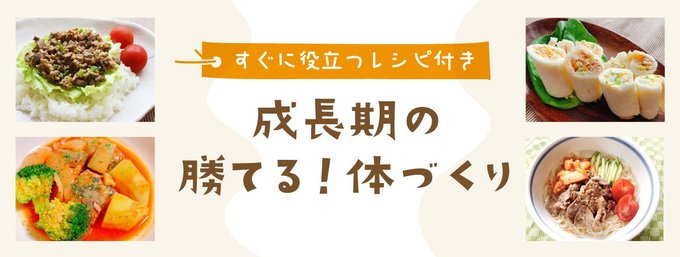皆さんは食事をするとき、どのようなことに気をつけていますか? 栄養バランスも大切ですが、よく噛んで食べることも大切です。食事を楽しむためではありません。全身の働きを向上させ、健康な体を維持するのに重要だからです。
しかし、子どもたちが好むのはカレーライスやラーメンなど、柔らかく、よく噛まなくてもよいメニューが多く、親もそういったものを食べさせることが増えてきました。
柔らかいものばかり食べて育つと、顎の骨の成長が遅れがちになります。結果、歯の成長とのバランスが崩れ、歯並びが悪くなります。同時に、硬いものを避けてよく噛むことをしないため、顎の関節や噛むための筋肉の機能も低下します。

「よく噛まない」問題は子どもだけに起こっているわけではありません。現代人は忙しい日々の中で、食事時間を短縮するため、かき込むように食べたり、柔らかく食べやすい料理やファストフード、ゼリー飲料に頼ることが多くなったりと、昔に比べて噛む回数が減っています。現代人の噛む回数、食事にかける時間は、いずれも昭和10年代の約半分になっているようです。
◇ ◇
よく噛むことにはどんなメリットがあるのでしょう。それを伝える標語に「ひみこのはがいーぜ(卑弥呼の歯がいーぜ)」があります。

【ひ】肥満予防
よく噛むことで自然と食べ方がゆっくりになり、満腹中枢を刺激して食べすぎを防ぎます。
【み】味覚の発達
食べ物の味は唾液の中に溶け出し、それを味蕾(みらい)という舌の組織が感知することによって脳に伝わります。よく噛むことで、食べ物の味がよく分かるようになります。
【こ】言葉の発音がはっきり
顎の骨や噛むための筋肉が鍛えられます。顎の発達は歯並びにも良い影響を与えます。噛み合わせが良くなることで、口を正しく開けられるようになり、発音が良くなります。
【の】脳の発達
噛むことで脳神経を刺激し、脳の働きを活発にします。
【は】歯の病気予防
よく噛むと唾液が分泌されます。唾液には歯周病菌やむし歯菌の繁殖を抑えたり、酸の中和、再石灰化を促したりと、歯の病気予防に重要な作用があります。抗菌作用で口の中をきれいにしてくれます。
【が】がん予防
唾液にはがんを抑制する作用もあるため、がん予防につながります。
【い】胃腸の快調
唾液に含まれる消化酵素アミラーゼの働きにより、体内での消化や吸収がアップし、胃にかかる負担が軽くなります。
【ぜ】全力投球
歯並びが良くなることで、嚙み合わせが良くなります。歯や顎が発達すると噛み締める力も強くなり、力が湧いてきます。
このように、よく噛むことはとても大切です。
次回は、噛む回数が減ると起きること、噛む回数を増やすコツなどをお伝えします。
◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士
富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。
日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。