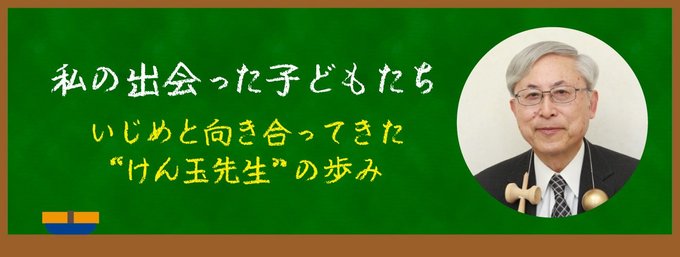「いじめを考える授業」から一週間後、ハルコの家を訪れ、母親と祖母に家族仲良く平和な家庭を築き上げていってほしいとお願いした。冬休みには、母親から電話をもらい、ハルコがどんどんよい方向に変わってきたこと、長年続いていた嫁姑の対立を解消できたことを知った。
3学期になってからのハルコは、学校でも見違えるほど優しくなった。クラスメイトとは分け隔てなく付き合い、言葉遣いも穏やかになった。教室の当番活動や係活動、「やさしさ運動」にも率先して取り組んだ。
ある日、次のような日記を書いてきた。
ミチコさんの詩「障がい者のほうが…」が載っていました。
うれしかったです。
これまでミチコさんをいじめた人が反省してくれるかもしれないからです。
でも、反対に腹を立てて仕返ししないか少し心配です。
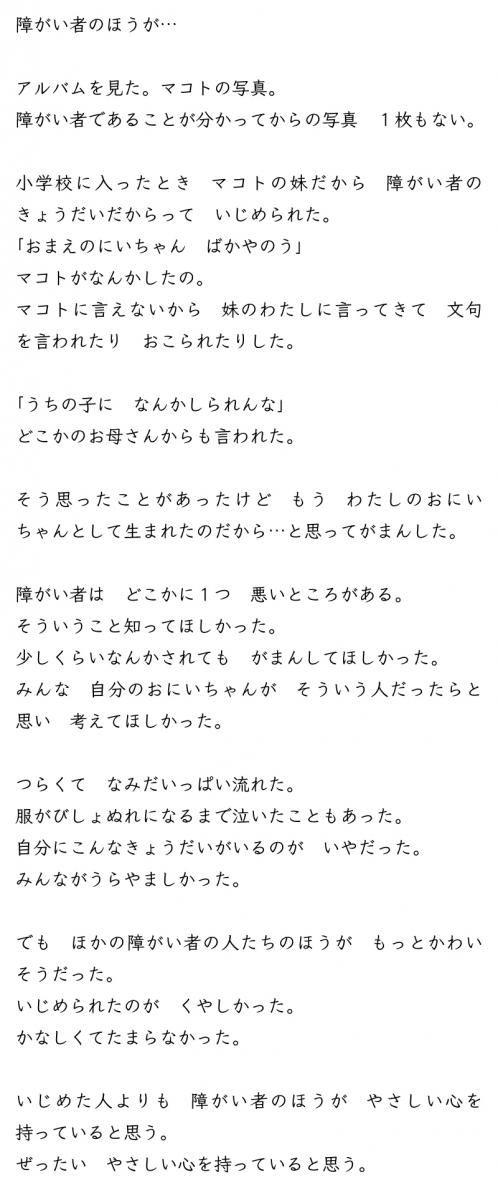
ハルコの日記をクラスの子どもたちに紹介すると「いじめを考える授業」を学校全体で行ってほしいという声が上がった。さっそく職員会議で提案し、各クラスで「いじめを考える授業」が実施され、全校児童による「いじめを考える集会」も開催されることになった。
集会ではミチコ本人が詩「障がい者のほうが…」を朗読した。
そのときのことをハルコは次のように日記に書き記した。
途中で泣きそうになったのを見て、心の中で(泣いちゃだめ、だめよ!)と言いました。ミチコさんは、涙をこらえながら朗読を続けました。
体育館がシーンと静まり返っていました。涙を流しながら聞いている人もいました。
私は(みんな、いじめられている人の気持ちがわかってきているんだ。これで本当にいじめがなくなればいいな)と思いました。
ミチコさんが読み終わったとき、ほっとしました。
教室に帰ってから「ミチコさん、がんばったね。ありがとう」と言いました。
3月31日、突然、私は東京に向かうことになった。県教委から派遣され、1年間、大学で教育相談について研修することになったためだ。
当日の夜、富山駅に着くと大勢の人の姿があった。5年3組の子どもたちと保護者の方々である。
私の姿を見つけると「先生!」と駆け寄ったのはハルコとツヨシだった。
「みんなからです」と渡された色紙には「忘れないで」と大書され、一人一人のメッセージが添えられていた。キャンディーの首飾りもかけてくれた。

夜行列車「急行能登」の発車時刻が迫った。
子どもたちはホームで、学級の愛唱歌である「森の熊さん」を合唱した。みんなの前で指揮をしているのはハルコだった。
列車が動き出すとツヨシを先頭に男子全員が走り出した。
ホームの最先端まで列車を追いかけ、手を振りながら見送ってくれた。(おわり)
◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。
現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。