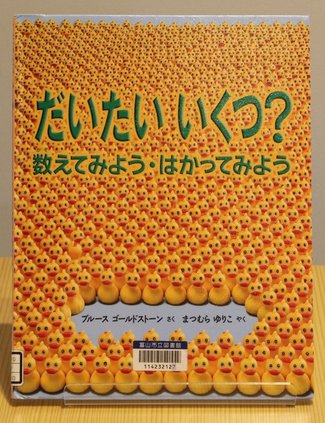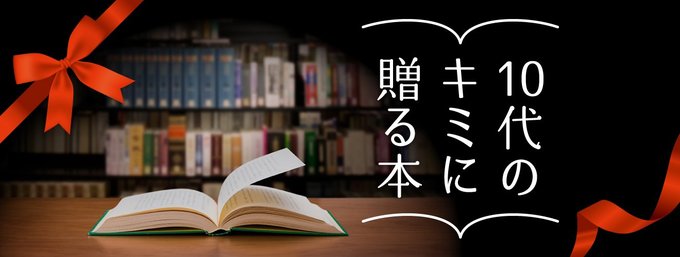―営んでおられる料理店「来人喜人 はぎ原」は、一軒家の日本家屋らしいたたずまいが印象的ですね。
昨年の7月にビルの1階にあった店から移転しました。一軒家になって随分店は大きくなったのですが、席数は20席と、前のお店とほとんど変えていません。私自身、これ以上、お客さんの数を増やしてしまうと、満足していたただくだけのおもてなしができないと思ったからなんです。

雰囲気も含めて提供
―移転は規模の拡大が目的ではないのですね。
以前のお店は2011年にオープンして約8年営業していました。お客さまに四季折々の素材を調理して提供しているうちに、「お料理をもっと楽しんでいただくためには、単に1品1品がおいしい、まずいだけでは足りない」と感じるようになったんです。雰囲気というか、場というか、空間というか、そういうもの全てをひっくるめて提供しなければいけないと思うようになっていきました。
―今のお店は、中庭や茶室もあり、風情のある造りの建物ですね。
そうやって場を提供しようと思うと、器の一つ一つも吟味しなければいけません。「器は料理の着物」という例えがあるように、素材や調理法、季節に合ったものを選べば、より料理が引き立ち、味わいも増すというものです。どんなにすてきな男性、女性でも、時と場をわきまえない服装では、せっかくの魅力が伝わらないのと一緒です。

経験積むほど器に関心
―今回ご紹介いただいた一冊「北大路魯山人(きたおおじ・ろさんじん)と須田菁華(すだ・せいか)」も器の作品集でした。
北大路魯山人は、書家であり、篆刻家であり、陶芸家であり、美食家でもあるという、とても一言では言い表せない芸術家です。今挙げた全てのジャンルを極めた存在といってもいいでしょう。その手から生み出される焼き物は、元来書家ということもあって絵付けの筆遣いが巧みで、面白味があります。その魯山人が憧れ、陶芸の世界を手ほどきしたのが、九谷焼の窯元であった初代の須田菁華です。紹介した本には4代までの作品が収められていますが、魯山人の焼き物も含めて、色絵の鉢、酒杯、徳利など、どの作品も見ていて楽しく、料理や盛り付けのイメージが沸いてきます。料理人として経験を積めば積むほど、器に関心が向いてしまいます。

―料理人の経験というお話でしたが、現在47歳。この道に入ってもう30年近いのでしょうか。
私は、高校卒業後にメッキ会社に勤めていたこともあって、料理の修業を始めたのは25歳になってからなんです。企業に就職して働くうちに自分が本当にやりたいことは何だったんだろうと思うようになりました。あれこれ考えるうちに、たどり着いたのが、料理人でした。
―ご実家は富山市内で仕出しも扱う鮮魚店でしたよね。てっきり、稼業を継ぐことがきっかけかと思っていました。
もちろん、実家が鮮魚店というのは、この道に進んだ大きなきっかけの一つです。ものごころつくか、つかない頃から稼業を手伝ってきました。店にいると、昨日魚を買ってくれたお客さんが翌日「おいしかったちゃ」と笑顔を見せてくれる、そんな幼いころの体験も影響していると思います。
人の2倍も3倍も
―とはいえ、和食の世界は10代で修業を始める人が大半です。
家族をはじめ、周りの人たちにけっこう反対されました。中学校を卒業後、この道に入る人たちも少なくありません。実際、修業が始まれば自分より年齢が若い人たちが先輩になるわけです。そこは悩みましたが、心を決め、知り合いの紹介で神戸市内のホテルにある和食店での修業がスタートしました。

―ドラマのようなお話ですね。
親方からは「他の人よりスタートがずっと遅いから、人の2倍、3倍も頑張らないと追いついけない」とことあるごとに言われました。もとより承知の上で入った世界です。実際、自分より年下の人は何人もいました。朝は誰よりも早く店に入り、夜は最後まで残って仕事をするといった日々が何年も続きました。本当にがむしゃらでしたね。その後、大阪の店に移り、トータルで10年くらいの修業期間を経て、2007年に富山に戻りました。
―富山ですぐにお店を開いたのですか。
まずは、富山の飲食店の状況を把握したり、仕入れ先を開拓する必要もあったりして、市内のホテルで働きながら開店準備を進めました。独立して店を開いたのは2011年になります。
―では、ことしは独立10年の節目の年になるんですね。
そうですね。ただ、この世界は経験を積めば積むほど、もっと勉強しなくてはいけないと感じるようになりました。料理はもちろん、器や書など、日本文化そのものについて理解を深めないとの思いが強まっています。茶道も習っていますが、まだまだです。そういう意味でやはり読書は欠かせません。料理の技術だけではなく、自分自身をもっと深めていきたいですね。