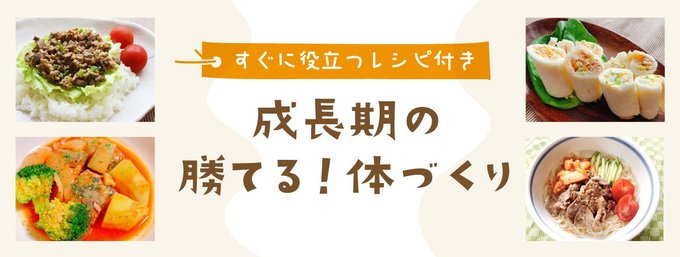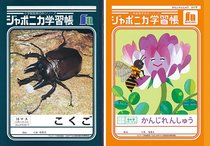ことしの冬至は12月21日、もうすぐですね。
冬至とは、一年で最も夜が長くなる日のこといいます。別名は「一陽来復(いちようらいふく)の日」。冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力がよみがえっていくという前向きな意味合いを含んでいます。
冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼び込めると言われています。にんじん、だいこん、れんこん、うどん、ぎんなん、きんかん……など「ん」のつくものを「運盛り」と呼び、縁起を担いできました。もちろん縁起をかつぐだけでなく、これらを食べることで栄養を取り、無病息災を願いながら寒い冬を乗りきる知恵とされています。

「運盛り」と言われる冬至の七種(写真提供:PIXTA)
現代では、この7種の中でも特にかぼちゃ(南京)を食べる風習が根付いています。
かぼちゃはビタミンAやカロテンが豊富なので、風邪予防になります。旬は夏ですが長期保存ができるため、昔の人は野菜が少なくなる冬に栄養たっぷりのかぼちゃを食べることで、栄養を補っていたんですね。
せっかくの季節の行事ですから、風習に込められた昔の人の知恵を学びながら、家族で楽しんでください。
次回は、冬至に食べたいかぼちゃ料理を紹介いたします。
◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士
富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。
日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。