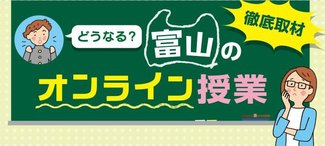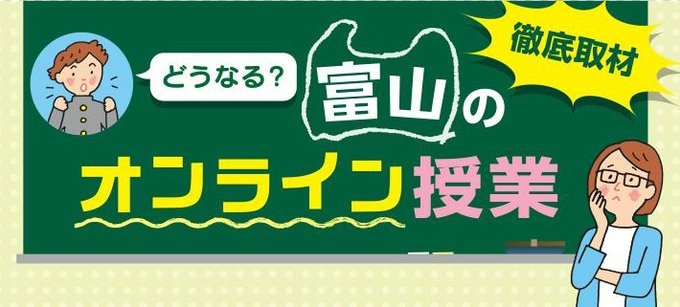
小中学校で進む「オンライン授業」(双方向)について、県内の15市町村教委に対応を聞いたところ、13教委が実施に向けて準備をしていることが分かりました。中には「8月6日に初開催する」(朝日町)や中学3年生を対象に「テスト済」(高岡市)、「夏休みに運用テストを計画」(滑川市)と先進的な教委もありました。授業の際に必要なタブレット端末は、全教委が年度末までに児童生徒1人に1台を配備する計画です。配備に先立ち、教員のスキルを高める研修会を開き、オンラインで必要な指導力のアップを図ります。
⇒朝日町で8月6日行われた一斉オンライン授業の様子はこちら
⇒1人1台端末時代、授業はどう変わる?専門家インタビューはこちら
オンライン授業に積極的に取り組んでいるのが朝日町です。8月6日は、さみさと小(全285人)、あさひ野小(同114人)、朝日中(同217人)の児童生徒と各学校をオンラインで結び、クラス単位で授業を受けます。5月にさみさと小で行った試験運用では、児童の93%が「楽しかった」「またやりたい」と前向きな回答をしました。一方で、接続に時間がかかったり、途中で画面が止まったりする課題もあったそうです。朝日町教委の小杉嘉博事務局長は「9月中にいつでもオンライン授業ができる体制を整え、コロナ感染や災害などに備えたい」としています。

高岡市は5月、市内12中学校(義務教育学校含む)の中学3年生約1300人がオンライン環境をテストしました。授業ではなく、クラスミーティングという形で、教員と生徒がやりとりをし、表情や声などを確認しました。担当者は「一定のノウハウができた。課題を洗い出し、教員の技術も高めていきたい」としています。中3は受験生でもあるため、対応を急いだそうです。滑川市も夏休み期間に中3生を対象に試験運用する予定です。
国の「GIGAスクール構想」では、「児童生徒1人1台の端末と、高速大容量の通信ネットワーク整備」を早急に進める方針を打ち出しています。県内では、立山町が全児童生徒分の1910台をすでに配備し、氷見市や舟橋村も一部配備しています。各教委は端末の配備に合わせ、学校内や各家庭内の無線LAN「Wi-Fi」などの整備・支援を進める方針。新型コロナの第2、第3波に備え、いつでも「オンライン授業」に切り替える体制を目指します。

課題となるのが、オンライン授業をする側の教員のスキルアップです。全教委が県教委や各市町村の教育センターなどと連携し、教員対象の研修会やセミナーを開く予定です。ICTマイスターや外部の支援員の協力も得て、対面式ではなく、画面を通じた授業に必要な指導技術やノウハウを学びます。
このほか、オンライン授業について、富山大付属小は、実施に向け準備を始め、富山大付属中は5月の休校期間中に全学年で実施済。片山学園初等科、片山学園中もすでにオンライン授業を行っており、いつでも切り替えができる環境を整備しています。
いつ来るか分からない新型コロナの感染拡大に備えることはもちろん、現代社会を生き抜く上でデジタル技術の習得は不可欠です。学校現場や家庭が力を合わせ、「子どもファースト」にデジタル環境への対応を進めていく必要がありそうです。