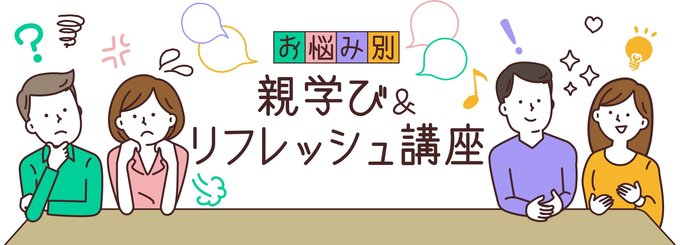富山市内の公民館では、地区にある学校のPTA役員や教員、地域住民らが集まる会合で、親学び講座が開かれました。各グループには、「子育て真っ最中」という人もいれば、「子育てはほぼ終わった」という人、「日々、孫の面倒をみている」という人など、さまざまな年代が混ざります。
テーマは「理解してくれる叱り方」。講師を務める親学び推進リーダーの柴垣幸正さんオリジナルのテーマです。
柴垣さん:最近、子どもに対して叱ったことを思い出して、1つ書いてみてください。
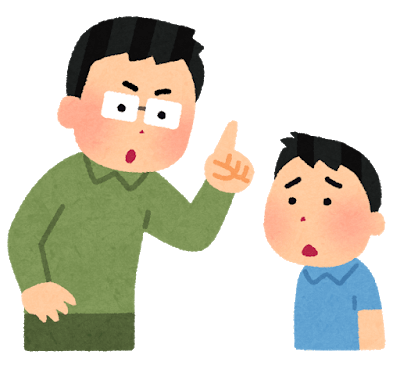
Q. 叱った後、子どもはどんな様子でしたか?
Q. 素直に聞いてくれたと感じた方は、叱り方の何が良かったからだと思いますか?
一方、反省した様子がなかった、聞いてもらえなかったと感じた方は、どうしたらよかったと思いますか?
☆ ☆
Aさん(ママ):毎日「早く宿題して!」って怒ってますね。なのに子どもはSNSに夢中で、全然言うことを聞かず、だらだらと遅くまで起きています。
Bさん(パパ):男親の言うことは特に、全然聞きませんね。
Cさん(地域住民):私はもう子育ては終わっているのですが、先日、近所でボール遊びをしていた小学校低学年の子どもが車道に飛び出したのを見掛け、思わず「危ない!」と叱りました。
一人は「はい、すみません」と謝りましたが、残りの3人は素知らぬ顔。その様子を見て、叱られ慣れている子と、そうじゃない子がいるなと感じました。その後、もしかしたら「すみません」と言えた子は、近くにおばあちゃんやおじいちゃんが住んでいるのかなとも思いました。
Dさん(教員):確かに、最近は「ありがとう」や「ごめんなさい」を言えない子が多いように感じます。家族の中でも、例えば家の手伝いが終わった後などに「ありがとう、またやってね」と言い合うことで、自然と言えるようになると思うのですが。
Eさん(パパ):そういえば、嫁にあまり「ありがとう」とは言ってないかも・・・。
Fさん(地域住民):今は、そういうことが大事だと分かるけれど、子育て中は分からなかったし、知る機会がなかったですね。家庭だけじゃなく、叱ってくれる近所のおじちゃん、おばちゃんの存在が、子どもの成長に必要だと感じています。
Gさん(地域住民):確かに、いろんな大人が声を掛けてくれる町っていいですよ。

Hさん(パパ):私はゲームのし過ぎをよく怒ってます。最近のゲームは内容が物語っぽくなってゲーム自体が長いんですよ。
Iさん(パパ):以前は私が、携帯でゲームをしていたんです。ある時、子どもに「お父さんばっかり」と言われて、「確かにそうだな」と思ってゲームをやめました。それで子どもたちに「あなたたちどうする?」って言いました。
子どもたちは、時間のルールを決めてゲームをしています。今では1分でも約束の時間が過ぎたら、「何時かな?守るための約束だよね」と言います。それでもやめなかったら、強制終了です。
Jさん(パパ):うちの場合は、やること(宿題など)を先にやったら、やりたいこと(ゲームなど)ができなくなるのが嫌らしく、遊んでから宿題をしてます。そのほうが本人としては納得できるようで、ちゃんとやることはやってますね。
☆ ☆
柴垣さん:意見を交わす中で、「共感してもらえてうれしかった」とか「こんなやり方もあるんだ」など、いろんなことを感じられたと思います。正解は一つではありません。参考にしたいと思ったことがあれば、家に帰って試してみてください。その状況を冷静に見て、うまくいけば、それが正解なのかもしれません。
【参加者の感想】
(ママ)親学び講座の参加は3回目。いろんな年代の人たちが参加する講座は初めてでした。年齢の上の皆さんは、やっぱり価値観、考え方が違うなと思うこともありましたが、いろんな経験を基に子どもたちを見守ってくださっていることが分かり、安心感を得ました。いろんな意見ももらいましたが、親ではないので素直に聞くことができました。
(地域住民)私たちが子育てした時とは、時代が違うなと思いました。叱り方も全然違って、今の親たちは優しいですね。きっと子どもたちはおじいちゃん、おばあちゃんと交わることで、より広い視野を持てるようになると思います。
親学び講座の詳細は「富山県ホームページ『子育てネッ!とやま』」へ
http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/hp/oya_kouza01.html