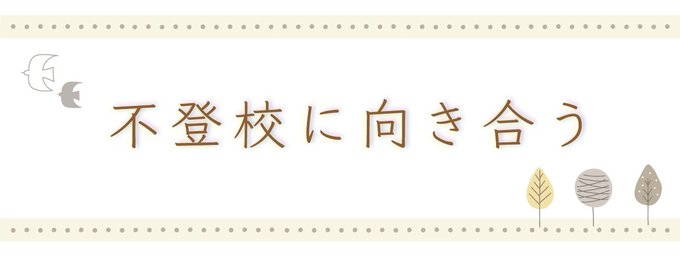不登校の子どもたちの学びの場として注目を集めているフリースクール。県内では35年前に富山YMCAが先駆けて開設しています。長年、フリースクールの運営に携わってきた富山YMCA総主事の上村香野子さんに、不登校の子どもと親たちを取り巻く環境の変化と、多様な学びの場から広がる進路について聞きました。

35年前 高校生年代向けからスタート
―フリースクール開講の経緯を教えてください。
富山YMCAが1989年、初めて開講したフリースクールは、高校生の年代が対象でした。高校を中退したり休学したりした人たちが、大学や短大を受験するには大学入学資格検定(通称大検、現在は高等学校卒業程度認定試験)に合格する必要があります。その受験に向けた予備校としてスタートしました。
中学生や小学生向けのフリースクールを作ったのは25年ほど前。本人のペースでゆっくりと勉強するコース、高校入試に向けた準備コース、勉強よりも友達との遊びを重視したコースなどがあります。子どもたちが必要とする場を設けるうちに、コースが増えていきました。
問い合わせ多数 通い続けられるのはそのうちの一部
―現在、フリースクールに通っているのは?
高校生10人、中学生15人、小学生10人がフリースクールに登録し、それぞれのペースで通っています。不登校は、低年齢化が進んでいます。理由はさまざまですが、学校にいると不安や息苦しさを感じ休んでいる場合が多いようです。
日々、多くの親御さんからフリースクールについて問い合わせを受けています。不登校になると、ほとんどの子どもは自宅にこもり、勉強よりは、ゲームをしたりユーチューブを見たり。子どもの将来を考え、何とか学校に行ってほしい、勉強をしてほしいという気持ちはよく分かります。ただ実際に通い続けられる子どもは、その中のほんの一部です。学校と同じで、子どもたち自身が「行ってみよう」と思わなければ、足は向きませんから。
子どもが自ら動くのを待つ
ーでは、大人たちはどうしたらいいのでしょうか。
私たち大人は、つい自分の価値観に子どもを合わせようとし、子どもに「普通」を求めがちです。「普通」とは「多数派」であり、多数派にいるほうが生きやすいと考えるからです。しかし子どもたちはそれぞれです。それぞれに性格や個性があり、どうしても受け入れられない、なじむことができない環境もあります。家にいる方が落ち着いて学べることもあります。
子どもが学校に行かないのは、集団生活に疲れている場合が多いです。そのような子どもたちは休みを必要としています。しっかり休んで充電期間が終われば、子どもたちは意外に簡単に動き出すものです。親御さんたちには、この期間をゆったりと構えて、同じ悩みを持つ人たちとつながる場を見つけたりし、自分の時間を大切にして、何とか乗り切ってもらいたいと思っています。
次回はインタビュー後半、不登校の後の学び方と進路について聞きます。