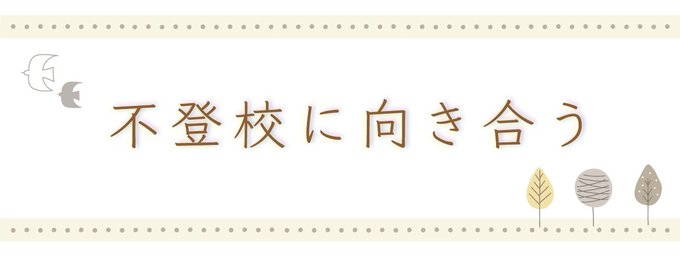県内の小中学校では、学校に行きづらいと感じている子どもたちが、教室以外で安心して過ごせる居場所づくりを進めています。かつて、その役割を保健室が担っていた時代もありましたが、現在は空き教室を利用して専用の部屋を設けています。
富山市 小学校8校、中学校9校に「校内サポートルーム」
富山市教育委員会では24年度から、「校内サポートルーム」を小学校8校と中学校9校に設置しました。市教委は「子どもたちに思い思いの時間を過ごしてもらい、心のエネルギーを蓄えてもらうのがねらい」と言います。設置校には指導員を配置し、開設時間や運用方法は各校に任せています。
利用数は17校合わせて9月が98人、10月が123人、11月が117人、12月は113人。「不登校の子どもが、『サポートルームなら』と学校に通うようになったケースや、サポートルームとクラスを行き来することで早退が減ったケースもある」と効果を話します。
アットホームな雰囲気で自由に過ごす
設置校の一つ、堀川中学校を訪ねました。扉を開けると、折り紙作品で飾られた仕切り壁があり、廊下から中が見えないようになっています。さらに奥へと進むと、マット敷きの広いスペースにソファとテーブル、ハンギングチェアが置かれていました。


「リラックスして過ごしてほしいので、アットホームな雰囲気づくりを心掛けています」と話すのは校内サポートルーム指導員の須貝美由紀さん。そのため生徒たちへの呼び掛けも「○○ちゃん」、生徒たちも「スー先生」と親しみを込めて呼び合います。
本年度は5人の生徒が自分のリズムで登校し、ジグソーパズルや折り紙など好きな活動をしたり、須貝さんや部屋の生徒らでボードゲームや卓球、風船バレーなど、さまざまなレクリエーションを楽しんだりしています。
心が満ちてくると次のステップへ
同校には、教室以外の居場所として「相談室」もあります。机がずらりと並びミニ教室のような雰囲気で、こちらはカウンセリング相談員の教員が担当しています。現在は20人ほどが利用し、一部の生徒は、ここを起点に教室と相談室を行き来しながら自分のペースで授業を受けるなどしています。

須貝さんによると、サポートルームを利用している生徒たちも、交流を重ねるうちに、より多くの生徒が集う相談室に移ったり、教室に行ってみようと頑張る姿が見られたりするようになるといいます。「子どもたちは、心が満たんになると前に動き出します。まずは生徒たちの心のよりどころとなり、そして次のステップにつながるようサポートしています」と言います。
悩んだ経験が人生を後押しする
長年カウンセリング指導員として不登校の生徒たちと関わってきた同校の古木陽子教頭は「子どもたちの中には、人との関わりで傷ついているケースもあります。でも、サポートルームや相談室で過ごすうちに、『人と関わると、嫌なこともあるけれど楽しいこともある』ということを知り、少しずつ変わっていきます。悩んだり立ち止まったりする時間も、それぞれの子どもたちの人生にとって大切な時間であり、その間に経験したことが、きっと社会に出てからも生きてくるのだと思います」と話しています。
次回は長年、不登校の子どもたちとその親たちの声を聞いてきた富山YMCA総主事、上村香野子さんにインタビューします。