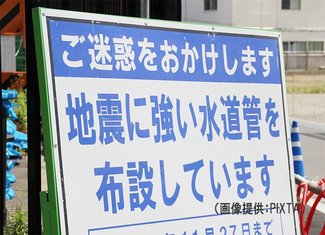災害時に命をつなぐ「水」。能登半島地震でもペットボトルの飲料水が被災地に届けられた一方、断水でトイレなどに使う生活用水が不足した。そんな中、注目されるのが「防災井戸」だ。
東日本大震災でも98%稼働
防災井戸は災害時、地下深くから水をくみ上げ、飲用ではないもののトイレなどの生活用水として使用する。全国の井戸工事業者でつくる全国さく

中川上市町長に防災井戸でくみ上げた水を見せる土肥社長(右)
災害対策の一つとして、防災井戸を設置する自治体は増加傾向だ。上市町では2023年12月、防災井戸があさひの郷公園に設置された。給排水配管設備工事の土肥鉄工(上市町旭町)が、
残り1183文字(全文:1547文字)