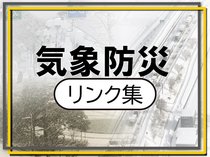魚津水族館に隣接する土産店「真珠コーナー」(魚津市三ケ)は土産の枠に捉われない品ぞろえを誇り、全国からファンがやって来る。1メートル超のカメの標本、宝石・原石、化石、起毛加工(フロッキー)の動物マスコットなど、多種多様な物・物・物が店内を埋め尽くす。いったい、なんの店なの?
東京、四国、九州からも
魚津水族館は、設立100年を超え、現存する国内最古の水族館。現在の建物は3代目になる。真珠コーナーは2代目水族館にオープンし、現在は「レストハウス」と書かれた建物の1階にある。

入るやいなや、商品の多さに圧倒された。ガラスの風鈴、貝殻、鉱物、ガラス細工の動物、恐竜の歯の化石、自社生産している魚津市のキャラクター「ミラたん」のぬいぐるみ…。見上げれば、ヒトデやハリセンボンのはく製も。雑多極まりない。
現在、店を担うのは渡辺良太郎さん(50)。「東京から来る方が多いですね。ほかにも四国、九州…、山口県から車で来た方もおられました」。SNSでこの店を知ったという人が多いそう。鉱物ファンの男性、昭和・平成レトロ好きの女性など性別を問わず、年齢層も幅広い。多くの県民の知らぬ間に(多分…)、全国区の人気店となっていた。
ここにしかない
人気の秘密は、ここにしかない激レア商品という。ところが、「これらの多くは元々売れ残りだったんですよ」と良太郎さんは語る。
今の真珠コーナーをつくり上げたのは、良太郎さんの父・哲(てつ)さん(故人)だ。哲さんは世界中を飛び回り、多種多様な商品を仕入れた。自然が好きで「海のロマンを売る店」「水のない水族館」を目指した。その流れで、ハリセンボンやヒトデのはく製、化石などが増えていった。

良太郎さんは「父(哲さん)はもうけが出ても『余計なお金を持つことはストレスになる』とすぐ新たな商品を仕入れてしまう」と振り返る。「売れればいいけど、売れなかったからこんなに商品が増えちゃった」
懐かしく新しい
当初は売れ残りの集まりだったが、歳月の流れが価値を変えた。商品の生産がいつの間にか終了し、どこにも売っていない激レア商品となったのだ。昔を知る人には「懐かしい」、若い人には「新しい」と再ブレークを果たす。

例えば、フロッキー(起毛加工)のカバのマスコット。コロナ禍の最中、SNSのX(旧ツイッター)にアップされた写真が注目され、知る人ぞ知る人気商品となった。

フロッキーのマスコットは、昭和の土産店でよく売られており、哲さんが好んで仕入れた。令和になって「ここにしかない」「東京近辺では見つからない」と次々と人がやって来るように。旧型のカバは売り切れたが、その人気ぶりを見て新たにフロッキーのマスコットを作ってくれる業者を見つけだし、現在は新たなカバを仕入れている。

なぜ「真珠コーナー」
そもそも、なぜ真珠コーナーという名前になったのか。