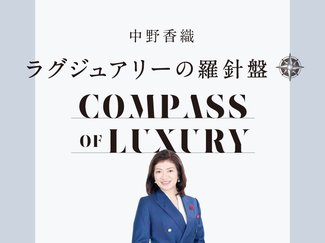「ママ振」という言葉を知りました。母親の振袖を娘が着用すること。ではそのきものを息子が継承したいと思ったらどうすればよいのでしょう?
「ママ振スーツ」を創ればよいではないか。
妙案を思いついたのは、モデルとして世界の一流ブランドのショーで活躍する武内秀龍さんです。実家は富山市の呉服専門店、牛島屋さんです。1848年創業という老舗ですが、現在、代表取締役社長を務める武内孝憲さんは、息子さんの案をさらに発展させ、振袖ばかりか黒留袖もスーツやドレスといった洋装に作り替えるプロジェクトを始めました。チャペル婚や洋式の宴が主流になってきたことで、せっかくの黒留袖も出番が少なくなっていることが背景にあります。
「衣服のもつドラマや物語の続きをデザインするというコンセプトです」と武内社長は語ります。「手持ちのきものを処分したいという相談を受けるようになりました。そこには、換金したいという要素よりも、きものは簡単に捨てられないという事情があります。選んだ時、着た時、着せた時の思い出やドラマが色濃いからだと思います」。人の思いや家族の物語を継承するという考え方で、単なるアップサイクルとは意味が異なりますね。
具体的にきものを洋装に作り替えるにあたり、パートナーに選んだのは、高松太一郎さんでした。ロンドンのセントラル・セント・マーチンズで修業し、プラダ、ドルチェ&ガッバーナ、ディオールで働いてきたキャリアをもつクチュールデザイナー&テーラーです。福岡市出身ですが、富山に移住し、この秋、富山市にアトリエを備えた店舗を開くべく準備中です。高松さんがディオールのアーカイブで服を護っていくための構造を学んでいたことが決め手となって、協力関係が始まりました。振袖を作り替えたスーツを秀龍さんが着用する写真を見せていただきましたが、男性服も自由に可能性を広げている現代に波長の合うかっこよさがあります。
高松さんのアトリエも訪問しました。ディオールの造形を思わせる立体的な白いトワルが立ち並びます。

一方、巨大な一枚板の黒松のテーブルが目を引きます。その上にダイナミックに飾られるのは、白い沙羅の花を主役にしたフラワーアート。実は沙羅の花は一日しか咲いていません。沙羅の花々がアトリエに咲き乱れる風景は、この日一日だけの超貴重なものだったのです。ご近所に住み、装花を手掛ける廣瀬亜紀さんの作品で、早朝、氷見市まで足をのばして摘んできた沙羅が飾られていたのでした。すべては客人(この日は私でしたが)のおもてなしのために。
沙羅の花に彩られた光景は一生覚えているでしょう。思いや記憶を護っていくクリエイターの感性と力量は、この演出だけで十分に伝わりました。

老舗の伝統と新しい技術の融合による、現代的感覚のプロジェクト。思いや記憶を大切にする、多領域にわたるプロフェッショナルな人たちのローカルコミュニティ。地域発の新しいラグジュアリーの萌芽を見る思いがします。あ、そもそも留袖を持たない世代としては「ママドレス・スーツ」も作れるとよいな(息子には辞退されるか)。