私にとって、ある日突然訪れた戦争は、決して突然訪れたわけではなかった。悲鳴が聞こえるまで気づかなかった。
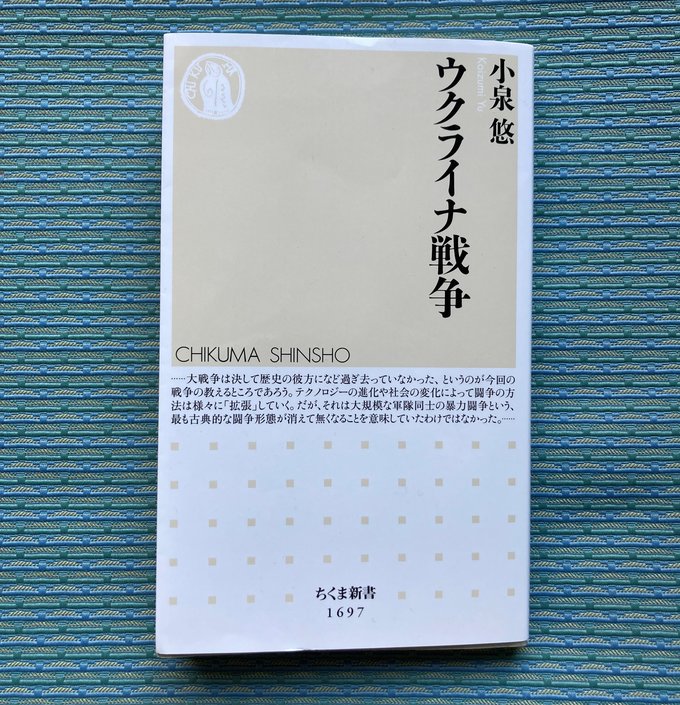
現在進行形で続いている事態に《先行きの不透明感ばかりが募る》とあとがきで著者が記すこととは裏腹に、2021年春から開戦前夜、戦争中に起きた出来事の数々を、極めて精緻に分析する。ここに書かれてあることをすべて知っている方は、学術的な研究を何年も積み重ねてきた方を除いて、そう多くはないはずだ。開戦してから、ニュースが今日に至るまであれほどあふれかえっているにも関わらず、ロシアとウクライナの歴史を丁寧に解説する番組は、驚くほど少ない。もちろん今日起きた悲劇を知ることも大切だが、なぜ悲劇が起きたのか、どうしたら悲劇は起きなかったのか、一市民として出来ることは何なのか。考えを深めるためにも、歴史を踏まえることは、最低限の条件ではないか。
特に印象に残ったのは、ゼレンシキー大統領(表記は本書に沿う)のパフォーマンスの巧みさである。《つまり、有事のリーダーはこうあってほしいと皆が思う通りに振る舞ってみせた》有名な話だが、ゼレンシキー大統領は元々俳優で、政治的キャリアはあまりない。しかし長年の政治的キャリアがあるプーチン大統領のほうがパフォーマンスがうまいと思うような人間は、世界中にほとんどいない状況を、短い期間のうちに、主には演技力とSNSでの凄まじい勢いの動画拡散によって、作り上げてみせた。凄いことだけれども、同時に、恐ろしい。ゼレンシキー大統領にとっての舞台は戦場であり、観客である私たちは、演技を現実として受け取るほかにない。そしてもう一つ見過ごせないことは、これからの戦争でも間違いなく参考にされる事例であるということだ。一国の首相や大統領が、政治的思想の中身よりも、演技力によって力を持つかもしれない、残酷なオーディションの幕開けである。










