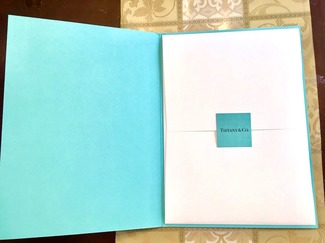日本の地方都市においては、どこに行っても見たことのある光景が広がります。ユニクロ、ニトリ、ドン・キホーテ、サイゼリヤ、コンビニ、回転寿司など、生活の必要を低価格で満たすサービスを提供するチェーン店が林立します。
1990年代から続くデフレ、低賃金、コスパ重視の経済が30年かけてこのような画一的な風景を作りました。15%ほどの利益を確保しつつ低価格競争を続けるというビジネスモデルが強さを発揮し、既視感のあるプレハブ店舗が日本を覆っています。誤解を恐れずに言えば、機能に徹した低コストのサービスに皆が落ち着き、これで足りると自らを納得させている空気感が漂います。しかし、人口減も響き、このデフレスパイラルからの脱却を模索しなくては立ちいかない時期に来ています。
じゃあ付加価値の高いラグジュアリー産業をつくろうということで富裕層顧客を対象とした高級品ビジネスが注目されているわけですが、それも大雑把すぎるのです。
たしかに、1990年からの30年間は、ヨーロッパの企業を主要プレイヤーとするラグジュアリー産業が発達しました。粗利率68%というビジネスは、機能を超えた文化的価値や感情的価値を付加価値として訴求することで成功しています。世界市場の規模は、1996年の760億ユーロに対し、2019年には2810億ユーロ。コロナ禍でも衰えず、2022年はコロナ前の2019年に比べて8〜10%の伸びを示すと報告されています。ルイ・ヴィトンやディオールを率いるLVMHグループの会長、ベルナール・アルノーは世界一の長者になりました。たしかに目指したい一つの方向として研究の価値はあります。
ただし、この産業は富の格差を背景として成り立ち、格差の拡大を後押しするという性格をもっています。格差の拡大が限界超えしたときの危険を考慮すると、このビジネスも将来安泰というわけではないのです。ラグジュアリー産業の動向に明るいコンサルタント会社「ベイン&カンパニー」が昨年秋の年次会議の報告で、経営者たちが抱く不安としてこんな比喩を紹介しました。「航海中のルートに氷山があるにもかかわらず、我々はそれを知らないがごとくタイタニック号の船内で豪華なパーティーを繰り広げているのではないか?」。
その比喩に便乗するならば、2月に公開される映画『逆転のトライアングル』は、予言的です。モデル、インフルエンサー、ロシアの新興財閥、イギリスの武器商人などの富裕層を乗せた豪華客船が難破し、生存者は無人島に漂着しますが、そこで頂点に立つのは、サバイバル能力に長けた地味なトイレ清掃員の女性だった……という資本主義の価値大逆転のブラックなストーリーなのです。現代の格差社会の愚かさと危険に警鐘を鳴らすようでもあります。
ラグジュアリーと一口に言っても、目指すべきはヨーロッパ型ラグジュアリー産業の方向ではなく、私たちが古くからなじんできた独自の思想や土地の固有性に支えられた、本来の豊かさを再評価する方向です。あ、今やそれが各地に根を下ろす安売り量販店であったりするのでしょうか?
(ゼロニイ2023年2月号に掲載)