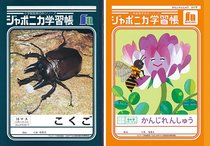Q まず「学校に行きたくない」「日中イライラする」「授業に集中できない」「自分に自信が持てない」…こういった子どもの状態をどのように考えたらよいでしょうか。
A(藤村コーディネーター) 「学校に行きたくない」という登校回避感情は、子どものメンタルの問題と捉えられることが多いかもしれませんね。もちろん心理的な問題でもあるのですが、実は睡眠習慣や生活習慣の乱れが原因になっている場合もあります。生活のリズムを立て直してあげることで、日中の疲労感やネガティブな感情が改善する可能性があります。
Q 寝不足でパワーが足りない状態でしょうか。
A 睡眠不足で授業に集中できないと、勉強が分からなくなったり、やる気が出ず『みんなにできることが自分にはできない』と自己肯定感が低くなったりします。大人だって、目覚めの気分が良くないと、ネガティブな気持ちで1日が始まりますよね。子どもも学校での活動が面倒だと感じたり、嫌になったりすることがあります。ポジティブに1日をスタートさせてあげましょう。
では、具体的にどうしたらよいか、7つのポイントについて藤村コーディネーターに解説していただきましょう。
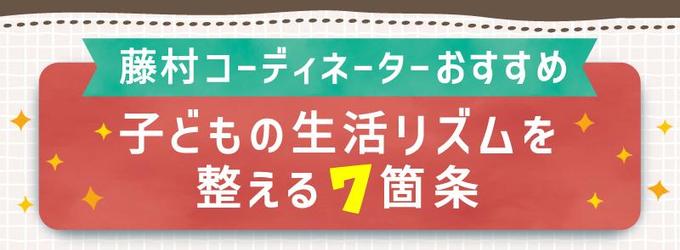

以前は、就寝時刻を中心に睡眠習慣を考えていたため「早寝・早起き」と言われていましたが、最近は起床時刻を軸に捉えるようになっています。まずは「早起き」を意識しましょう。
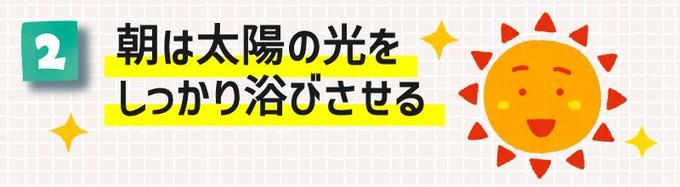
朝起きたら、太陽の光をしっかりと浴びて、体内時計のスイッチを入れましょう。このときスイッチがしっかり入ると、約14時間後に自然な眠気が訪れると言われています。
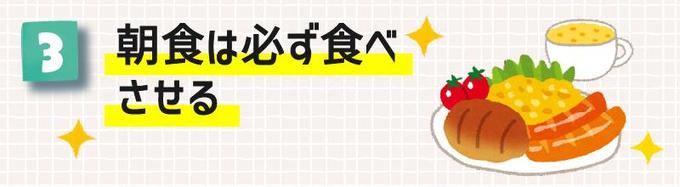
朝食はマスト。朝は水分やエネルギーが不足しており、食べないと1日の活動に必要なエネルギーや栄養を得ることができません。
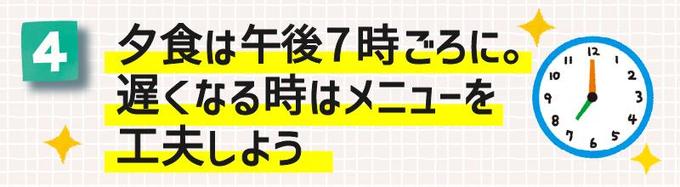
小学校高学年の児童であれば、遅くとも午後10時には布団に入りたいので、夕食の時刻は7時ごろが理想です。大人の時間に子どもが合わせている、ということはありませんか? もし夕食が遅くなる場合は宿題や翌日の準備などを先に済ませておくように習慣付けましょう。塾や習い事で遅くなるようなら、先に食べてしまうのもおすすめです。
夕食が遅いと、就寝までの時間も短くなってしまうため、高カロリーのおかずばかりにならないよう注意が必要です。と言っても、油抜きではありません。油を使う料理は1品とし、カロリーより栄養をしっかり取るよう意識します。大豆製品、魚料理、野菜を積極的に活用したいですね。おなかが空きすぎて、揚げ物や肉をたくさん食べると、消化に時間がかかります。逆流性食道炎や肥満の予防にも気を配ってあげましょう。
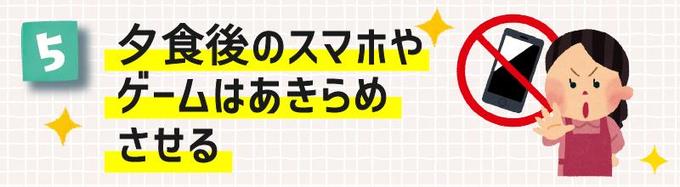
日中、活動的に過ごして少し疲労感をおぼえるぐらいで夜を迎えると、自然に眠くなってきます。このタイミングで、ブルーライトを浴びると、体内時計が後ろに1~2時間ずれてしまいます。寝たくても寝られない状態です。また、寝る直前までゲームやスマホを触っていると、興奮状態が収まらず、交感神経が優位になっているため、なかなか寝付けなくなります。入眠準備の段階から、スマホやゲームはあきらめさせてください。その際、心身の成長に影響があることを丁寧に説明しましょう。
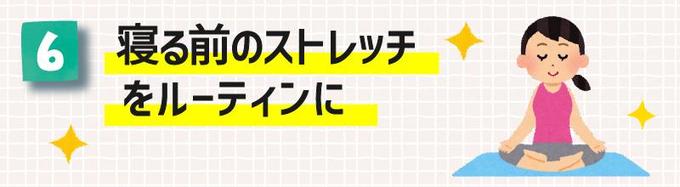
寝る前のストレッチも効果的です。毎晩のルーティンにするといいですよ。(富山大学『睡眠導入用ストレッチ』YouTube動画⇒上半身ver. 下半身ver. 全身ver.)
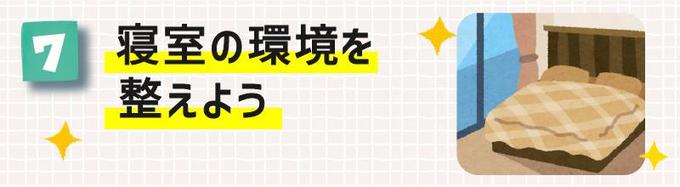
温度、湿度、明るさ、騒音などが睡眠に影響を与えます。部屋を真っ暗にして眠るのが良いとされています。カーテンを少し開けておくことで、朝日が部屋に差し込み自然な目覚めにつながります。大人がテレビや話し声で子どもの入眠を妨げていないか、注意してください。子どもには「もう寝なさい」と言っておきながら、大人はテレビやスマホを楽しそうに見ている…なんてことはありませんか?
朝の生活習慣から変えよう
藤村コーディネーターは7箇条のうち「まずは朝の生活習慣から変えてみて」とアドバイスします。「早起きして、体内時計のスイッチをしっかり入れ、朝食を取る。子どもがエネルギーを十分に補給し、気分的に元気な状態で登校できるようにしてあげたいですね」。
親子で一緒に生活のリズムを立て直し、元気に2学期を迎えましょう!
※もし、夜、睡眠時間がしっかり取れているにもかかわらず、日中眠くなったり授業中に居眠りしてしまう場合は、病気が影響している可能性があります。かかりつけの小児科医に相談してください。
内閣府「自殺対策白書」(2015年版)によると、18歳以下の自殺者が1年間で最も多いのは夏休み明けです。親としてはそういった取り返しのつかない事態に陥らないように、普段から子どもが毎日を元気に過ごせるよう生活面でアシストしてあげたいですね。