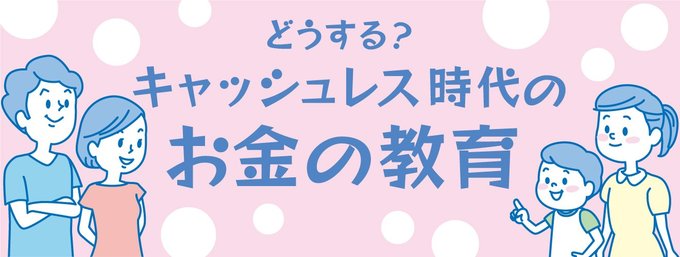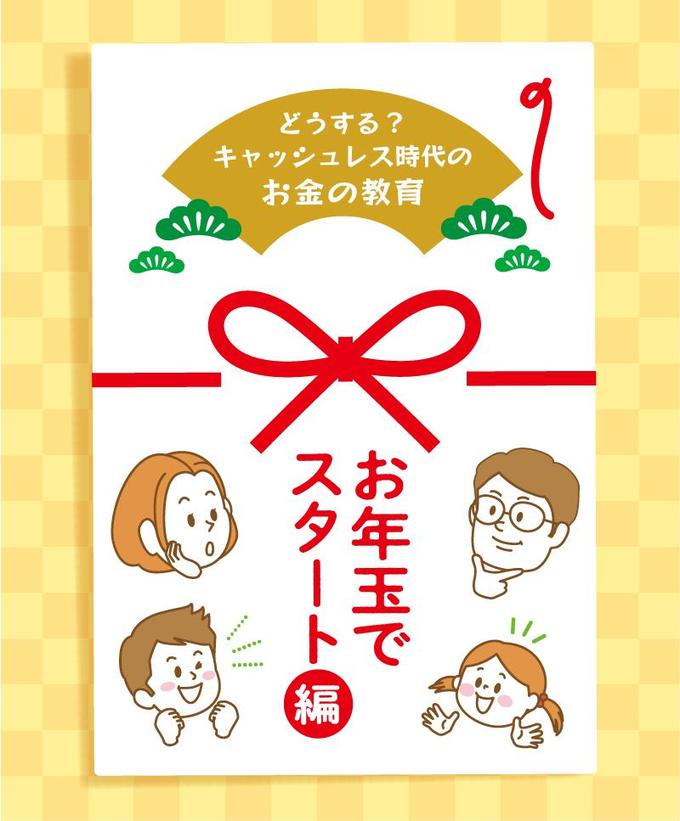
子どもが一度に大きな額を手にするお年玉。親が預かって教育費に充てるという方法もありますが、渡し方次第では、キャッシュレス時代に必要なお金の知識や使い方を教えるチャンスにもなります。ポイントは、子どもに主体的に関わらせること。ファイナンシャルプランナー(FP)の丹羽誠さん(富山市)に、お年玉から始めるお金の教育5ステップを提案してもらいました。


子どもに渡すと落としたり、使い込んだりしないか心配し、親が管理する家庭もありますが、「親のお金ではなく、子どもの代わりに預かっている」という認識を持ちましょう。
また「預かるよ」と言っておきながら、子どもが使いたい時に使えなければ、親子の信頼関係は崩れてしまいます。

「孫のために」と渡してくれた祖父母ら、贈り主の気持ちを尊重する意味でも、お年玉は子どもに管理させます。物欲をコントロールする力や計画性を身に付けるチャンスと考えてください。

通帳を子ども名義にすることで、「自分でお金を管理しよう」という意欲が高まります。また銀行の役割や預金の仕組みを学ぶことができます。


手元にあった現金が、通帳に記載された数字と一致していることを子どもに認識させます。


手元にたくさんのお金があると、いろんな物が欲しくなります。子どもが買いたいものと、その理由を聞きます。説明させることで、本当に必用な物かどうかを深く考えるようになります。
また大きな額のお金は、少額が積み重なって生まれた大切なものであること、将来の夢や目標を達成するための手段になることを説明します。
そうすることで、今欲しい物を買う以外にも、好きな習い事や学校の部活動のために使う、将来の学びのために預金するなど、さまざまな使い道が見えてきます。

どうやって使うかは、親子で話し合って決めてください。将来について話す中で、子どもが取り組んでみたいことを、親が知る機会にもなります。
教育費として預金した場合も、子どもに黙って使うのは避け、何にいくら使うのか具体的に話し、理解を得ます。あくまでも、子どもが主体的にお年玉に関わるのが理想です。

子どもがキャッシュレス決済をする場合には、○○Payで知られるスマホ決済、事前にチャージするプリペイドカード、銀行口座から購入時に引き落とされるデビットカードを使う方法がおすすめです。
○○Payの代表格、PayPayは銀行口座やクレジットカードの情報を登録しなくても、セブン銀行、ローソン銀行のATMでチャージ(入金)できます。さらに、親のスマホに登録しているPayPayの残高から子どもに送金することができて便利です。

子どもが買い物をしたら親にメールが届いたり、月の利用上限金額を設定できたりするカードもあり、親子で使いやすい方法を選びましょう。
失敗も含め実践が大切
世界的に進むキャッシュレス決済は、カードやスマホ一つで買い物ができるメリットがある一方、お金を使った感覚が薄く、使い過ぎることがあるかもしれません。
丹羽さんは「やりくりがうまくいかない時も出てくると思いますが、親はとにかく見守ってあげてください。失敗も含めて実践することが、子どもの教育には最も大切です」と強調します。