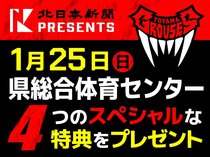①「扇状地」がよく分かる! 黒部川の愛本橋(黒部市宇奈月町下立)
富山県の特徴的な地形と言えば、高い山、急流河川、扇状地です。山と川は見れば分かりますが、「扇状地って何?」という子どもたちは多いかもしれません。そんな子どもたちにおすすめなのが、黒部川の中流に架かる「愛本橋」です。
扇状地を言葉で説明すると「川が平野に流れ出たところに、土砂が扇形に積もってできた地形」となりますが、この橋に立てば一目瞭然! 自分の立っている場所が、扇の要で、平野が海に向かってどんどん広くなっていくのがよく分かります。
車に気を付けて道路を渡り、橋から山側も見てみましょう。

この橋の周辺だけ、川幅がぎゅっと狭くなっていることが分かります。その理由は、橋の両岸の岩にあります。
詳しくは、橋の西側に立つ案内看板に書いてあります。ぜひここもチェックしてみてください。

②かつての黒部川の河床 崖の上に発見! 中ノ口緑地公園(黒部市宇奈月町中ノ口)
愛本橋で扇状地を見た後に訪れたのは、橋から少し下流にある中ノ口緑地公園です。ここでは黒部川が動いていた証拠を見つけることができます。
【解説します!】大地は動いている
恐竜がいた約1億5000万年前、日本列島はありませんでした。それが大陸の東の端が、ちょっとずつ裂けて日本海ができ、約300万年前に日本列島の原型ができます。そのころから立山連峰を含む飛騨山脈が、徐々に高くなっていきます。また立山黒部エリアは雨や雪が多く、急流河川もあり、水が豊富な地域です。これらの水の影響で大地が削られたりもし、現在の富山の地形ができました。
〈参考〉立山黒部ジオパークHP
黒部川周辺でも、大地が盛り上がったり、それによって川の流れが変わったりすることが繰り返され、川の流れに沿って階段のような地形をつくる「河岸段丘」ができました。中ノ口緑地公園は、その階段の一番下に位置し、次の段との境になる崖が北東側にあります。崖の高さは約30メートル。

崖は草や木に覆われていますが、上部をよく見ると、大きな石がごろごろと積み重なった地層が見えます。
これが約3万年前の黒部川の河床です。地図で現在の黒部川の位置と比べると、川がダイナミックに動いていたことを実感できますよ。
〈参考文献〉「歩いて手繰る 立山黒部ジオパーク見聞録」立山黒部ジオパーク協会 2020年