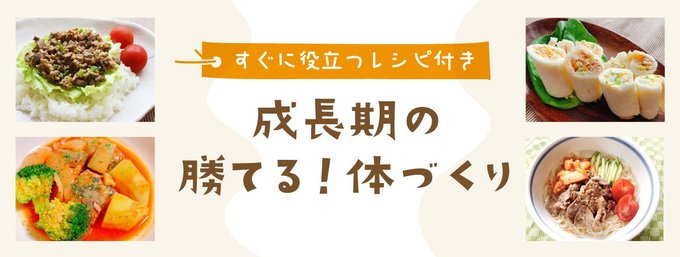食中毒が起こりやすい季節といえば、梅雨や夏を思い浮かべる人が多いと思いますが、冬にも多く発生しています。
今年は新型コロナウイルスの感染予防対策として手指のアルコール消毒をしっかりしている方は多いと思いますが、食中毒の観点から注意点を確認します。

冬の食中毒はウイルス性が多く、感染力が強く、集団発生しやすいのが特徴です。特に抵抗力の弱い子どもや高齢者には注意が必要です。
代表的なものがノロウイルスです。11月から2月に流行します。
二枚貝が原因食品と考える人が多いかもしれませんが、感染者が吐いた物や便、また感染者が作った料理などを介して人から人へと感染を広げていきます。
症状は下痢、嘔吐、吐き気、腹痛、微熱がみられます。潜伏期間は1~2日間。症状が治まっても、しばらくは注意が必要です。
【予防のポイント】
①手洗いの徹底

食事前、トイレの後、調理前後には、泡立てた石けんでよく洗い、流水で十分に流します。ためた水での手洗いはやめましょう。
② 消毒―人からの感染予防

感染した人の便やおう吐物からの二次感染、飛沫感染を予防する必要があります。
便や吐物などを扱う時は手袋やマスクを使用し、床やトイレ、洗面台を消毒するなど衛生管理が必要です。
消毒する場合は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)が有効です。ただし、金属腐食性があるので、消毒後には薬剤を十分に拭き取るよう注意してください。
③加熱―食品からの感染予防

画像提供:PIXTA
加熱して食べる食材は中心部までしっかりと火を通しましょう。中心部が85℃~90℃で90秒間以上の加熱が必要とされています。
また調理器具は消毒したり、使用後にはすぐに洗い流したりして清潔に保ちましょう。 調理器具の消毒には、熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱、または次亜塩素酸ナトリウムが有効です。
④健康管理
規則正しい生活、バランスの良い食事、適度な睡眠をとりましょう。
次回は、かきを使用した調理をご紹介します。
◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士
富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。
日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。