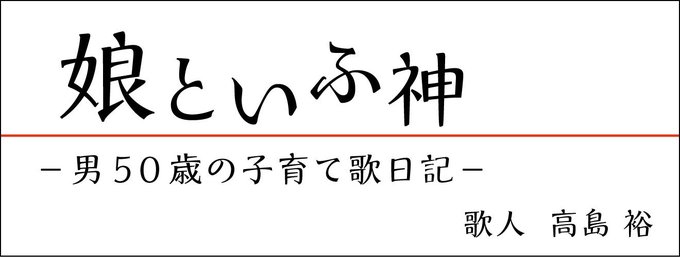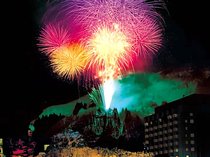二月の終わり。娘の三歳の誕生日が近づいていた。新型コロナウイルスの脅威が言われつつ、富山県内は、まだ今まで通りの日常が続いていた。ただ、誕生祝いのために、何か特別な場所に出かけることは憚られた。ケーキとお惣菜を買って妻の実家に行き、家の中で、みんなでご飯を食べてささやかにお祝いをした。
その翌日の日曜日の午後、みんなで運動公園に出かけ、シャボン玉やボールで娘を遊ばせた。その時、娘は、買ってもらったプラスティックのおもちゃのバットを思い切り振り回して、妻の顔にぶつけてしまった。すぐにぶつかったところを冷やして大事なかったが、娘は、痛がってうずくまる妻や、心配そうにタオルを冷やして持ってくるみんなの様子を見て、自分の行動が、大好きなお母さんを傷めてしまったことを理解したようだった。帰りの車の中でも「大丈夫?ごめんね」と言い、次の日の保育所でも、先生にこのことを話していたそうだ。自分が、大切な人に「悪いことをしてしまった」という気持ちが、その場限りでなく、記憶とともに持続していることに、三歳となった娘の心の成長と、「人格」の萌芽を見る思いがした。
三歳の空、ふり仰ぐ青空に雨を宿せるひとところあり

娘に人格が芽生えたところで、この連載は終わりを迎える。「三つ子の魂百まで」と言われる通り、三歳頃までに作り上げられた性向は、一生を貫く「人となり」となる。三歳となった娘は、小さいながら独立した人格と見なされねばならず、もはや親の視点からのみ語られるべき存在ではなくなった。
この連載をお読みいただいた方々の中には、私を「イクメン」だと思われる方がおられるかもしれない。しかし、私は、子育てに関わって自分が「何をしたか」については多くを語ったが、「何をしなかったか」については語っていない。
私は昭和に生まれ、戦前戦中を生きた高齢の両親に育てられた。男は家ではどっしり腰を落ち着けているべきで、女の領分である家事育児に立ち入ることは、むしろみっともないことだというような雰囲気の中で育った。こうした考え方が過去のものであることはわかっていても、ちょっとした所作や行動(あるいは行動しないこと)に、古い価値観が顔を出してしまうことは、今でも克服し切れずにいる。私は家事育児に関してはイクメンどころか、今の若い世代の平均的な父親にも及ばないだろう。
それでも、私なりに子育てに関わろうとする中で、古来、女たちが担ってきたものの重みと、苦しみと、喜びとを、少しは共有できたように思う。
そしてそれを通じて、文学を志す者として、ひとつの大きな問いに行き当たった。学問や文学芸術に携る者、とくに優れた業績を上げている者は、圧倒的に男が多い。優れた男性学者、男性作家たちはみな、その母や妻や恋人に家事育児一切を任せきりにして、自らの身の回りの世話までもさせることで、創作や研究のための時間を確保してきたのである。その事実は、創作や研究の質を規定し、限界づけているのではないか。今私たちの目の前に積み上げられた、学問や文学芸術の歴史的成果は、読書の暇もなく生命継受の営みを担い続けてきた女たちの現実には、一指だに触れ得ないのではないか。もっと言えば、今に残された学問や文学芸術のすべては、生命継受の現場から、根本的にその価値を問い直されるべきではないか。
そんな、あまりにも大きな問いに足元を揺さぶられつつ、日々成長し変化してゆく一つの生命に向き合う日々が、これからも続く。
おわり
◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。