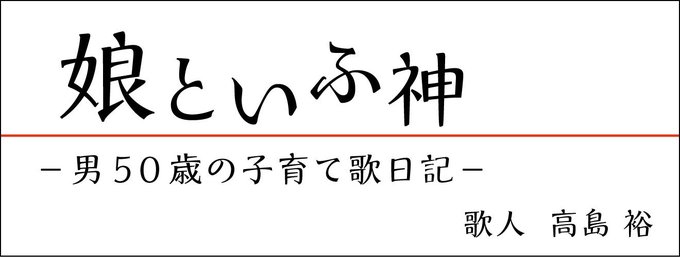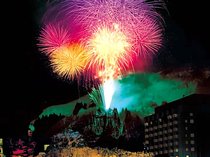産後五日で退院となった。母子ともに健康で何よりだった。以後しばらく、妻と娘、そして私自身もまた、妻の実家でお世話になることとなる。私は、毎日、一般道で片道一時間半かけて、職場に通った。
私も大変だったが、それ以上に大変だったのは、妻の方である。娘は、昼夜かかわりなく、真夜中にも泣く。そのたびに抱っこし、授乳し、ミルクを作って飲ませる。オムツも頻繁に替えないといけない。もちろん私も、夜には帰って寄り添い、妻をサポートした。けれどもそれは、ささやかな「お手伝い」でしかなかった。
産後一週間もすると、娘は、私の抱っこでは泣き止まなくなった。匂いや声や触れ合う感触などで、母親を判別しているのだ。いくら父親が頑張っても、赤ちゃんにとっては、これまでそのお腹の中にいた母親の方がいいに決まっている。そして、厳然たる自然の掟として、授乳は母親にしかできない仕事である。新米の父である私は、無力感と疎外感に打ちひしがれた。そして自分が役に立てておらず、育児の負担を妻ひとりに負わせていることに、申し訳なさを感じた。
一滴の乳を生(な)さざる男(をのこ)の身寂しきままに梅も過ぎたり
やがて妻は、不安とストレスと睡眠不足とで元気がなくなり、表情を失っていった。
そんな時、妻を支えてくれたのは、三人の子を育て上げた、妻のお母さんだった。豊かな経験から、手際よく、愛情こめて娘を世話してくださり、妻の睡眠時間を確保するために、夜間、娘を引き取ってくださったりもした。市の健康センターからの訪問があり、悩みを聞いてもらったりもして、妻は元気を取り戻した。私は、父親である自分の無力を後ろめたく感じた。
けれども、初めての育児は、私にとって、かけがえのない楽しみでもあった。専用の入れ物に哺乳瓶を入れ、少し水を差して電子レンジで温めて殺菌しておく。そこにミルクの粉末を入れ、熱湯で溶かす。それを外側から氷水で冷やし、人肌ほどにぬるくなったところで飲ませる。娘が泣いている中、ミルクがなかなか冷めず、いつも焦る。出来上がったミルクはほのかに黄味を帯びて、実にうまそうだ。娘を膝に横たえて、乳首をくわえさせ、哺乳瓶を傾けて飲ませる。目を見開いて、一生懸命に吸って飲む。飲み終えると、膝の上に座らせ、小さな背中をさすってげっぷをさせる。そのげっぷが、何とも言えず可愛い。
オムツを替えるのも、楽しい仕事だ。うんちは、母乳とミルクを合わせ飲んでいる赤ちゃんの、黄白色の水っぽいもの。大人の大便のような臭いもなく、少しも汚いとは思わなかった。もちろん使い捨ての紙オムツ。中が濡れると表に青いサインが現れる仕組みになっていて、替え時になったのがすぐにわかる。便利なものだ。布オムツを替えて洗濯していた、一昔前のお母さんたちの苦労が偲ばれる。赤ちゃんのお尻拭き専用のウエットペーパーがあって、それでお尻回りを優しく、丁寧に拭いてから、新しいオムツを穿かせる。
グループホームの母に娘が無事生まれたことを報告すると、認知症ながら理解して、涙を流して喜んだ。達筆だった母。認知能力が衰えてゆく中で、グループホームの職員のみなさんに助けられて、色紙に筆で「琳」と大きく書いてくれた。
娘が生れて一ヶ月が経ち、桜の季節となった。こんなに長く感じた三月は初めてだった。

◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。